
野崎まど『know』
ハヤカワ文庫JA 2013年
超情報化対策として、人造の脳葉“電子葉”の移植が義務化された2081年の日本・京都。情報庁で働く官僚の御野・連レルは、情報素子のコードのなかに恩師であり現在は行方不明の研究者、道終・常イチが残した暗号を発見する。その“啓示”に誘われた先で待っていたのは、ひとりの少女だった。道終の真意もわからぬまま、御野は「すべてを知る」ため彼女と行動をともにする。それは、世界が変わる4日間の始まりだった― (Amazon 内容紹介より)
=例会レポート=
「文学賞に応募してくる作家の中には、文章そのものは上手で読みやすいが、内容が何一つ記憶に残らないという書き手がいる。
そして、物語は極めて幼い。
そんな書き手は、アニメや漫画の原作を手がけている人に多く見られる。」
菊池先生が講評の中でおっしゃった言葉です。
今月の課題本は、野崎(「崎」のつくりは上が「立」)まどの『know』。
近未来の京都を舞台にしたサイバーパンク小説です。
情報技術の発達で、人々は脳に「電子葉」というチップを埋め込むことが義務付けられ、建物や什器や道路や庭木に塗布された情報材の助けを借りて、外部デバイス無しで自在に情報にアクセスできる。
したがって、彼らにとって「”Know” 知っている」というのは、「あらかじめその知識がある」という意味ではなく、「今すぐその情報をとりこめる」状態を指すようになっていた。
しかし、各人の電子葉のアクセス権限の多寡によって、あらたな厳然たる階級社会ができあがっていた。
内閣府の情報審議官である主人公は、その有り余る能力で出世コースを駆け上がり、絶大な情報アクセス権限を手にしているが、ある日、巨大情報通信社の訪問を受け、かつての師の謎の失踪に国家機密がからんでいたことを知り、自分も追われる羽目になるが――
物語はざっとこんな感じで進んでゆきますが、まずは集まった会員の皆さんの感想を聞いてみましょう。
―これっきりのアイデアで書くなら、短編小説のボリュームが妥当でしょうな
―「知識=情報量の多さ」、というのは、ちょっと違うんじゃないですか?
―得られる情報量の違いで起きる社会格差を、もっとおもしろく書けなかったかなぁ
―どうせ読むなら、「そういう世界なら行ってみたい」と思うような未来を読みたいものです
―今日は「この本のどこがおもしろかったか」を皆さんに伺おうと思って参上したのですが
―だいたいですね、カタカナを多用する日本の小説で、僕はこれまでにいいものにあたった験しがない
―中高生向き。この作品に何かを求めてもしょうがないですよ
―小説を読んでいるのではなく、アニメを観ていると思えばよろしいのでは?
―でも文章が巧いからスラスラ読んでしまった
―「クラス*」を出してきたのは大失敗
―いやむしろそこがおもしろかったです
―銃弾の中を盛装してダンスしながら建礼門を通る場面が、バカバカしくていいじゃないですか
―こんな内容を、衒いもなく書けるなんて。ぼかァ、恥ずかしくってとてもとても・・
―いや~おもしろかったぁ! 10日経ったら全部忘れちゃったけど
・・・あらあら。
大半の皆さんのお顔に「Mさんはどうしてこの本を推薦したんだろう?」という疑問符が貼り付いていたようでしたよ。今月の課題本は、先月特別ゲストとしてお越しくださった、前講師、文芸評論家のM氏の推薦によるものだったのです。
『魔の山』から『掏摸』、はたまた『ヤシ酒飲み』や『蜜のあはれ』まで、自在に読み漁るおも本会員にとって、この課題本は一種のトンデモ小説だったかもしれません。
しかし、Kさん曰く「趣味が合っててちゃんと付き合ってるパートナーはいるけれど、ちょっと浮気をしてみたらそのひと時の快楽が意外によかった」的な読書も、たまにはいいのではないでしょうか。
(作者なら「浮気」のところに ”One Night Stand”とルビを振って、またそれが恥ずかしい!と読者の顰蹙を買うかもしれませんが。)
ちなみに、京都に詳しいTさんによると、冒頭に出てくる行きずりの女の子と主人公とは、お互い上京区の意外に近いところに住んでいるようすで、もしかすると街ですれ違っちゃうかも?というお話でした。
脇が甘いですぞ、審議官。
Tさん提供のトリビアをもう一つご紹介すると、連レル、知ル、問ウといった動詞を使った名前は、平家物語に出てくる関東武者に多いんですって。
作者なりに、古めかしさを出そうとしているのかしら?というのがTさんの見立てでした。
さて、作者がエヴァンゲリオンの綾波レイに対抗する気マンマンで書いたであろうことが恥ずかしいまでに想像されるヒロイン「知ル」は、制服を着ているかドレスを身につけているか、あるいは裸で主人公と何かをしているというサービス精神溢るゝ人物であるわけですが、彼女を含めた登場人物全員がひとっつも葛藤や疑問を搭載していない、単なる情報の受け皿(ここに ”Memory”とルビを振ってね)であったことは、残念でなりません。
彼らが「死」の謎を解いたところで、一体どうなるのでしょう。
かくのごとくに、小説家の思いつきと作品のあいだには、お話を進める文章力だけでなく、物語を編む豊穣な想像力との両方が備わっていないことには、このような数時間の浮気の相手だけが量産されてしまうのだという厳しい現実を、私たちはあらためて知らされたと言えないでしょうか。
映像やセル画の助けを初めから期待してしまっているものを、小説と呼んでよいものかどうか。
ここで、作者の想像が及ばなかったであろうある点について、菊池先生がスルドイ指摘をくださいました。
「この時代には、認知症はもはやなくなっているだろうなぁ」
・・・嗚呼、そうです!
ここに明るいミライが、ちょっとだけ仄見えるじゃありませんか。
Viva! 電脳化社会。
けれど、死後の世界から戻ってくる情報の舟があっても、私はそれに乗ろうとは思わないなぁ。










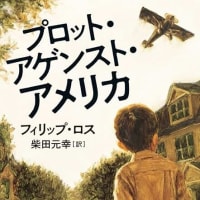
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます