相談員の高橋です。
音羽台レジデンスには会議室があります。会議室ですので会議をしたり、研修をしたり。時にはコンサート会場になってみたり、荷物置き場になってみたり、講座の会場になってみたり。色々と役割を持ってくれています。ただし、あまり大きくないけれど、仕方がない。
最近の会議室の活躍を少し紹介します。
まずは、王道の研修。
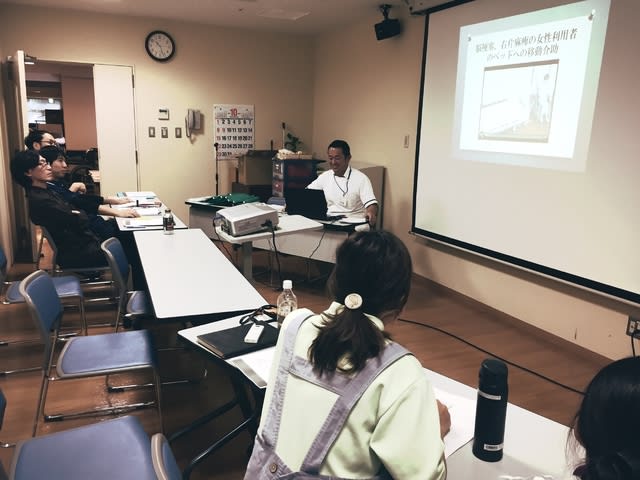
毎月、介護保険施設で働く上で必要な知識を得るための研修を行っています。全ての職員さんが参加するのは難しい現状でどうしたら一人でも多くの方が出られるのか、悩みに悩んで出た今の方法が「月曜日〜金曜日の午前と午後の90分を使って同じ研修を繰り返し行う」でした。講師役の職員さんもありがとうございます。同じ講義を9コマ行います。これも決定打にはなりませんが、それでも60人位の方は参加できるようになりました。でも、参加できない方もいて、夕方に実施する等の工夫が必要です。出席できなかった職員の皆さんすみません。資料だけは配布します。また同じ研修を他の時間で行うなどの工夫をさせていただきますのでお待ちください。
職員会議も行います。
これは看護チームの話し合いの風景。

ISOの取得に向け、今、看護チームでは誰にでもわかる手順書を作っています。看護チームでは毎日、朝、夕にカンファを行い情報共有やケースカンファを行う他、週に2回はこの手順書を皆で作るためのカンファをしています。皆で手順を確認しながら作りますが、人によって手順も解釈も違っていたことの発見も多く、特養のような大きな組織における「共通のルール」の重要性を再確認しています。やはり、特養という組織は大きい。
こちらは相談室の話し合いの風景。

相談室では月に2回の会議を開催しています。主にケースカンファを中心に行います。ケースカンファを行うことで、情報共有はもとより、お互いの援助方法についての意見を出し合うことで自分たちの学びの場としています。また、外部研修に出た際には、その伝達研修の場としています。この写真は、立教大学の社会福祉学科の学生の実習発表の際の風景です。社会福祉士を目指す学生が約2ヶ月間(180時間)相談室に入り実習を行います。地域の社会資源を学ぶと同時に、社会福祉士としての援助技法を学んだり、実際に地域で働く相談員たちの活躍を目で見て肌で感じて学びます。そして特養内では、特定の入居者様について、アセスメントからプランの立案を行い実行し、モニタリングまで行う…という、学生さんにとっても、指導者にとっても、なかなか期間的にも厳しいてんこ盛りの課題を持ってきます。
そして、最終日には、特養での実習についての発表をします。学生さんなりに一生懸命に考え、悩みに悩んで、入居者さんに教わりながら「自立支援とは」「尊厳とは」「コミュニケーションとは」「傾聴と受容とは」なんてことを考えながら「自分を知る=自己覚知」へと迫ります。今の精一杯を表現してくれる学生を見るとこちらも感動してしまいます。毎回、泣けます。
何の話でしたっけ。会議室の話だったはず。すみません。思わず長いブログになってしまいました。おつきあいありがとうございました。
音羽台レジデンスには会議室があります。会議室ですので会議をしたり、研修をしたり。時にはコンサート会場になってみたり、荷物置き場になってみたり、講座の会場になってみたり。色々と役割を持ってくれています。ただし、あまり大きくないけれど、仕方がない。
最近の会議室の活躍を少し紹介します。
まずは、王道の研修。
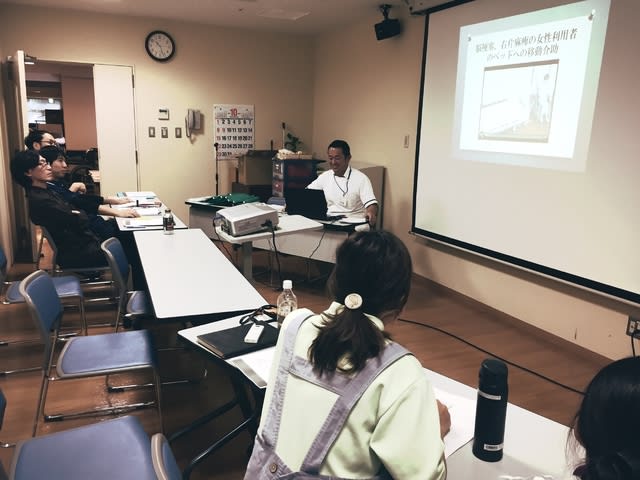
毎月、介護保険施設で働く上で必要な知識を得るための研修を行っています。全ての職員さんが参加するのは難しい現状でどうしたら一人でも多くの方が出られるのか、悩みに悩んで出た今の方法が「月曜日〜金曜日の午前と午後の90分を使って同じ研修を繰り返し行う」でした。講師役の職員さんもありがとうございます。同じ講義を9コマ行います。これも決定打にはなりませんが、それでも60人位の方は参加できるようになりました。でも、参加できない方もいて、夕方に実施する等の工夫が必要です。出席できなかった職員の皆さんすみません。資料だけは配布します。また同じ研修を他の時間で行うなどの工夫をさせていただきますのでお待ちください。
職員会議も行います。
これは看護チームの話し合いの風景。

ISOの取得に向け、今、看護チームでは誰にでもわかる手順書を作っています。看護チームでは毎日、朝、夕にカンファを行い情報共有やケースカンファを行う他、週に2回はこの手順書を皆で作るためのカンファをしています。皆で手順を確認しながら作りますが、人によって手順も解釈も違っていたことの発見も多く、特養のような大きな組織における「共通のルール」の重要性を再確認しています。やはり、特養という組織は大きい。
こちらは相談室の話し合いの風景。

相談室では月に2回の会議を開催しています。主にケースカンファを中心に行います。ケースカンファを行うことで、情報共有はもとより、お互いの援助方法についての意見を出し合うことで自分たちの学びの場としています。また、外部研修に出た際には、その伝達研修の場としています。この写真は、立教大学の社会福祉学科の学生の実習発表の際の風景です。社会福祉士を目指す学生が約2ヶ月間(180時間)相談室に入り実習を行います。地域の社会資源を学ぶと同時に、社会福祉士としての援助技法を学んだり、実際に地域で働く相談員たちの活躍を目で見て肌で感じて学びます。そして特養内では、特定の入居者様について、アセスメントからプランの立案を行い実行し、モニタリングまで行う…という、学生さんにとっても、指導者にとっても、なかなか期間的にも厳しいてんこ盛りの課題を持ってきます。
そして、最終日には、特養での実習についての発表をします。学生さんなりに一生懸命に考え、悩みに悩んで、入居者さんに教わりながら「自立支援とは」「尊厳とは」「コミュニケーションとは」「傾聴と受容とは」なんてことを考えながら「自分を知る=自己覚知」へと迫ります。今の精一杯を表現してくれる学生を見るとこちらも感動してしまいます。毎回、泣けます。
何の話でしたっけ。会議室の話だったはず。すみません。思わず長いブログになってしまいました。おつきあいありがとうございました。















