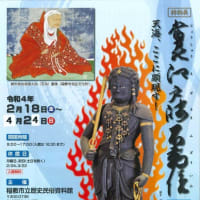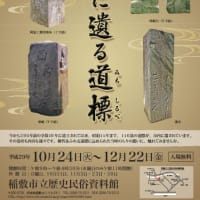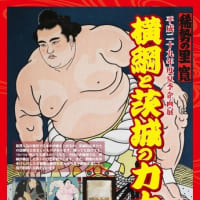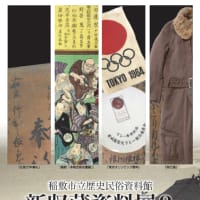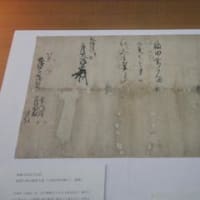江戸崎不動院の草創について(2)
前回は、江戸崎不動院が文明2年(1470)に比叡山
無動寺の、幸誉法印権大僧都を開山として創建されまし
たが、その当時のご開基さまがわからない、というお話
をしました。
実際に文明年間のそてれが不動院の草創なのか、中興
開山なのか、決め手となる文書資料や出土遺物が無い
ため、はっきりしたことは分かりません。
前回紹介しました、「医王山過去帳」(№2)や『不動院
記録』に収録された「先師代々位牌写」№3)には、幸誉
法印が護持してきた不動明王についての説明がありますの
で、今回はその由来について触れたいと思います。
(№2)も(№3)も、不動院開山僧幸誉が持参したのは、
無動寺開山僧・相応作の不動明王と記しています。
そして、弘化4年(1847)の『不動堂石坂鋪石勧化記』
(№5)や明治17年(1884)『不動堂再建募縁記』
(№6)には、本尊の不動明王が慈覚大師円仁親刻の尊像
と記されています。

比叡山無動寺といいますと、千日回峰行の荒行で知られて
いますが、その本尊が相応作の不動明王です。
また、慈覚大師円仁は、日本天台宗を起こした最澄の高弟
で、比叡山延暦寺を本寺とする山門派の祖となった人物です。
このように不動院の本尊である不動明王は、相応和尚や円仁
とのゆかりを持つものと考えられてきたようで、比叡山、つ
まり山門派の霊験あらたかな不動明王として信仰されてきました。
(№5)では、慈覚大師円仁の親刻、無動寺相応和尚所持と
していますが、この説明ですと両者とのゆかりが説明できそう
ですね。
ただし、現在の不動院のご本尊さま(№1)は、鎌倉時代の作と
されていますので、相応和尚や円仁とは時代が異なるようです。

前回は、江戸崎不動院が文明2年(1470)に比叡山
無動寺の、幸誉法印権大僧都を開山として創建されまし
たが、その当時のご開基さまがわからない、というお話
をしました。
実際に文明年間のそてれが不動院の草創なのか、中興
開山なのか、決め手となる文書資料や出土遺物が無い
ため、はっきりしたことは分かりません。
前回紹介しました、「医王山過去帳」(№2)や『不動院
記録』に収録された「先師代々位牌写」№3)には、幸誉
法印が護持してきた不動明王についての説明がありますの
で、今回はその由来について触れたいと思います。
(№2)も(№3)も、不動院開山僧幸誉が持参したのは、
無動寺開山僧・相応作の不動明王と記しています。
そして、弘化4年(1847)の『不動堂石坂鋪石勧化記』
(№5)や明治17年(1884)『不動堂再建募縁記』
(№6)には、本尊の不動明王が慈覚大師円仁親刻の尊像
と記されています。

比叡山無動寺といいますと、千日回峰行の荒行で知られて
いますが、その本尊が相応作の不動明王です。
また、慈覚大師円仁は、日本天台宗を起こした最澄の高弟
で、比叡山延暦寺を本寺とする山門派の祖となった人物です。
このように不動院の本尊である不動明王は、相応和尚や円仁
とのゆかりを持つものと考えられてきたようで、比叡山、つ
まり山門派の霊験あらたかな不動明王として信仰されてきました。
(№5)では、慈覚大師円仁の親刻、無動寺相応和尚所持と
していますが、この説明ですと両者とのゆかりが説明できそう
ですね。
ただし、現在の不動院のご本尊さま(№1)は、鎌倉時代の作と
されていますので、相応和尚や円仁とは時代が異なるようです。