
茶道で、茶碗を湯や水ですすいだあと
その湯や水をすてる先が建水(けんすい)。
きょうは珍しい槍鞘(やりのさや)という建水を使わせていただきました。
やわらかい曲線にスリムボディ。
高さがあるものですから
湯や水をすてるとなんともいえない音を楽しめます。
槍鞘の上にのっているのは
釜の蓋を置く蓋置(ふたおき)と柄杓。
この蓋置にも遊び心があって
なかに鈴が入っているのです。
なので持ち運びすると
チリコロチリコロ・・・
駅鈴(えきれい)という名前がついています。
駅鈴は、律令制の下、官人が公務出張のときに
朝廷から支給された鈴。
駅馬を使用するための許可証であり、
これを振り鳴らして駅馬や駅子を徴発したそうです。
そんな駅鈴を茶道具にとり入れるなんて面白いなぁ。










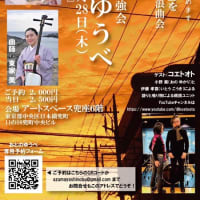



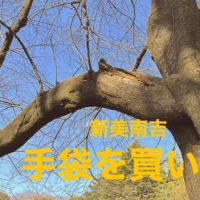






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます