岡崎城は、いわずとしれた徳川家康の生誕の地です。
現在の地に有った西郷氏の砦を松平清康が城郭として築き直したとされます。
その孫の徳川家康も若き城主として岡崎城で勢力を伸ばし浜松、駿府、江戸へと
羽ばたいたのは皆さんご存知のとおりです。
岡崎城は家康の城というイメージが強いのですが、今見ることが出来る岡崎城は
家康の関東移封後に入部した豊臣方の田中吉政の時代にその基礎が築かれました。
江戸時代を通じて度々城主が変わり、変化した部分もありますが、城下の街造り
と合わせて、田中吉政の構想が元になっています。
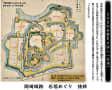 岡崎城絵図とマップ位置の図 抜粋 クリックで拡大
岡崎城絵図とマップ位置の図 抜粋 クリックで拡大
このたび岡崎城の石垣を23箇所紹介し、石垣をめぐる案内マップが
愛知県岡崎市公式観光サイトにPDFファイルでアップされましたのでご覧ください。
A3版裏表カラーです。 岡崎城には216面の石垣が残されているそうですが、
主だったものが紹介されています。
 天守石垣と鏡石
天守石垣と鏡石
岡崎城で最も古い田中吉政時代の石垣といわれているのは、天守台の石垣です。
鏡石も備えて、豊臣の権威を示していたのかもしれません。
 石垣と土の青海堀
石垣と土の青海堀
青海堀は岡崎城で最も古い堀遺構といわれ、本来は土の堀です。
後の時代に石垣を積んだようで、堀に石垣と土の切岸が残ります。
一部には石垣のない、原型と思われる土だけの青海堀も残っています。

全長400m 菅生川端石垣
江戸期に入ってからの石垣で、今は菅生(すごう)川に面していますが往時は
堀状の水面と中洲があり、その向こう側を川が流れていたようです。
発掘調査によれば、全高5mの石垣が連なっていたようですが、今は埋め戻されて
高さを実感することは出来ません。
 坂谷門を伊賀川越しに見る
坂谷門を伊賀川越しに見る
伊賀川の流路はしばしば変えられており、今の流路は現代の開削によるものです。
今の流れがある場所には堀がありその手前には白山曲輪がありました。
写真奥が坂谷曲輪で、左手方向に家康が誕生した屋敷が有ったとされ、産湯の
井戸が今も大切に保存されています。
地元では、これまで田中吉政は、寺領を取り上げ、移転を強要し、従わないと破却した
「悪いやつ」と言う人物評が定着していましたが、実際には現在の岡崎の街造りに
貢献した「良い人」だったのではという再評価が最近になって行われるようになりました。
岡崎は日本三大石都といわれ、花崗岩の産地で今でも石材店が多くあります。
田中吉政が河内・和泉の石工を城下に呼び寄せたのが始まりとされ、ここでも
後世まで続く産業の礎を築いた人物だったことが判ります。
城の石垣を積むためだけに地元の花崗岩を使ったのでは無かったのですね。
現在の地に有った西郷氏の砦を松平清康が城郭として築き直したとされます。
その孫の徳川家康も若き城主として岡崎城で勢力を伸ばし浜松、駿府、江戸へと
羽ばたいたのは皆さんご存知のとおりです。
岡崎城は家康の城というイメージが強いのですが、今見ることが出来る岡崎城は
家康の関東移封後に入部した豊臣方の田中吉政の時代にその基礎が築かれました。
江戸時代を通じて度々城主が変わり、変化した部分もありますが、城下の街造り
と合わせて、田中吉政の構想が元になっています。
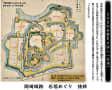 岡崎城絵図とマップ位置の図 抜粋 クリックで拡大
岡崎城絵図とマップ位置の図 抜粋 クリックで拡大このたび岡崎城の石垣を23箇所紹介し、石垣をめぐる案内マップが
愛知県岡崎市公式観光サイトにPDFファイルでアップされましたのでご覧ください。
A3版裏表カラーです。 岡崎城には216面の石垣が残されているそうですが、
主だったものが紹介されています。
 天守石垣と鏡石
天守石垣と鏡石岡崎城で最も古い田中吉政時代の石垣といわれているのは、天守台の石垣です。
鏡石も備えて、豊臣の権威を示していたのかもしれません。
 石垣と土の青海堀
石垣と土の青海堀青海堀は岡崎城で最も古い堀遺構といわれ、本来は土の堀です。
後の時代に石垣を積んだようで、堀に石垣と土の切岸が残ります。
一部には石垣のない、原型と思われる土だけの青海堀も残っています。

全長400m 菅生川端石垣
江戸期に入ってからの石垣で、今は菅生(すごう)川に面していますが往時は
堀状の水面と中洲があり、その向こう側を川が流れていたようです。
発掘調査によれば、全高5mの石垣が連なっていたようですが、今は埋め戻されて
高さを実感することは出来ません。
 坂谷門を伊賀川越しに見る
坂谷門を伊賀川越しに見る伊賀川の流路はしばしば変えられており、今の流路は現代の開削によるものです。
今の流れがある場所には堀がありその手前には白山曲輪がありました。
写真奥が坂谷曲輪で、左手方向に家康が誕生した屋敷が有ったとされ、産湯の
井戸が今も大切に保存されています。
地元では、これまで田中吉政は、寺領を取り上げ、移転を強要し、従わないと破却した
「悪いやつ」と言う人物評が定着していましたが、実際には現在の岡崎の街造りに
貢献した「良い人」だったのではという再評価が最近になって行われるようになりました。
岡崎は日本三大石都といわれ、花崗岩の産地で今でも石材店が多くあります。
田中吉政が河内・和泉の石工を城下に呼び寄せたのが始まりとされ、ここでも
後世まで続く産業の礎を築いた人物だったことが判ります。
城の石垣を積むためだけに地元の花崗岩を使ったのでは無かったのですね。










