=====
これは、東京在住 アラサーOLが、ぐるっとパス2018のチケットを有効期限のその日まで、どれだけ活用できるかという静かなる戦いの記録である。
=====
江戸東京博物館を出て、ツツジまだ咲いてるかも〜などと思い、旧安田庭園に寄ることにしました。

新緑!青鷺発見!
葉は青々と茂って、ツツジはこの暑さですぐ傷んでしまいそうでした。
さて、次に向かうは刀剣博物館。
旧安田庭園出てすぐです。初めてだー

おお、外観も刀剣っぽい。
こちらではただ今「第63回 重要刀剣等指定展」を見ることができます。
東京国立博物館の刀剣コーナーで見るぐらいしか経験のない私、もちろん知識も全くなく入場…
展示室はひとつだけですが、人が結構いました。
しかも老若男女。カップルや、女子二人連れも。
受付で、『日本刀の基礎知識』というパンフレットをもらえるので刀剣に関する簡単な予備知識はおさらいすることができます。
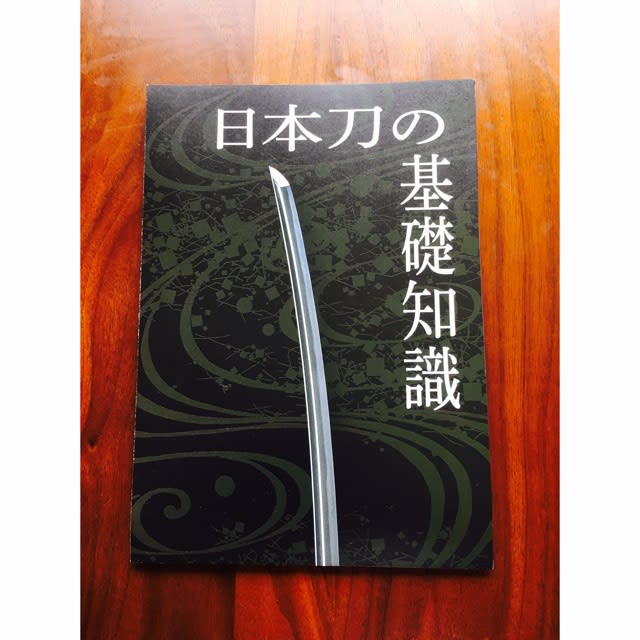
とは言っても、そこに書いてある地鉄や刃文についての記述が、目の前にある作品ではどうなのか素人にはあんまりわかりません。
隣でみている詳しそうなおじいさんに話しかけて教えてもらいたい気持ちを抑えつつ、部屋を一周。
パンフレットを見直して、もう一度じっとりみながらもう一周。。ぱっと見だと長さ以外そんなに違いがないように見えた刀たちに、違いがみえてきました(本当)!
数年前からの刀剣ブーム、なにがそんなに人を惹きつけるのかなと思ってましたが、この「実は違う」ところを見分けるのが面白いのかな。
シンプルな作品の中に、作者や時代による微妙な違いや、受ける印象の違いがあることを知りました。
あとは、歴史好きな人がはまるのかな。
私はどちらかというと、美術品としての刀剣鑑賞に興味がわきました。
1階には、日本刀を作る伝統技術についての展示もありました。
鉄の塊をカンカン叩いて伸ばして刀にしてるんでしょ、と思っていたけど、複雑で手間のかかる工程がたくさんあることを知りました。
驚いた工程のひとつは、鉄の塊をまるで折り紙でもするみたいに何度も折りたたむ作業をしていること!
ちなみに、日本刀作りに使われるとくに品質の良い鉄の塊は『玉鋼たまはがね』と言うようです。
ここの展示には玉鋼以降の説明だけでしたが、帰ってからちょっと調べたら、玉鋼を作り出す製鉄技術もかなり高度で謎につつまれたものだったよう。奥出雲のいくつかの家系に世襲制で伝わった製鉄技術。。究極の職人仕事ですね。
何度も折りたたんだ玉鋼を切ってから並べて加熱、鍛える。この作業の加減によって、日本刀表面に表れる模様が変わってくるそう。
そしてまた驚いた工程が、玉鋼は芯の部分と外側の部分を別に作って組み合わせているというところ。これによって十分な強度としなやかさが共存するらしい。矛盾する働きの二つが一つの刀に共存するとは不思議。
いま日本刀を切るために使う人はいないから必要ない工程な気もするけど、こういう複雑なところも無くさないのが技術の継承っていうのかな。
そして玉鋼を熱して水に入れる焼き入れによって、刀を丈夫にし切れ味を良くしていく…この作業のときに刃文が現れるそう。
水に入れたらって、それじゃあさっきの展示室で刃文についていろんなコメントがあったけど、けっこう不確かな偶然できた模様について語っていたのか!と驚きました。
名職人だとそれなりに加減できたのかもしれないけど、同じ模様は絶対二度と出ないよなぁ。
そういう人為的なものだけでは説明できない産物が日本刀なんだな、と理解しました。
うーん 奥が深いし、また博物館で日本刀をみるのが楽しみになってきたぞ。
刀剣博物館
『第63回 重要刀剣等指定展』
1,000YEN→ぐるっとパスによりFREE!
これは、東京在住 アラサーOLが、ぐるっとパス2018のチケットを有効期限のその日まで、どれだけ活用できるかという静かなる戦いの記録である。
=====
江戸東京博物館を出て、ツツジまだ咲いてるかも〜などと思い、旧安田庭園に寄ることにしました。

新緑!青鷺発見!
葉は青々と茂って、ツツジはこの暑さですぐ傷んでしまいそうでした。
さて、次に向かうは刀剣博物館。
旧安田庭園出てすぐです。初めてだー

おお、外観も刀剣っぽい。
こちらではただ今「第63回 重要刀剣等指定展」を見ることができます。
東京国立博物館の刀剣コーナーで見るぐらいしか経験のない私、もちろん知識も全くなく入場…
展示室はひとつだけですが、人が結構いました。
しかも老若男女。カップルや、女子二人連れも。
受付で、『日本刀の基礎知識』というパンフレットをもらえるので刀剣に関する簡単な予備知識はおさらいすることができます。
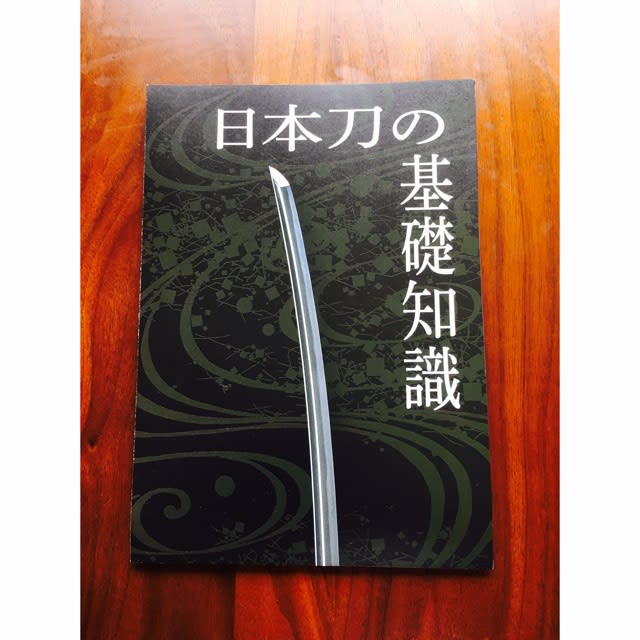
とは言っても、そこに書いてある地鉄や刃文についての記述が、目の前にある作品ではどうなのか素人にはあんまりわかりません。
隣でみている詳しそうなおじいさんに話しかけて教えてもらいたい気持ちを抑えつつ、部屋を一周。
パンフレットを見直して、もう一度じっとりみながらもう一周。。ぱっと見だと長さ以外そんなに違いがないように見えた刀たちに、違いがみえてきました(本当)!
数年前からの刀剣ブーム、なにがそんなに人を惹きつけるのかなと思ってましたが、この「実は違う」ところを見分けるのが面白いのかな。
シンプルな作品の中に、作者や時代による微妙な違いや、受ける印象の違いがあることを知りました。
あとは、歴史好きな人がはまるのかな。
私はどちらかというと、美術品としての刀剣鑑賞に興味がわきました。
1階には、日本刀を作る伝統技術についての展示もありました。
鉄の塊をカンカン叩いて伸ばして刀にしてるんでしょ、と思っていたけど、複雑で手間のかかる工程がたくさんあることを知りました。
驚いた工程のひとつは、鉄の塊をまるで折り紙でもするみたいに何度も折りたたむ作業をしていること!
ちなみに、日本刀作りに使われるとくに品質の良い鉄の塊は『玉鋼たまはがね』と言うようです。
ここの展示には玉鋼以降の説明だけでしたが、帰ってからちょっと調べたら、玉鋼を作り出す製鉄技術もかなり高度で謎につつまれたものだったよう。奥出雲のいくつかの家系に世襲制で伝わった製鉄技術。。究極の職人仕事ですね。
何度も折りたたんだ玉鋼を切ってから並べて加熱、鍛える。この作業の加減によって、日本刀表面に表れる模様が変わってくるそう。
そしてまた驚いた工程が、玉鋼は芯の部分と外側の部分を別に作って組み合わせているというところ。これによって十分な強度としなやかさが共存するらしい。矛盾する働きの二つが一つの刀に共存するとは不思議。
いま日本刀を切るために使う人はいないから必要ない工程な気もするけど、こういう複雑なところも無くさないのが技術の継承っていうのかな。
そして玉鋼を熱して水に入れる焼き入れによって、刀を丈夫にし切れ味を良くしていく…この作業のときに刃文が現れるそう。
水に入れたらって、それじゃあさっきの展示室で刃文についていろんなコメントがあったけど、けっこう不確かな偶然できた模様について語っていたのか!と驚きました。
名職人だとそれなりに加減できたのかもしれないけど、同じ模様は絶対二度と出ないよなぁ。
そういう人為的なものだけでは説明できない産物が日本刀なんだな、と理解しました。
うーん 奥が深いし、また博物館で日本刀をみるのが楽しみになってきたぞ。
刀剣博物館
『第63回 重要刀剣等指定展』
1,000YEN→ぐるっとパスによりFREE!


















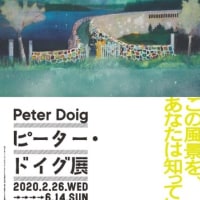

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます