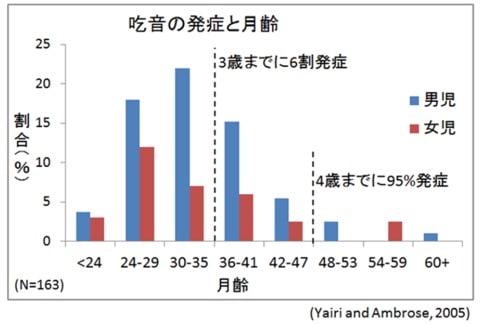⒈ 自分に正直な人生を生きればよかった
他人に期待された通りの人生を送らない。
不健全な関係は断ち切り、「もうたくさん」と言える意志の強さも大切。
自分の幸せに責任を持つことが、大切な出発点。
⒉ 働き過ぎなければよかった
最期を迎えた人が一番大切だと思うのは、愛する人をどれだけ幸せにできたか、自分は好きなことにどれだけの時間を費やせたかだ。
シンプルな生活は所有物や他人の評価などで自分の価値を確認しなくてもいられるようになる。
⒊ 思い切って自分の気持ちを伝えればよかった
自分がどれだけ生きられるか、愛する人がいつまでこの世にいてくれるのか分からない。
相手の反応は予想できない。けれど正直に話しはじめたことに驚かれても、最後には以前よりずっと健全な関係を築けるだろう。そうでない場合は、その人との関係は不健全だから断ち切るべきだ。
⒋ 友人と連絡を取り続ければよかった
本当に大事な人や、一番大好きな人とは、どんな努力をしてでも連絡を取りつづける価値がある。
最後に大切なのは愛情と人間関係だけだ。
死に直面していてもいなくても、最悪の時に笑わせてくれるのは友人たちだけだ。
⒌ 幸せをあきらめなければよかった
幸せになるには自分の意志が大切。
幸せになるには、毎日の行動すべてに感謝をすることが大切。
人はなにかがうまくいけば幸せになれると考えがちだが、その反対もある。幸せを感じていれば、物事がうまくいくこともあるのだ。
幸せは自分で選ぶものであると知れば人生の荒波にもみくちゃにされることもなくなる。
今、自分の人生をあらためて考えるのはとても重要だ。
自分の人生を変える選択をし、自分の心のままに生きる強さを持ち、後悔せずに死ねるように生きるべきだ。
それにはまず他人にも自分にも優しくなり、許せるようになればいい。自分を許すことはとても重要だ。
選ぶのは自分だ。
人生は自分だけのものだ。