日本は、1944年の「ブレトンウッズ体制(「IMF体制」や「金・ドル本位制」とも呼ばれ、ブレトンウッズ協定や「関税及び貿易に関する一般協定」による通貨・金融・貿易の国際経済体制をいう)」で1$=360円の固定相場制となりましたが、1971年の米国のリチャード・ニクソン大統領が1971年8月15日に、テレビとラジオで全米に向けて、新経済政策(減税と歳出削減、雇用促進策、価格政策の発動、金ドル交換停止、10%の輸入課徴金の導入)を電撃的に発表し、其の中の「金ドル交換停止(金とドルとの固定比率での交換停止)」のことによりブレトンウッズ体制が崩壊した後、「変動相場制」へと移行しました。
「変動相場制」とは、固定相場制の様に通貨を一定比率に固定せず、為替レートの決定を外為市場(マーケット)の需要と供給により自由に変動させる制度をいいます。此れは、マーケットで外貨通貨を対価とする自国通貨の売りが増えれば、自国通貨の対外価値が減価し、逆に外国通貨の売りが増えれば、自国通貨の対外価値が上昇(増価)するといった仕組みに成っています。
日本は固定相場制の下では相当「円安(1$=360円)」だったのだが、今日は1$=90~150円の幅にあるから、此れと比べると同じ$で、固定相場制だった頃の方が沢山の「円」を買えたのです。詰まり、商品「円」が沢山買える、詰まり「円」は安い商品だった。
従って、「円安」だった固定相場制だった日本は「輸出がし易い」国であった。
逆に、米国は「輸入し易く、輸出し難い国だった」と言うことに成る。敗戦によって日本は経済的に出口を見出せ無程の状況に追い込まれたが、米国は日本を経済的に強くすることで、所謂「勝共」の役割を日本に期待して円安の固定相場制を認めて居たが、日本経済が強く成るにつれて米国は、日本の経済力の伸長に危機感を持つ様に成ったのだ。実際は、固定相場制の中で何度か為替レイトを変えたが、米国は滔々「変動相場制」に変える決断をしざるを得無く成った。次に、「購買平価説」について説明する。
「購買力平価説」
此れは、「二国間でも同じものが買える様にする『為替レート』が決まる」という有名な「為替レート決定理論」である。
長期に亘る為替レートの決定理論で、スウェーデンの経済学者カッセル氏によって提唱された。購買力平価説には、「絶対的購買力平価説」と「相対的購買力平価説」がある。
前者の「絶対的購買力平価説」は、為替レートは2国間の通貨の購買力によって決定されるという説である。具体的には、例えば米国では1$で買えるハンバーガーが日本では100円で買えるとするとき、1$と100円では同じものが買える(詰まり1$と100円の購買力は等しい)ので、為替レートは1ドル=100円が妥当だという考え方である。然し、この説が成立するには総ての財やサービスが自由に貿易されなければ成らないから、厳密には成り立た無い。
一方、後者の「相対的購買力平価説」は、為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定されるという説である。具体的には、或る国の物価上昇率が他の国より相対的に高い場合、其の国の通貨価値は減価する為、為替レートは下落するという考え方です。然し乍ら、此の説も総ての財やサービスが同じ割合で変動することを前提として居る為、厳密には成り立た無いことに成る。
もう少し、分かり易く説明すると、
マクドナルドのハンガーが米国で2$、日本で300円だとすると、米国と日本で同じ「マクドナルドのハンガー」を買うのに。
2$=300円(1$=150円換算)
と成る。此処で、米国で4$、日本で600円ならば
4$=600円(1$=150円換算)
と成る。此の様な仕組みで「為替レート」が決まるとして居るのが「購買力平価説」である👉「購買力(買える物の量)」が「平価(同じ価値)」に成るというのが「『購買力平価説』である」とする。
実際には、此の様に一つの商品で比べることをし無いで、出来る限り多くの商品を買うと想定して、同じ量買える様に調整される。
もう少し、詳しく説明すると、
もし、前述のハンバーガーが米国では2$、日本では300円なのに、為替レートが1$=100円だったら
此のハンバーグは米国では2$=200円で買えるが、この値段で米国で買ったハンバーガーを日本に持って来て売ったならば、300円で売れるので100円儲かることに成る。
👆
輸送費は無視。実際にはハンバーグを持って来るのは無理。
此れでは美味し過ぎる商売と成る⇨誰でも此の商売を遣る⇨多くの人が米国でハンバーグを買って日本で売る⇨米国では売るハンバーグが無く成り、日本では供給過剰⇨ハンバーグの値段が米国で高騰し、日本では値が下がる⇨此の現象は「米国でのハンバーガーの値段」=「日本でのハンバーガーの値段」と成る迄続く⇨結局、「日本と米国では丁度同じものが買える様(両国の需給のバランスに見合う様)に、為替レートが決まる」というのが「購買力平価説」が成立つ。
次に、以上の考えを一般化して、「日本での値段」を「日本の物価」、「米国の値段」を「米国の物価」として、「為替レート」が決まるかを考える。
日本の物価水準PJ、米国の物価水準をPAとして、為替レートをe(1$=e円)とする。同様に、米国でPAのものは円だと「為替レート×PA円=e×PA円」に成る⇨米国の物価を日本円に表すと「e×PA円」に成るのである。
「購買平価説」に依れば、此れが「PJ」と等しく成るのだから、
PJ = e×PA
と成る。
⇩
e = PJ/PA
と成る様に「為替レート」が決まるのだ。
此れ迄に、「『為替レート』が夫々の国の物価に応じて決まる」ということ迄話して来たが、物価変動が起きた時に如何成るかを、次に考えて行く。
日本の物価(PJ)が上がる⇒eが増加する。
ex. 「1$=100円」⇨「1$=120円」☜「円安」に成った。
逆に、
米国の物価(PA)が上がる⇒eが下がる。
ex. 「1$=100円」⇨「1$=80円」☜「円高」に成った。
👇
日本の物価上昇(インフレ) : 円安に繋がる。
外国の物価上昇(インフレ) : 円高に繋がる。
此れが、「購買力平価説」である。
此の「購買力平価説」には重篤な欠陥がある。
「実際には、成り立って居無い。」
「購買力平価説」: 為替レートは物価水準に基づいて決まる👈物価が変動し無ければ、「レートも変わら無い」ということに成るが、実際に為替レートは日々目が紛るしく変動してる👈購買力平価説は長期的には或る程度当て嵌まるが、短期的にはまるっきり意味を成さ無い。
👆為替には物価水準以外にも色々な要因が絡んで来て居る。
其の要因の一つが、「資本の移動」である。
つ づ く
※ 本投稿文中の綴りや語句の使い方や理論分析の誤りは、適当に解釈して貰うか、コメント欄で指摘して頂きたい。










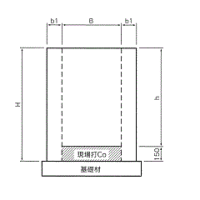









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます