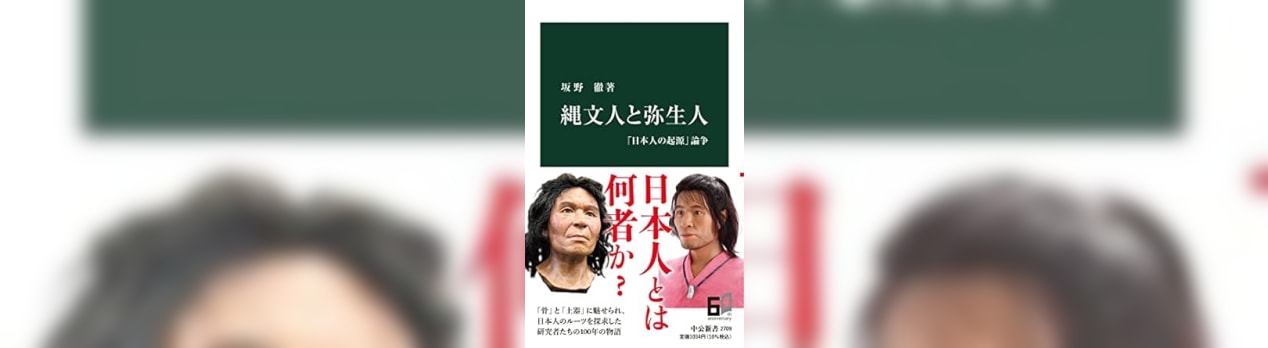最新の定説は、日本人のご先祖は、最初に大陸から移住してきて定住し始めた狩猟採集民が縄文人となり定住した日本列島に、渡来系の米作民が混血して生まれた、というもの。DNA分析によれば、大陸北方民からの移住者と南方島伝いと大陸南方陸地伝いの移住者が混じり合っているという。さらに、縄文時代と弥生時代の境目も明確には決め難く、狩猟収集生活と漁労生活、そして稲作、農作による生活は、気候変動や灌漑、鉄器などの技術進歩とともに時間をかけて混ざり合い、列島を東西から南北へと漸進して広がっていったことが考えられる。この定説が定着するまでに、人種交代説、固有日本人説、混血説、変形説などの様々な仮説が唱えられてきた。
日本で唱えられる縄文時代と弥生時代という土器に基づく歴史的区分呼称は、世界での旧石器時代、新石器時代、金属器時代という世界の歴史区分とは異なる。また沖縄と北海道では、この時代区分はさらに異なる。弥生人も、渡来系と縄文系に分類できるという。縄文、弥生系という歴史区分が高校教科書に掲載されたのは1950年代位以降、現代人は縄文人と弥生人の混血であるという最新の学説は1980年代以降定着してきた、比較的新しいものである。
本書では、明治期以降に唱えられてきた、アイヌ人先祖説、コロボックル先祖説、土器や貝塚発見の経緯と各種仮説の時間的推移などを紹介し、現在の学説に至った道筋を紹介する。本書筆者の考える振り返りのポイントは、次の通り。1.考古学は土器分析中心であり、人類学の視点がおろそか。2.現在的学説を中心に振り帰ると、過去には中心的だった仮説を軽んじる結果となる。3,日本人起源を検討するためには考古学と人類学などの合作、垣根を取り払う必要がある。
これらに加えて、明治期から太平洋戦争にかけては、日本中心、皇国史観的考え方が優位になり、学説を歪めてしまった影響が戦後まで続いていたこと、そしてその揺り戻しも激しかったことなども踏まえて、日本人とはなにか、各種学説とその歴史的背景をじっくりと振り返る100年の物語である。