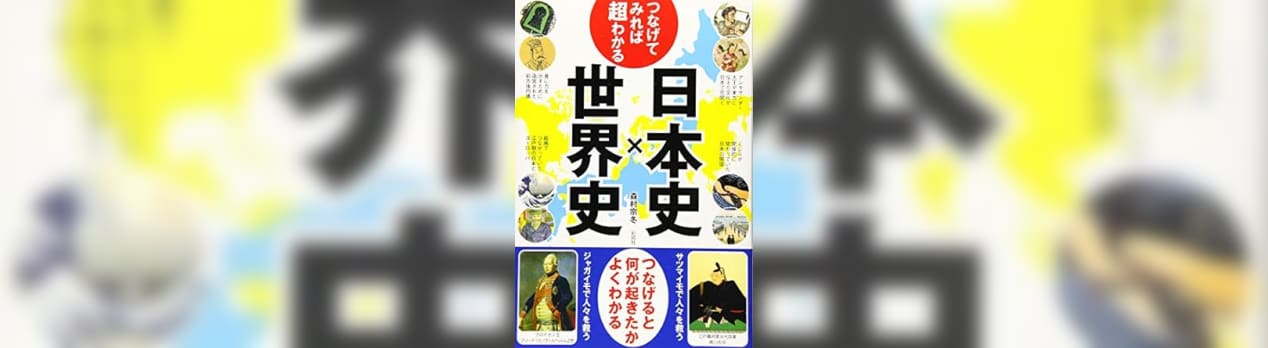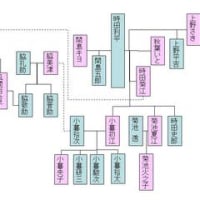日本史と世界史を別々に学ぶよりも同時並行的に並べて理解するほうがよりよく分かる、という一冊。
日本列島の黎明時代に人類の祖先が約1万年かけてアフリカ大陸から日本列島にやってきた頃、世界でも人類の世界的拡散が進んでいた。約1万年ほども続いたという縄文時代には、東地中海ではクレタ島に金石文化が興りエーゲ文明が誕生。エジプトではメネス王が上下エジプトを統一、エジプト第一王朝が樹立。メソポタミアではシュメール文明が興り、ウル、ウルク、ラガンシュなどの都市国家が形成。中国大陸で生まれた文明により玉器の加工技術が発展し、長江文明や北方、南方文化などが融合して縄文文化が形成された。地球温暖化と寒冷化は繰り返し興り、寒冷化の時代におきた動乱の余波を受け、日本列島に逃れてきた大陸からの渡来人たちにより稲作が列島にもたらされた。
遣唐使廃止は唐の滅亡に同期し、日本では国風文化、女流文学が生み出された。神仏習合が進み、本地垂迹思想から権現が生まれ、愛宕権現、秋葉権現、白山権現などが信仰を集め寺院参拝が一般化していく。鎌倉時代が始まる頃誕生したモンゴル帝国、日本には元寇として進出を試みたが、蒙古による支配を防ぐため九州では倭寇が生まれ物資を得るようになる。大陸の明王朝の冊封体制に入った義満は勘合貿易で利益を得て日本国王として振る舞った。欧州でのペスト流行と香辛料への需要は東アジアへの関心を増大させ、日本に鉄砲をもたらし、刀鍛冶の技術を持つ技術者は多くの鉄砲コピーを作成、日本は当時の軍事大国となる。欧州の大航海時代、日本の金銀は世界に広がり、それで得られた軍資金で戦国大名たちは戦っていた。その後の宣教師を尖兵とするカソリックの日本進出は秀吉、家康により阻まれ、植民地化を免れた。
江戸時代の鎖国、泰平な時代は欧州における200年にも及ぶ戦乱と革命により保たれた。その後欧州ではジャポニズム、日本では欧州製の絵の具が使われ北斎、広重などの傑作が生まれた。ナポレオンの登場でオランダは独立を失い、その間帰国を阻まれたオランダ商館長ドゥーフは日蘭辞書を作成、その後の蘭学振興に寄与した。幕府は北方ロシアからの圧力に対抗するため、蝦夷地の測量を始め、伊能忠敬の日本地図完成に寄与した。鯨油を採取するため日本列島に近づいたアメリカ船は日本からの水や薪、石炭獲得のため開国を迫り、南北戦争で使われた最新武器がその直後の戊辰戦争では新政府軍により活用、明治維新につながる。英国での鉄道の産業寄与を目にした岩倉使節団は、日本での鉄道建設に力を入れた。
本書内容は、列島黎明期から日本の近代化までを網羅、日本史が世界の状況とすべてリンクしていることを紹介している、以上。