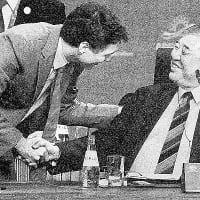最近、都道府県知事選の多選に厳しい目が向けられるようになった。7月に行われた群馬県知事選で五選目の現職が敗れたのは、その象徴的出来事だと思う。
最近、都道府県知事選の多選に厳しい目が向けられるようになった。7月に行われた群馬県知事選で五選目の現職が敗れたのは、その象徴的出来事だと思う。
神奈川県議会では、10月12日に、知事の任期を三期十二年とする多選禁止条例案を賛成多数で可決した。松沢成文知事が語るとおり、「他の自治体にも影響を与える」<10月13日付『読売新聞』第37面〈社会〉>だろう。
10月21日付『読売新聞』第4面〈政治〉の<政(まつりごと)なび>欄では、加藤清正の治世十二年に因んだ、熊本県の「清正公(せいしょこ)信仰」を引き合いにして、知事多選禁止を論じている。知事の巨大な権限を制御するのに、三期十二年は妥当なところである。
規模は小さくなるが、市町村長の任期についても同じことがいえる。釧路市では、昭和52年の市長選で、四期目を目指した山口哲夫(革新)に対して、前回の雪辱を期す鰐淵俊之(保守)は、「多選の弊害」を公約の一つに掲げて当選したが、結局、五期十九年(最後の一年は、衆議院議員)の長期に渡る市長在任となった。四選・五選については、本人の意志とは異なる地域の事情から、苦渋の選択となったのだろうが、多選に対する批判があった。
平成4年の「市制施行70周年記念事業」は、鰐淵市政の総まとめとして見ることができる。他の都市に比べ立ち遅れていた都市インフラの整備への取り組みが、鰐淵市政の業績だが、一方で、産業や輸送・文化的都市機能の積極的な基盤づくりが、現在の財政危機の遠因になっていることも否めない。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事