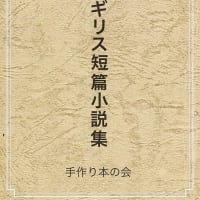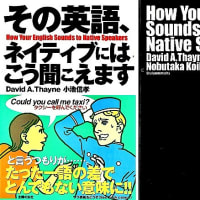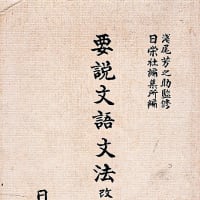日本の大学は、欧米の大学と違い、入学するのが難しく、卒業は容易と、昔から言われてきた。しかし今、大学全入時代を迎え、入学も卒業も容易な状況になりつつあり、大学が授与する学士号は、国際的通用性を喪失する恐れが出てきたという。
札幌に住む、国立大学(独立法人)準教授の若い友人は、講義や演習の成績評価が厳しいことで、学生に恐れられているが、そのような教員は、少数派だそうである。「教養英語ごときで、そんなに厳しくすることないだろ」と、自分の講座の学生を不合格にされた教員から陰口をたたかれるのを、常々ぼやいていた。講座の同僚でさえ、「不合格者を出すと次の年の処理が大変だ」と平気で公言する、と聞いた。
10月26日付『読売新聞』第11面〈解説〉の<論点>は、「全入時代の『質』低下防ぐ」というタイトルで、「学士力」の必要性を説いている。
学士力とは聞き慣れない用語だが、記事の冒頭で、中央教育審議会の小委員会による審議経過報告内容が引用され、「学士課程教育を通じて共通に習得を目指す学習成果を『学士力』(仮称)と名付けて提案」とある。
釧路公立大学や北海道教育大学釧路校も、厳格な卒業認定を行い、学習成果を明らかにし、国際的通用性を高めることが求められるだろう。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事