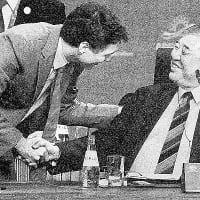最近のグローバルな魚食ブームのせいで、経済資源として魚の価値が高まり、需要が増加しているため、漁場となる海洋全体に関して、根拠のある資源管理が強く求められる時代になった。
最近のグローバルな魚食ブームのせいで、経済資源として魚の価値が高まり、需要が増加しているため、漁場となる海洋全体に関して、根拠のある資源管理が強く求められる時代になった。
平成20年2月13日付『北海道新聞』第2面〈総合〉を初回に、「イワシはなぜ消えた」と題する記事が、16日と18日を除いて五回連載された。かつて釧路港の水揚げ日本一を支えたマサバとマイワシが、周期的に豊漁と不漁を繰り返す原因を、単なる乱獲主因説ではなく、「大気─海洋─海洋生態系という基本構造(レジーム)が数十年周期で転換(シフト)する」という「レジームシフト」の考え方に求め、気候や環境の変動を考慮しつつ漁獲制限措置をとる必要性を説く論旨の展開には、強い説得力がある。
レジームシフトは、マサバやマイワシだけではなく、シロザケ・ブリ・サンマ・スケソウ・ハタハタなど、他の多くの魚種の資源量に影響を与えているという。環境の変化を考慮しないTAC(漁獲可能量)だけに頼る漁獲管理には限界があり、やがては資源枯渇という最悪の事態が現実のものとなりかねない。

サケ・マスの漁獲は、水産庁の孵化・放流事業に支えられているが、成魚になるまで生活するベーリング海の環境変化によって、期待された成果が得られないこともあり得る。禁漁解禁後に釣るヤマベは、雌が春から初夏にかけて、いわゆるギンケとなって降海した後、川に残った雄ではあるが、サクラマスの資源を考えると、趣味として釣ることに複雑な思いがしないでもない。
一時は資源枯渇寸前まで追い込まれた秋田県のハタハタについては、連載第3回で言及がある。2月17日付『讀賣新聞』第14面〈くらし〉の<歳時記>欄に、秋田県水産振興センター海洋部長の、「ハタハタは秋田の宝。そんな思いもあって漁師が自主的に取り組み、『とりながら増やす』資源管理型漁業の世界的モデルになった」という話が引用されているが、『北海道新聞』連載第3回で引用されている、茨城県水産試験場主席研究員の、「ハタハタの資源回復は厳しい漁獲規制と海の環境が好転したことの複合的な要因が背景にあり‥‥」という見解が正しいのではないだろうか。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事