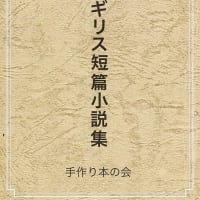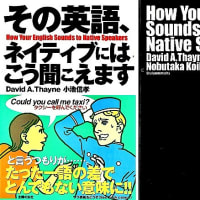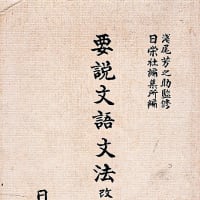釧路湿原国立公園が7月31日に指定二十周年を迎えるに当たり、『北海道新聞』は、第30面〈釧路〉・第31面〈釧路・根室〉の二面を使って特集を組み、多彩な記念イベントの紹介とともに、教育現場への普及活動を目指した、釧路湿原再生協議会の環境教育推進策を、大きな紙面を割いて、詳しく報じている。
釧路湿原国立公園が7月31日に指定二十周年を迎えるに当たり、『北海道新聞』は、第30面〈釧路〉・第31面〈釧路・根室〉の二面を使って特集を組み、多彩な記念イベントの紹介とともに、教育現場への普及活動を目指した、釧路湿原再生協議会の環境教育推進策を、大きな紙面を割いて、詳しく報じている。
私は、釧路湿原再生協議会の取り組みに反対はしないが、辻井達一会長の、「例えば国立公園内のごみの問題でも、環境省に『もっと取り締まれ』というだけでなく、大人が湿原に子供を連れて行って厳しくしつける一種の環境教育が必要だ」という発言には違和感がある。小見出しにあるように、「学校と連携し環境教育」をするのであれば、当然、「大人」つまり「教員」が「厳しくしつける」という意味になる。しかし、今、子供たちを厳しくしつけることができる教員がどれほどいるか、会長はご存じないのではないだろうか。教育現場をよく見て頂きたい。
上の写真は、北海道教育大学釧路校のキャンパスの南東の一隅である。歩道にまではみ出した見苦しい蕗を、大学はなぜ放置しているのか。

右は、平成18年度に植樹された、「大学再編記念樹」のチシマザクラ。雑草が茂り放題で記念樹も形無し。
左は、何の建物か知らないが、入り口はガラクタの山。湿原だけが環境教育の場ではなかろう。このような荒れた環境の中で、学生は、環境教育について何を学び、教員になって、何を教えられるのか。子供たちを湿原に連れて行って、何を厳しくしつけられるのか。
自らのキャンパスの環境整備ができないで、釧路湿原の環境保護を子どもたちに教えられる教員が育つかどうか、私は疑問に思うのである。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事