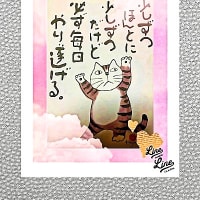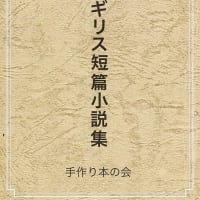文化庁は、九月十五日、今年二月に実施した「2010年度国語に関する世論調査」の結果を発表したが、1995年度以来五年ごとに実施されてきた「ら」抜き言葉が、調査のたびに増加し、「来れる」の使用率が95年度の33.8%から今年度は43.2%に達したことが判明(9月16日付『讀賣新聞』第34面参照)した。特に北海道は顕著で、57.7%に及ぶという。「食べれない」と「見れた」の場合も、北海道は全国平均よりはるかに高率(全国・道内比較グラフ=写真上段は、同日付『北海道新聞』第29面から転写)で、大らかというか大雑把というか、あまり因習にこだわらない道民気質がよく現れている。
文化庁は、九月十五日、今年二月に実施した「2010年度国語に関する世論調査」の結果を発表したが、1995年度以来五年ごとに実施されてきた「ら」抜き言葉が、調査のたびに増加し、「来れる」の使用率が95年度の33.8%から今年度は43.2%に達したことが判明(9月16日付『讀賣新聞』第34面参照)した。特に北海道は顕著で、57.7%に及ぶという。「食べれない」と「見れた」の場合も、北海道は全国平均よりはるかに高率(全国・道内比較グラフ=写真上段は、同日付『北海道新聞』第29面から転写)で、大らかというか大雑把というか、あまり因習にこだわらない道民気質がよく現れている。 しかし、いくら道民が言語規範にこだわらないといえ、市内の小学校の教頭を務める四十歳代の知人が、平気で「来れる・食べれる」と発話するのを耳にすると、私は愕然とせざるを得ない。手本となるはずの教育者がこうなのだから、全国平均で十歳代の73.8%が「来れる」を使うのも納得できる。北海道の十歳代はもっと高率だろう。正しい国語教育ができていないのに、小学生に英語を教えるなどもってのほかである。
しかし、いくら道民が言語規範にこだわらないといえ、市内の小学校の教頭を務める四十歳代の知人が、平気で「来れる・食べれる」と発話するのを耳にすると、私は愕然とせざるを得ない。手本となるはずの教育者がこうなのだから、全国平均で十歳代の73.8%が「来れる」を使うのも納得できる。北海道の十歳代はもっと高率だろう。正しい国語教育ができていないのに、小学生に英語を教えるなどもってのほかである。
ま、かくいう私自身も、慣用句(言葉や慣用句の調査結果=写真下段は、同新聞から転写)の一つを間違えていたので、大きな顔はできない。私の家では残念ながら、私も女房も長男も「声を荒らげる」を「こえをあらげる」と読んでいた。七十歳を目前にして赤面の至りである。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事