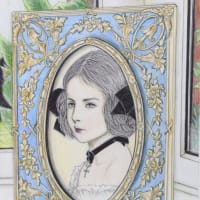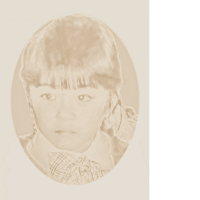ポーランドの首都ワルシャワは、同一の戦いに於いて異なる民族が2度にわたり蜂起した人類史上稀にみる都市である。
一度目はユダヤ人、2度目はポーランド市民。
そんな頃の物語。
その頃のワルシャワはドイツ軍による支配の中、混沌と劇的な変革の渦中にあった。
その一番の主人公はワルシャワ在住のユダヤ人の存在だった。
ドイツ軍のポーランド侵攻直前当時、ワルシャワにはユダヤ人が37万5000人いた。
実に市内人口の30%を占め、アメリカニューヨークに次ぐ多さだった。
ワルシャワ占領直後から、ユダヤ人封じ込めの政策が検討されていたが、1940年3月以降、市内にチフスが蔓延し始めた。
特にユダヤ人居住地区に。
同年10月2日正式にユダヤ人評議会に命じ、ゲットー建設が始まり、11月には完成をみた。
その広さは従来の居住地区の3分の2、ワルシャワ全面積の2.4%、最大人口は44万5000人に及んだ。
それはナチスドイツによる全ゲットー最大規模を誇った。
更に完成間もない11月16日、ゲットーは封鎖され、特別に通行許可証が発行された時以外の通過は許されなかった。
ゲットー内の運営はドイツ当局の監督のもと、ユダヤ人評議会が行う。
中にはユダヤ人ゲットー警察さえ存在した。
その運営は自由主義的統治で、ブント、社会主義シオニスト党、青年運動などが活発に地下活動も行っていた。
しかし同じユダヤ人社会でありながら、貧富の格差も顕著に出現し、飢餓に苦しむ貧困層に対しては、ユダヤ人相互援助協会(ZTOS)が組織され救済にあたった。
ゲットー内では一般の市場原理に伴う生産活動も活発に行われたが、仕事を持たないものは、強制労働に駆り出された。
1942年7月22日、ラインハルト作戦(ユダヤ人絶滅・殺りく実行計画)決行に伴い、ユダヤ人を東部に移送する旨《むね》通告された。
ゲットー解体と強制収容所移送に伴うホロコースト《大量殺りく》の始まりである。
移送は決して戻ることのない片道切符の旅。
そのスピードは極めて迅速で、わずか10日足らずで6万人、8月半ばまでに全体の半数、第一次移送終了の時点で30万人が駆り出され、死出の旅へと向かわされた。
それまで無抵抗の姿勢を貫いていたユダヤ人社会にも、ようやく抵抗への機運が高まり、秋頃から準備が始まった。
共産党、シオニスト党、社会主義者で構成されたブントが10月20日に合弁、ユダヤ人戦闘組織(ZOB)結成、戦闘団など22の部隊が組織された。
総指揮官はモルデハイ・アニエレヴィッツ(24)が任命された。
彼らがまず標的にしたのはゲットー警察、その上部組織のユダヤ人評議会へのテロだった。
つまり民族の共通の敵であるドイツ軍ではなく、最初にユダヤ人同士が仲間割れし、ドイツ軍に協力し仲間を売る評議会への敵視と憎悪からくる分裂であり、同じ民族同士、殺し合う事を意味した。
反抗を実現させるためには、まずドイツ軍の犬である組織を潰す必要があったのだ。
それと平行し、抵抗に必要な武器の調達が至上命題だった。
武器購入資金を得た組織は、ゲットー部外のポーランド人に密かに協力を要請、武器入手を企図した。
しかし頼みの綱のポーランド人達もドイツによる被支配階層であり、そう簡単に準備できるわけではなかった。
しかも全てのポーランド人がユダヤ人に協力的というハズもなく、むしろ反感・差別意識の強い者が多くを占めていた。
そんな背景もあり、多額の購入資金を託したにも関わらず、僅かな武器しか入手できない。
指揮官モルデハイの目論見《もくろみ》では、少なくとも拳銃100丁、小銃数丁を見込んでいたが、実際に渡されたのは、たったの拳銃10丁のみであった。
いくら抗議してもそれ以上は渡されず、思わず天を見上げる。
一方ポーランド人側にしてみたら、近く自分達の蜂起もあるかもしれない以上、今負けると分かっているユダヤ人たちの蜂起に、貴重な武器をそう安易《やすやす》と渡す訳にはいかない。
これがギリギリ協力できる限界だったのだ。
ドイツ軍による殺害の脅威に晒され、隣人のポーランド人に見放され、孤独で絶望的な戦いを強いられる現実を改めて見せつけられた気がした。
決起=鎮圧による死
無抵抗=絶滅収容所行による死
生きるという選択肢も可能性もゼロの明日に、涙すら出てこなかった。
それでも決起を選ぶ理由は、民族と各々《おのおの》の人生の誇りと意地を守るために他ならない。
あらゆる手立てとネットワーク、手段を駆使し、新たに数丁の機関銃、ポーランド人レジスタンス組織「国内軍」などから拳銃50丁、手りゅう弾50個、爆薬など最低限の支援を得る。
国内軍は、まだ人の心を持っていた。
先ほどと、ここでも登場したフィリプも所属する国内軍。
説明が先と重複《ちょうふく》し、くどくなるが、ポーランド政府残存要人がロンドン亡命政府を組織し、その指揮下国内残存兵士及び有志たちにより祖国の独立と自由を標榜し、レジスタンス目的に組織された地下組織軍隊である。
しかし圧倒的な軍事力を誇るドイツ軍に対し、あまりに貧弱な武装しかできない義勇軍にすぎなかった。
イエジキ部隊も武器の協力はできなかったが、食料の供給ではできる限りの力を尽くす。
しかし、ドイツ軍の目が光る中では、次第に供給路は細くなり、ついには絶えてしまった。
話を戻す。
1943年4月19日750人の戦闘員が決起、火炎瓶と少数の銃でドイツ武装親衛隊と警察の部隊に武力蜂起した。
初日こそドイツ軍を撃退したが、翌日体制を立て直したドイツ側は徹底した焦土作戦を決行、5月16日に完全鎮圧、戦闘は終了した。
最初から彼らに勝ち目などは無かった。
それでも貧相な武器で立ち向かった彼らは、一体どういう気持ちで戦ったのだろう?
戦いに参加したイザック(25)には父と母と妹がいた。
父はゲットーに収容される前、ドイツ軍兵士に路上で身分証明書の提示を求めれれた。
ドイツ兵はユダヤ人と見るや様々な嫌がらせをし、罵倒し、辱め、銃殺や殴り殺すのが当たり前の時代。
目をつけられて無事で済む筈はなかった。
父はその威圧的な怒号の命令にすっかり恐れ慄《おのの》いた。
萎縮した手は震え、胸ポケットから紙の証明書を出そうとしてもままならない。
しびれを切らしたドイツ軍兵士は二度大声で「身分書を出せ!!」と怒鳴りながら自動小銃を構え、躊躇《ちゅうちょ》せず父に至近距離から乱射した。
その場で倒れる父。
目の前の悲劇を目撃し、母は今まで見たことがない取り乱し様で、父の骸《むくろ》に駆け寄りすがりついた。
大声で泣き叫ぶ母を、通りがかりの人々は関わらないよう足早に過ぎ去り、誰一人助けようとはしない。
イザックと妹は後から駆け付け、そんな父と母に涙した。
それから一月後、イザックは母と妹と共にゲットーに収容される。
ゲットーの建物の各部屋に数家族が押し込められた。
赤の他人がある日突然、同じ部屋で強制的に同居させられるのだ。
しかしそんな同居生活もそう長くはなかった。
母と妹は8月2日トレブリンカ絶滅収容所に移送のため、イザックと力づくで引き離された。
彼が見た家族の最後の姿は、ユダヤ人ゲットー警察数人に取り囲まれたため、部屋のドアの向こうに出るところまで。
母の二度目の泣き叫ぶ声と妹の兄の名を呼ぶ声だけが段々遠く聞こえるのみであった。
怒りと悲しみに震えるイザック。
天蓋孤独となり、もう守る者は誰もいない。
自暴自棄になり勝ち目のない反抗に参加するのは、彼にとって当たり前の行動であった。
ユダヤ人のゲットー蜂起とは、そんな悲しみと絶望を背負った名も無き人々が武器を持たない兵士となり、戦いに挑んだ悲しい歴史であることを決して忘れてはならない。
蜂起という無謀な悲劇の戦いに敗れ、結果、残存ユダヤ人市民5万6000人が連行された。
その後彼らは当然の如く射殺、若しくは収容所において特殊処理《毒ガス室送り》されることとなる。
そしてすぐさまワルシャワゲットー跡地に強制収容所が建設され、新たな悲劇の象徴に生まれ変わった。
ゲットーの瓦礫の撤去作業に強制収容所の囚人と、ポーランド人労働者が動員された。
また蜂起による戦闘中、ゲットーの外に逃亡したユダヤ人狩りが行われ、ポーランド人市民による密告が横行、更にギャングが現出し、見つけ出してはユダヤ人からお金などの財産を奪い取っていた。
そんな非道な行いが横行したワルシャワ市内。
それでもユダヤ人にとってヨーロッパで一番住み易い街なのは、ユダヤ人の割合が一番多かったことでも分かる。
迫害と殺戮が続くドイツ国内から、多くのユダヤが遥々《はるばる》ワルシャワめがけて移り済んできたくらいなのだから。
でも仕方なかった時代だったとはいえ、市民による密告や略奪が続いたその間、その様を目撃した一般の善良なワルシャワ人市民たちはどう思っていたのだろう?
たとえユダヤ人が嫌われていたとしても、その悲劇にはさぞ心を痛めていただろう。
そして明日は我が身の運命を悟ったのだった。
ゲットー近くに住まうヨアンナはその一部終始を目撃していた。
彼女も青年会の一員として組織の中でユダヤ人救援を行っていたが、やがて組織としての行動は不可能になる。
しかしヨアンナには納得できない。
彼女は承服しなかった。
時に逃亡してきたユダヤ人を匿《かくま》い、食料を与え、できる限りの援助に務めた。
しかしその行為を知るに至り、支援していたイエジキ部隊のメンバー、福田会からの友であるエミルやアレック、ヤンなどからドイツ側への発覚を恐れ厳しく窘《たしな》められた。
彼らも今ではイエジキ部隊の中核を構成する有力なメンバーだった。
男気厚い彼らもまたエヴァ夫妻同様、ヨアンナを心配してワルシャワまでついてきたのだった。
特にエミルは、ハンナの同意を得るのに人一倍苦労したが・・・。
彼らとて決して平気で目の前の惨状を傍観していたわけではない。
反抗の準備ができていなかったのだ。
火の粉を自ら掃えない現状では、関わることは自殺行為に他ならない。
涙を飲んで見過ごすしかなかった。
エヴァはヨアンナを涙ながらに説得した。
フィリプも同じだった。
その背後にはエミルやアレックも控え、無言の圧力をかけた。
彼女を心配する心に変わりはない。
でも被支配層同士が団結行動できない悲哀。
そんな悲しい状況が彼らの心を寒くした。
しかし何故ヨアンナは身の危険を顧みず、ユダヤ人に救いの手を伸ばしたのか?
そもそも何故ユダヤ人は絶滅を企図され、ホロコーストの犠牲にならなければならなかったのか?
ヒトラーや一般のドイツ人に嫌われただけならまだしも、全ヨーロッパに蔓延した反ユダヤ主義はどんな理由があっての事なのか?
何故殺されなければならないほど憎まれ殺戮《さつりく》を傍観されたのか?
キリスト教の裏切り者『ユダ』がユダヤ人だったから?それが原因?
だとしたら全くの笑止である。
宗教の教義の中に、特定の人種を憎んでも良い、憎悪の対象は殺害しても良い、なんて教えだあったとしたら・・・・。
人を救済すべき宗教が原因で、ホロコーストの犠牲になるなんて本末転倒だろう。
逆に人殺しを是とする宗教なんぞ、絶対にあってはならない。
(現実にはそんな宗教も数多《あまた》あるが)
もし憎悪の動機がそれだとしたら、その教義を実践し差別を是認したのなら、信者自らが間違った宗教を信じ、実践してきた事になる。
自分の信じる宗教が悪である事の証明になる。
そんな小学生でもわかる簡単な理屈に気づけなかったとしたら、実に愚かだと断じられるのではないか?
そんなくだらない理由が主たる原因であるはずはないと信じたい。
では何故どこからも救援が無かったのか?
世界で唯一、当時新世界と呼ばれたアメリカが受け入れたが、それもナチス台頭のユダヤ人弾圧初期の頃の話。
大戦の動乱が進み難民が殺到すると、さすがのアメリカも次第に入国条件のハードルを上げ、受け入れ制限政策に舵をきり、積極的な救済に動くことはなかった。
来るものは条件付きで拒まず。
それがアメリカの態度だった。
シェイクスピアの『ヴェニスの商人』に登場するユダヤ人悪徳商人シャイロックや、『クリスマスキャロル』の守銭奴スクルージに代表される悪人のイメージがユダヤ人全体の印象なら、あまりに悲しすぎる。
仮にそのような悪人が多数存在していたとしても、それが民族全体にあてはまる訳ではあるまい。
同じ数だけ善人が存在し、大多数は普通に生活する庶民に過ぎなかったのではないのか?
ユダヤ民族が団結して組織的な犯罪、殺人、弾圧・抑圧、搾取を長年繰り返してきたのなら納得もできるだろうが、そうではないだろう。
ただユダヤ教に固執し、社会に積極的に溶け込む努力が足りなかっただけで、商才にたけた人物が他民族より多く、金持ちが多かったというだけで、そこまでの憎悪の対象になるのか?ならなければならなかったのか?
人類の歴史はあまりに人命の価値が軽かった。
第二次世界大戦終結後の条約・法律・社会制度・人権の仕組みが整えられた現在でも紛争や差別や対立や難民が絶えないが、それ以前はそれらが未整備の状態の中、おびただしい悲劇が起きた。
その中にあっても、ユダヤ人ホロコーストは異彩を放つ突出した悲劇だった。
ヨアンナは納得しない。
しかし、ただ彼女がきれいごとの世界、平和なお花畑の住人だったわけではない。
単なる軽佻浮薄なヒューマニズムから、気まぐれの衝動的な行動として手を差し伸べたのではない。
彼女の生い立ちに思考の原点、行動の指針があった。
故国を捨て、シベリアに逃避した難民の子として、途上両親を失い周囲の悲劇を多数目撃し、それ以上の善意の救済を経験し、現在まで生かされてきた。
善意は人を救う。
無関心や憎悪は人を死にも追いやる。
自分はどちらの道を選択すべきか?
その答えが総てだった。
毎日 其処此処《そこここ》で断末魔の叫びが聞こえる。
一度も会った事のない声の主の顔が一瞬闇に浮かぶ。
そして消えゆく魂と一緒に、苦悶に歪んだ表情も消えてゆく。
ナチスの殺戮の漆黒の闇の怖さが、人の正常な思考を破壊する。
そんな恐怖に萎縮するより、勇気を持って『当たり前の人』でいよう。
でも彼女は瀕死の逃亡ユダヤ人にパンを施す度、匿《かくま》うため一夜の隠れ場所を提供する度、自分の無力さを感じていた。
できる事の限界を感じていた。
この人たちを遥か遠くの国、日本に送ることができたら。
きっとたくさんの人を救えたのに・・・。
自分たちの民族も武力で占領され、支配されている苦しい状況に居ながら、ヨアンナはそんな事を考えていた。
但し、その日本も個人単位ではユダヤ人を救ってきたが、国家が直接救う事はなかった。
ナチスドイツとの軍事同盟があったから。
ここにあるひとりの男の言葉が思い浮かばれる。
―マルティン・ニーメラー―
反ナチ運動家で、弾圧された経験から後に記された詩からの言葉である。
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき
私は声を上げなかった
私は共産主義者ではなかったから
ナチスがユダヤ人を連行して行ったとき
私は声を上げなかった
私はユダヤ人ではなかったから
そしてナチスが私を攻撃したとき
私のために声を上げる者は
誰一人残っていなかった
つづく