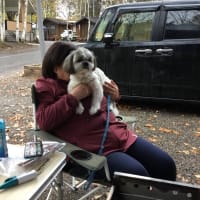ポーランド北部のグダニスク(ドイツ名ダンツィヒ)に移り住んだヨアンナ一行。
移住後彼女は息つく間もなく、生活の糧を得なければならない。
青年会支援者たちの力添えもあって、街の片隅に小さな食堂を開くことができた。
そこは彼らの憩いの場となり、近くの造船所で働く工員たちも客として徐々に増えてきて、何とか生活の目途が立つくらいの繁盛を見た。
ヨアンナは生きるため、我が子を育てるため必死で働いた。
一方ワルシャワでは、ヨアンナ宅でソ連の治安部隊に巻き添えの銃撃を喰らい瀕死の重傷を負っていたアレックも、何とか一命をとりとめる。
ようやく体力も回復し自由に動けるようになると、エミルやハンナの元に元気な姿を見せたくなる。
そう思うといても立っても居られない性格のアレックは、直ぐ様ヴェイへローヴォ孤児院で働くエミルたちに逢いにやってきた。
もちろんヴェイへローヴォ孤児院出身の昔からの仲間たちからは、愛犬が飼い主の帰りを歓待する時のように、病み上がりの彼をモミクチャにして喜んだ。
「痛い!痛い!!痛いぞコラ!!」
それでも歓迎の儀式は止まない。
アレックは自分をここまで歓迎してくれる仲間たちの心根が嬉しくもあり、あまりに手痛い歓迎ぶりに、訪れた事をちょっと後悔もした。
そして落ち着いた頃、ヨアンナ達の住むグダニスクにも顔を出す。
すると、ここでもまた同様の凄まじい喜びの声と手荒い歓迎を受けた。
いつも冷静でおしとやかなヨアンナでさえ、嬉しさのあまりモミクチャにする。
ヴェイへローヴォ孤児院出身者の伝統って、こうだっけ?
その日のヨアンナのお店は急遽閉店し、アレックに一緒についてきたヴェイへローヴォ孤児院の仲間を加え、盛大な歓迎の宴が遅くまで催されたのは言うまでもない。
そういう激しい歓待を受けるのが、アレックの人柄だった。
アレックはヨアンナの息子アダムを見て、
「暫く見ない間に大きくなったなぁ!」と大げさに驚く。
幼いアダムもそんなアレックおじさんが大好きだった。
アダムは皆んなの希望の星。
そのそばで絶えず目を離さず支え続けてくれたエヴァ夫妻と幼馴染のエミリア。
可愛い娘エミリアは、ヨアンナを「おばちゃま」と呼び、かけがえのない息子アダムの一番の友達に成長していた。
腕白だったアダムも次第に聡明な少年に成長し、父親の面影が随所に見られた。
エヴァ一家や周囲の手厚い支援もあり、人並みに学校にも通うことができた。
アレックも時々フラッとやってきて、アダムにお土産やら、昔ばなしをする間柄になり、殊更可愛がる。
アダムはアレックおじさんと呼ぶ程の仲になるのは自然の流れだった。
(ここまでのくだりは、次話にてもう少し詳細に紹介するので暫しおまちを)
*でも勘違いしないでね。
アレックもアダムの母ヨアンナも、勘繰る仲には永久にならないから。
アダム溺れる
ある夏の暑い日、アダムは学校の休みを利用して、仲の良い友だちと近くの海岸に繰り出し遊んでいた。
友のひとりが手づくりのビーチボールに見立てた皮製の粗末な大きめの球を持参する。
その日はバルト海沿岸にしては珍しく30℃近い猛暑日だったが、南の陸から北のバルト海に向かって吹く風が流れる日でもあった。
数人で釣りをした後ボール遊びに興じていると、遊びの輪から離れ風に流されたボールが、波打ち際へと転がっていった。
アダムは咄嗟に追いかけ、寄せては引く波の中から海へと夢中で走り、ザブザブと波をかき分け入ってゆく。
しかしボールはどんどん遠くの沖の方に流され、アダムがどんなに追いかけても追いつけない。
やがて気がつくと、気温の割に驚くほど冷たい海水がアダムの胸に達し、怖くなってボールを追うのを諦め、岸に戻ろうとした。
しかし陸から沖に向かって吹く風は向かい風になり、どんなに岸に戻ろうともがいても、もがいても、押し戻されていく。
その様子を浜で見ていた友たちは、当初はすぐにボールを取り戻し、岸に帰って来るものと楽観していた。
だがいつまで経っても岸に戻れないアダムの様子に、次第に不安になってくる。
アダムは体力を消耗し疲れ始めていた。
疲労が表情に現れる。
「ああ、アダムがおぼれる!」
初めて事の重大さに気づいた友のひとりが、近くにいた大人に助けを求めた。
たちまち人が集まり、近郊の漁師が使う小さな磯舟で助けに向かった。
その磯舟でさえアダムを救助し岸に戻るとき、その向かい風の強さにオールを押し戻されるほどだった。
しこたま海水を飲み、ぐったりしているアダムに、助けた漁師が
「危なかった・・・。
この俺の舟まで流されるかと思った!
九死に一生を得られて良かった、良かった!
なぁ坊主、もうあんな向こう見ずな事、やるんじゃないぞ!」
「ありがとう・・・。ごめんなさい。」
アダムは無事に戻れて安堵したのか、まだ肩で息をしながら、うつむき加減に小声でそう言った。
しかし海水を飲み溺れかけた者は必ずと言って良い程、重い病気に罹ったような脱力感と、悪寒の症状に陥る。
具合が悪くて立っている事も、座り続ける事もできない。
肩から大きめのタオルを掛け、30分以上ぐったりし、紫色に染まった唇でガタガタ震えながら目の前の焚火で暖を取る。
アダムが元気を取り戻し、家に帰れるまで回復するのには小1時間以上はかかった。
心配して付き添ってくれた友たちもそれぞれの家路についたときは、すっかり日が暮れていた。
アダムが家に戻り、事の一部始終を聴いたヨアンナは、意外にも落ち着いている。
取り乱したり喚くこともなく、最後まで黙って聞き、間をおいてからこう言った。
「アダム、今あなたはどう思っていますか?」
「心配かけてごめんなさい。」
蚊の鳴くような声でそう言った。
「助けてくれた人に、ちゃんとお礼を言いましたか?」
「うん、僕、ちゃんと言ったよ!」
「アダムは母さんにとって大事な、大事な息子。
お母さんだけでなく、天国のお父様もいつもあなたを見守ってくれていることを忘れないでね。
きっとよ。」
翌日お店を開ける前に、ヨアンナとアダムは改めて助けてくれた漁師を探し当て、丁寧にお礼を言った。
アダムは幼い少年の心に深く刻んだ。
もう二度と軽はずみな行動はとるまいと。
エミリアはそれをきっかけに、アダムの行動を注意深く見守った。
もちろん母エヴァからの言いつけではあったが、本当にそれだけか?と思うほど積極的にそばを離れず、いつも監視し関りを持とうとする。
アダムが「うるさいなぁ!」と煩わしさを露わにするほど付き纏った。
お陰で小学校・中学校で
「エミリアはアダムの奥さんかぁ?」
と囃し立てられ、誰もが認める不動のカップルと見なされた。
恥ずかしさから逃げるアダムと、追うエミリア。
「あぁ、青春だなぁ。」
と誰もが思った。
つづく