横断歩道
最近僕は手を挙げて近所の信号のない横断歩道を渡る。
以前は車の流れが切れるまで何もしないで待っていた。子供のころは親に言われたり学校から指導を受けたりして素直に手を挙げて横断歩道を渡っていたと思うが、たぶん中学生や高校生になったころ、手を挙げることは子供っぽくて恥ずかしいと感じ、手を挙げるのをやめたのではないかと思う。大学生になって自動車の運転免許を取った後は、自分が歩行者の時も運転手気取りで頑なに手を挙げなくなった。そして車の流れがなかなか切れないときには、一体何時になったら渡れるのだろうと内心苛立ったり、横断歩道で歩行者を見ても停止しないで通り過ぎていく運転手を恨めしく見送ったりしていた。逆に僕が運転手の時も信号のない交差点で手を挙げずに立っている歩行者のことをほとんど気に留めずにいた。
僕に変化が起こったのは昨年四月までの二年間の名古屋での生活だ。
僕は単身赴任で名古屋市丸の内一丁目にあるマンションで暮らした。毎朝運動不足解消のため、30分から45分ぐらい近所を散歩することを日課としていた。丸の内界隈は昔の城下町の面影を色濃く残しており、徳川家康が名古屋城を築城した際に整えた碁盤割という整然とした町割りが特徴だ。街中には縦横に道が走り至る所に信号のない交差点と横断歩道がある。車は交差点で必ず徐行し歩行者がいれば停止して道を譲る。僕も運転者に目配せをし、軽く会釈をして道を渡った。そして自然と軽く手を挙げて「渡らせてくださいね。」と合図を出し、止まってくれたら「ありがとう。」と手を振るようになった。運転手も心地よく応えてくれた。
単身赴任を終え、藤沢での以前の生活環境に戻った。土日の近所の県道は相変わらず遠方からの観光客などで車の量が多い。スーパーマーケットに買い物に行くために信号のない横断歩道を渡らなければならないが、なかなか車の流れが切れずに渡れない。それで僕は名古屋で覚えたように手を挙げた。なかなか車は止まってくれなかったが何台か目の車が止まってくれた。対向車線の車も止まってくれた。僕はうれしくなって感謝しながら道を渡った。待っていた何人かの人たちも渡った。
名古屋在住時に参加したマルティン・ブーバー勉強会で、段差のある人間関係においても限定的な「我―汝」は実現できると学んだ。段差のある人間関係とは例えば、教師と生徒、経営者と従業員、上司と部下、医師と患者など社会的役割に明確な違いのある関係をいう。この段差のある人間関係には横断歩道での運転手と歩行者の関係も含まれると思える。自動車という機械を操縦する運転手は生身の歩行者よりも圧倒的に強力だ。もし運転手と歩行者がお互いに我を張り同時に横断歩道内に進入すれば確実に歩行者が傷つく。その意味で歩行者は完全な弱者である。歩行者はこのことを自覚し横断歩道を渡りたいときは素直に運転手に手を挙げて合図を出し、止まってくれたら感謝を示すことが自然であり重要なことだと思う。そしてこのことによって限定的とはいえども「我―汝」の関係を実現できる可能性を広げることができる。
気のせいかもしれないが、最近近所のこの横断歩道で止まってくれる車が増えた。手を挙げて横断歩道を渡る歩行者も増えたようだ。
必要な時に手を挙げて合図を出し、止まってくれたら感謝を示す。とても当たり前で些細なことではあるが、段差のある人間関係で「我―汝」という相手に語りかける態度を実現していくための貴重な一歩だと思う。情報氾濫の中で忙殺され、相手を利用する態度である「我―それ」ばかりが横行する世知辛いこの世の中で少しでも豊かで人間的な生き方を実現していくために、こうした些細なところから、出来ることから大切に大事にしていきたいと思う。
僕も車を運転するときに信号のない横断歩道で渡ろうとしている人を見たら、出来るだけ車を止めよう。そして横断歩道を渡る歩行者が会釈をしてくれたら、ニッコリ笑顔を返そう。
最新の画像[もっと見る]
-
 小唄 惚れて通うに
2年前
小唄 惚れて通うに
2年前
-
 YMCA健康福祉専門学校 ホームページ
2年前
YMCA健康福祉専門学校 ホームページ
2年前
-
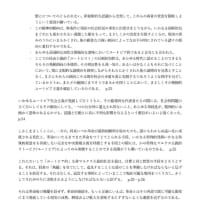 【公開】 マルティン・ブーバー原著『対話の倫理』抄本
2年前
【公開】 マルティン・ブーバー原著『対話の倫理』抄本
2年前
-
 福祉と防災
2年前
福祉と防災
2年前
-
 ウクライナ避難民女性の心意気
2年前
ウクライナ避難民女性の心意気
2年前
-
 マイタウン玉縄「歴史を物語る玉縄の寺社・史跡」シリーズ開始
2年前
マイタウン玉縄「歴史を物語る玉縄の寺社・史跡」シリーズ開始
2年前
-
 マイタウン玉縄「歴史を物語る玉縄の寺社・史跡」シリーズ開始
2年前
マイタウン玉縄「歴史を物語る玉縄の寺社・史跡」シリーズ開始
2年前
-
 【基本コンセプト】地域共生社会への途
3年前
【基本コンセプト】地域共生社会への途
3年前
-
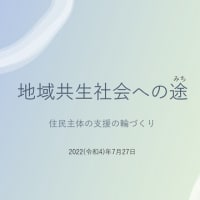 【基本コンセプト】地域共生社会への途
3年前
【基本コンセプト】地域共生社会への途
3年前
-
 円頓寺銀座
3年前
円頓寺銀座
3年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます