龍馬を巡る私の旅
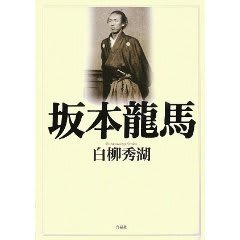
坂本龍馬
龍馬を巡る私の旅
山口敏太郎
@昔の記事の蔵出し
人間の人生は、旅に例えられる事が多い。生きる事そのものが旅であり、死ぬことさえも新たなる旅立ちかもしれない。今回は龍馬の人生を辿る“私の旅”を紹介してみたい。
我々、現代人にとって幕末最大の英傑と言えば坂本龍馬である。そもそも終戦直後までは、幕末の英傑と言えば西郷隆盛であった。だが、英傑の理想像に関して変換期が訪れる。1962年、司馬遼太郎が「竜馬がゆく」を発表してから、龍馬を英雄視する傾向が強くなったのだ。いや、司馬だけのせいではあるまい。父権的国家だった日本が、個人主義に移行していく価値観の変遷が、西郷から龍馬へという英雄像の変遷を生んだ可能性は高い。
龍馬に魅力を感じてから、20数年間、私は時折龍馬の残像を追い求める旅をしている。事件現場において、プロファイリングする事により、犯人の心理に迫れる事があるように、幕末の現場に立つことで、新しい発見があるのも事実である。
まず、龍馬暗殺の現場と言われている近江屋であるが、この周辺に池田屋、酢屋、土佐藩邸など数多くの史跡がある事に気がつく。幕末の頃、薩長も会津もかなり狭い空間で凌ぎを削っていたのだ。もし、これが北海道であれば様相は違って来ただろう。複数のライバル企業が狭いスペースでひしめきあう緊張感、それが明治維新という化学変化を生んだのである。幕末のビットバレーは、間違いなく京都だったのだ。
最近、龍馬の暗殺現場である近江屋が現在では碑のある場所になかったという奇説が提唱されている。確かに、当時の古地図上に、近江屋があったとされる場所には寺が描かれている。これは何を意味しているのだろうか。そもそも近江屋の関係者たちの発言も整合性が無い。龍馬の暗殺事件は、暗殺場所も含め、土佐藩によって情報操作された可能性は無いだろうか。筆者は土佐藩黙認の上で、薩摩藩の意向を汲んだ者が殺ったのではないかと解釈している。
また、龍馬とおりょうの新婚旅行の軌跡を辿ってみると、旅行の工程が二人の人生と被ってくるのがわかる。二人が上陸した後、温泉に入り、谷川でピストルを撃ち、霧島神宮に参拝する過程は、二人が出会い、寺田屋での危機をピストルで突破し、龍馬が暗殺され帰天してしまう流れと一致する。あまりにも暗示的で、マジカルなハネムーンであった。
更に、幕末の志士たちの生家巡りをすると、彼らの思想がよくわかる。山々に囲まれ取り残されたような集落。吉村寅太郎や中岡慎太郎の生まれた村は、小さな宇宙空間であった。彼らが、「只ここで生まれ、ここで死ぬのはいやだ」と思った気持ちは痛いほどわかった。自らの生きる空間に何も存在しないが故、何かを求めたのだろう。
また、岩崎弥太郎の生家の庭には、彼が石で造った日本地図が残されている。龍馬の遺産を受け継いだ男の感性は、庭を日々睨む事で形成されたのだ。
更に、龍馬が自然堂と称した下関の伊藤助太夫邸は、おりょうが龍馬の訃報に接した場所だが、この屋敷跡の隣接地は春帆楼という旅館であり、この場所は日清戦争の講和会議が行われた史跡である。この会議で、大国・清を相手にハードネゴシエイトを演じたのは海援隊の隊士だった陸奥宗光である。講和条約に挑む陸奥の胸に、在りし日の龍馬がよぎったことは容易に察する事ができる。
龍馬の生家があり、都市化の進む高知の本丁筋でさえも、龍馬の悲鳴が聞こえてきた。余所者に対して排他的であり、閉塞感の漂う土佐の気風に育った龍馬だからこそ、身分の無い海に活路を見出し、己の手足を縛る藩という壁を飛び越える事ができたのだ。
龍馬の婚約者で、暗殺事件後も独身を守り通した千葉さなの晩年のエピソードも泣かせる。鍼灸店を開業した千葉さなに顧客を紹介したのは板垣退助であった。板垣が紹介した山梨の自由民権運動家・小田切謙明とその妻は千葉さなを終生支援し、千葉さなの骨は甲府の小田切家の墓所に埋葬されている。板垣退助の龍馬への想いが推測される逸話である。
また、おりょうの終焉の地、横須賀では酒に溺れた晩年のおりょうに涙が止まらなかった。図らずも、龍馬を奉った戦艦・三笠が、日露戦争で旗艦という大役を果たした後、横須賀に曳航されている。死後、二人は横須賀の地で再会したのだ。
龍馬を想い、龍馬の背中を追う日々を僕は送っている。僕らの眼前には、世界的な不況で死屍累々の惨状が広がっている。僕らの平成維新は不毛の荒地から始まる。人を殺さない英雄、坂本龍馬。彼の生き様こそ、日本再生のヒントになるのだ。
龍馬を巡る私の旅
山口敏太郎
@昔の記事の蔵出し
人間の人生は、旅に例えられる事が多い。生きる事そのものが旅であり、死ぬことさえも新たなる旅立ちかもしれない。今回は龍馬の人生を辿る“私の旅”を紹介してみたい。
我々、現代人にとって幕末最大の英傑と言えば坂本龍馬である。そもそも終戦直後までは、幕末の英傑と言えば西郷隆盛であった。だが、英傑の理想像に関して変換期が訪れる。1962年、司馬遼太郎が「竜馬がゆく」を発表してから、龍馬を英雄視する傾向が強くなったのだ。いや、司馬だけのせいではあるまい。父権的国家だった日本が、個人主義に移行していく価値観の変遷が、西郷から龍馬へという英雄像の変遷を生んだ可能性は高い。
龍馬に魅力を感じてから、20数年間、私は時折龍馬の残像を追い求める旅をしている。事件現場において、プロファイリングする事により、犯人の心理に迫れる事があるように、幕末の現場に立つことで、新しい発見があるのも事実である。
まず、龍馬暗殺の現場と言われている近江屋であるが、この周辺に池田屋、酢屋、土佐藩邸など数多くの史跡がある事に気がつく。幕末の頃、薩長も会津もかなり狭い空間で凌ぎを削っていたのだ。もし、これが北海道であれば様相は違って来ただろう。複数のライバル企業が狭いスペースでひしめきあう緊張感、それが明治維新という化学変化を生んだのである。幕末のビットバレーは、間違いなく京都だったのだ。
最近、龍馬の暗殺現場である近江屋が現在では碑のある場所になかったという奇説が提唱されている。確かに、当時の古地図上に、近江屋があったとされる場所には寺が描かれている。これは何を意味しているのだろうか。そもそも近江屋の関係者たちの発言も整合性が無い。龍馬の暗殺事件は、暗殺場所も含め、土佐藩によって情報操作された可能性は無いだろうか。筆者は土佐藩黙認の上で、薩摩藩の意向を汲んだ者が殺ったのではないかと解釈している。
また、龍馬とおりょうの新婚旅行の軌跡を辿ってみると、旅行の工程が二人の人生と被ってくるのがわかる。二人が上陸した後、温泉に入り、谷川でピストルを撃ち、霧島神宮に参拝する過程は、二人が出会い、寺田屋での危機をピストルで突破し、龍馬が暗殺され帰天してしまう流れと一致する。あまりにも暗示的で、マジカルなハネムーンであった。
更に、幕末の志士たちの生家巡りをすると、彼らの思想がよくわかる。山々に囲まれ取り残されたような集落。吉村寅太郎や中岡慎太郎の生まれた村は、小さな宇宙空間であった。彼らが、「只ここで生まれ、ここで死ぬのはいやだ」と思った気持ちは痛いほどわかった。自らの生きる空間に何も存在しないが故、何かを求めたのだろう。
また、岩崎弥太郎の生家の庭には、彼が石で造った日本地図が残されている。龍馬の遺産を受け継いだ男の感性は、庭を日々睨む事で形成されたのだ。
更に、龍馬が自然堂と称した下関の伊藤助太夫邸は、おりょうが龍馬の訃報に接した場所だが、この屋敷跡の隣接地は春帆楼という旅館であり、この場所は日清戦争の講和会議が行われた史跡である。この会議で、大国・清を相手にハードネゴシエイトを演じたのは海援隊の隊士だった陸奥宗光である。講和条約に挑む陸奥の胸に、在りし日の龍馬がよぎったことは容易に察する事ができる。
龍馬の生家があり、都市化の進む高知の本丁筋でさえも、龍馬の悲鳴が聞こえてきた。余所者に対して排他的であり、閉塞感の漂う土佐の気風に育った龍馬だからこそ、身分の無い海に活路を見出し、己の手足を縛る藩という壁を飛び越える事ができたのだ。
龍馬の婚約者で、暗殺事件後も独身を守り通した千葉さなの晩年のエピソードも泣かせる。鍼灸店を開業した千葉さなに顧客を紹介したのは板垣退助であった。板垣が紹介した山梨の自由民権運動家・小田切謙明とその妻は千葉さなを終生支援し、千葉さなの骨は甲府の小田切家の墓所に埋葬されている。板垣退助の龍馬への想いが推測される逸話である。
また、おりょうの終焉の地、横須賀では酒に溺れた晩年のおりょうに涙が止まらなかった。図らずも、龍馬を奉った戦艦・三笠が、日露戦争で旗艦という大役を果たした後、横須賀に曳航されている。死後、二人は横須賀の地で再会したのだ。
龍馬を想い、龍馬の背中を追う日々を僕は送っている。僕らの眼前には、世界的な不況で死屍累々の惨状が広がっている。僕らの平成維新は不毛の荒地から始まる。人を殺さない英雄、坂本龍馬。彼の生き様こそ、日本再生のヒントになるのだ。



















































