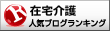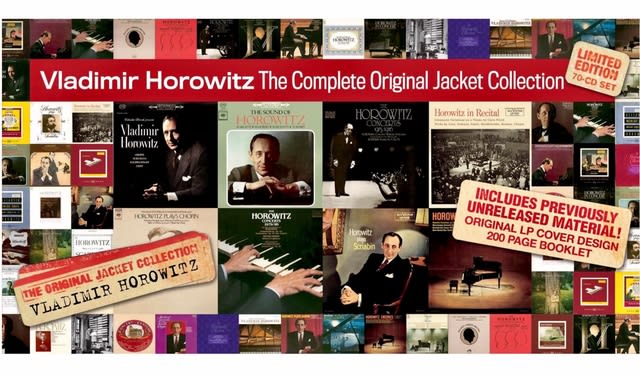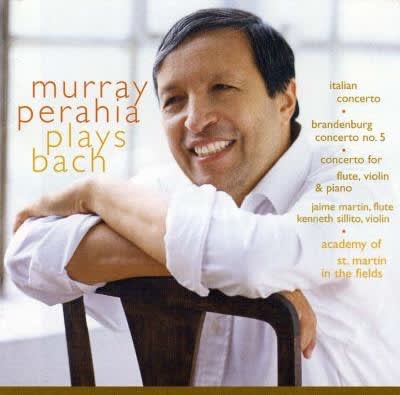・ショパン:ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調Op.35『葬送』
・ショパン:バラード第1番ト短調Op.23
・ショパン:夜想曲第5番嬰ヘ長調Op.15-2
・リスト:巡礼の年第1年『スイス』より『泉のほとりで』
・リスト:ハンガリー狂詩曲第6番ニ長調『ペストの謝肉祭』
録音時期:1947年5月16&19日、1950年5月13日[LM-1235]
ウラディミール・ホロヴィッツ
そうそうスビャトスラフ・リヒテルやエミール・ギレリスにラザール・ベルマンなどもそうですがウラディミール・ホロヴィッツは楽器を弾ききった音が大変綺麗なのです。
大音量ですが決して汚くならないのが彼らの特徴でしょうか?
このショパンのソナタ2番
導入は仰々しくホロヴィッツ特有の解釈でしょうか?ゆったり弾ききってピアニッシモからフォルテシモまでしっかり楽器というものを鳴らしきってるのがスビャトスラフ・リヒテルと比べてしまうのかもしれません。
ホロヴィッツのこの頃の演奏はラジオで聴いていたでしょうか?
柿島秀吉