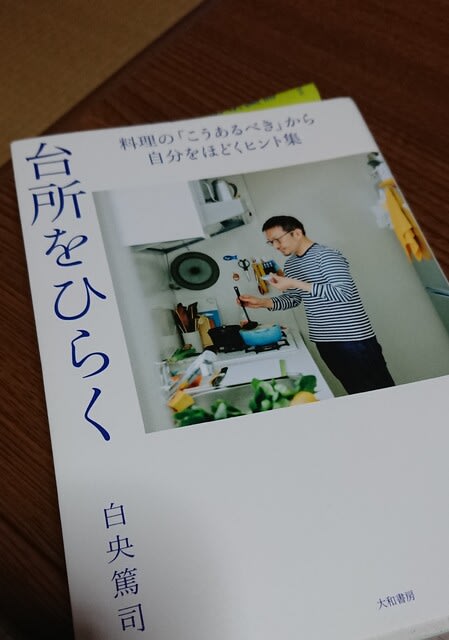真夏日予想だった昨日でしたが、なんとか28℃台で済みました。でも日差しの下は暑かったですね。
毎朝6時過ぎには洗濯物を干していますが、昨日はカラッとしていたこともあって10時過ぎに乾き具合をみるとすっかり乾いていたので取り込んで。
ついでに2階の窓の網戸を外して洗い、窓拭きもしました。久しぶりだったので窓の汚かったこと!
そんな気になったのは、一昨日届いたエッセイストの小川奈緒さんの新作を読んだ影響があったから。
きれい好きと自認している小川さんの暮らしの様子を読んでいると、自分のずぼらな毎日が恥ずかしくなってきます。
一時的にでも心を入れ替えて少しはきれいにしようと思えるのなら、読んだものに影響を受けやすい単純な性格もいいんじゃないかと思えます。というところからして単純だな。
その新作のタイトルは「家 が 好きで」というもの。
なんだかシンプルなタイトルではあるけれど、なんだかちょっと気になることが。よくよく見ると「家」と「が」と「好きで」の間に半角程度の空きがあるんです。私もそれに倣って
みましたが、シンプルなタイトルがこんなわずかなことで目に引っかかるというか、視覚に影響があるものなんだなと思いました。
カバーのコバルトブルーが小川さんのお宅にあるゴールデンベルという証明の金色の補色になって、ぐっと目を惹きます。
昔装幀家の栃折久美子さんの「製本工房から」という本を読んでから、本を買うたびに装幀にも注目してきました。残念ながら最近の単行本は価格を抑えたいというところもあれば
電子書籍の台頭もあって、以前のような上製本での出版はほとんどありません。
本を読みかけで置いておくときに開きっぱなしに出来ないものばかりで、スピン(細い紐状の栞)もないから、本の帯だったり時には輪ゴムを栞代わりにすることも。
先日買った本は帯とは呼べないほど幅が広いもので、まるで腰巻。栞代わりに使うにはちょっと大きすぎましたっけ。
本の中身についてはまた改めて書こうかなと思っています。とりあえず一読は終って二読め中。一読めはかなり突っ走って読むので読み飛ばしが多いんです。
本と言えば、今月に入ってからEテレで放送されている「理想的本箱」を録画して観ています。これ、結構面白くて。
自分の好みだけで本を選んでいるだけではなかなか出合えないものに触れることが出来るのが、この番組のよさ。この番組ではその本を紹介する「映像の帯」という数分の映像で
中身の一部を紹介するのだけれど、文字で書かれた(時に絵本もあるけれど)ものを映像化した人がどのようにその本を感じたか視覚化することの面白さがいい。
最近はコミックがドラマ化されるほうが多いけれど、小説をドラマ化するときにその小説をまだ読んでいないときには、私は先に本で読んでおきたいタイプ。
文章だけで作り上げた自分の脳内イメージと映像化されたそのイメージとの比較したいんです。先に映像化されたものを見てから本を読むと、頭に浮かぶ主人公が某俳優さんになって
しまうじゃないですか。そうではなくて逆に、自分がドラマ化するとしたらどの俳優さんを選ぶか、などと考えるのも楽しみのひとつだと思うんです。
となると、「映像の帯」はあまりありがたくないか?と言われると、そうでもない。
全く興味のないジャンルの本に対するとっかかりをもらえるように思えるからです。
この前の放送は、「同性を好きになったときに読む本」というコンセプトで選ばれた本3冊。そういった経験はないけれど、最近はドラマなどでも取り上げられることが多く
なりましたよね。私はドラマはほぼ見ないので、中身はよく知りません。まだこれは観ていなくて、時間があるときにさっさと観なくては。
毎回思うのは、本を選ぶブックディレクターの幅さんの本に対する知識の豊富さと造詣の深さ。職業柄とはいえレベルが違いすぎますね。