 北陸にいよいよ寒波がやってきた。金沢の冬の風情と言えば「雪つり」だ。市民も兼六園や街路樹で雪つりが始まると冬の訪れを実感するのではないだろうか。
北陸にいよいよ寒波がやってきた。金沢の冬の風情と言えば「雪つり」だ。市民も兼六園や街路樹で雪つりが始まると冬の訪れを実感するのではないだろうか。
この雪つりは自分でやるとなると結構技術がいる。造園業者に任せると金がかかる。暖冬が続き雪が降らないと、「庭税」のように忌々しく思えてきて、風情を楽しむどころではない。
ところが、2004年の冬のように、50㌢を超す大雪となると、が然と雪つりはその威力を発揮する。上の写真は雪つりが施されたもの。同じ場所での下の写真をご覧いただければ分かるように、 こんなに雪が積もると、何代にもわたって育ててきた五葉松(東日本では姫小松とも呼ぶ)も枝が折れてしまう。何しろ金沢の雪はパウダースノーではなく、たっぷりと湿気を含んだベタ雪なので重い。松の枝を一本一本支えている縄のおかげで、枝が折れずに済んでいる。
こんなに雪が積もると、何代にもわたって育ててきた五葉松(東日本では姫小松とも呼ぶ)も枝が折れてしまう。何しろ金沢の雪はパウダースノーではなく、たっぷりと湿気を含んだベタ雪なので重い。松の枝を一本一本支えている縄のおかげで、枝が折れずに済んでいる。
「庭税だ」云々と言ってはみても、ドカ雪がやってくるか予想できないから雪つりはやめられない。金沢に住んでいる以上は仕方がない。これはもうスタッドレスタイヤやスコップと同じように「雪国の住民税」と考えるしかないのである。
でも、こうして写真を眺めていると、金沢の先人の知恵というものが伝わってくる。一説にリンゴつりの応用で兼六園で使われた手法が広く伝わったともいわれるが、雪つりのルーツについては定かではない。
ともあれ、ことしの冬は雪つりの値打ちを実感できるほど雪が降るのか、あるいは「庭税」と思ってしまうのか。
⇒30日(水)朝・金沢の天気 あめ










 テーマ「記事をリフォームする」
テーマ「記事をリフォームする」  だと、少々手の込んだ作り変えが必要だ。「
だと、少々手の込んだ作り変えが必要だ。「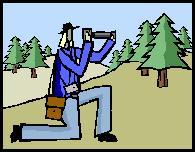

 ア「里山メイト」が自主的に栽培したダイコン畑。雨上がりで土壌が軟らかかったこともあり、ダイコンは意外とすっぽりと抜けた。
ア「里山メイト」が自主的に栽培したダイコン畑。雨上がりで土壌が軟らかかったこともあり、ダイコンは意外とすっぽりと抜けた。 

 話題となってその知名度が大きく上がった。2004年の米大統領選挙では民主党陣営が草の根的にブログを使い広がった。ブロガーは本名記載、コメントも本名投稿が原則である。これに対し、日本では「2ちゃんねる」に代表される掲示板というインターネット文化がブログ以前からあり、文章も一話完結ではなく、「日々綴る」風の日記形式が多い。そして、書き手は匿名あるいはハンドルネームが主流だ。大雑把に言えば、日本は匿名・日記風、アメリカは本名・コラム風と対比できるかもしれない。
話題となってその知名度が大きく上がった。2004年の米大統領選挙では民主党陣営が草の根的にブログを使い広がった。ブロガーは本名記載、コメントも本名投稿が原則である。これに対し、日本では「2ちゃんねる」に代表される掲示板というインターネット文化がブログ以前からあり、文章も一話完結ではなく、「日々綴る」風の日記形式が多い。そして、書き手は匿名あるいはハンドルネームが主流だ。大雑把に言えば、日本は匿名・日記風、アメリカは本名・コラム風と対比できるかもしれない。

 ブログにしろ、SNSにしろ無料のサービスが多い。では、同じ無料という条件のなのに、あまたあるブログのサイトの中から、私の場合なぜ「goo」のサイトを選んだのか、である。確かにライブドアは2003年12月にブログサイトを開設した「老舗」である。その老舗を選ばなかった理由は…。
ブログにしろ、SNSにしろ無料のサービスが多い。では、同じ無料という条件のなのに、あまたあるブログのサイトの中から、私の場合なぜ「goo」のサイトを選んだのか、である。確かにライブドアは2003年12月にブログサイトを開設した「老舗」である。その老舗を選ばなかった理由は…。 もともとブログを始めたのは秋田市に住む友人Y・M氏の影響だ。ブログそのものは2003年12月にニフティとライブドアが無料ブログのサービスを開始してから、気にはなっていた。Y・M氏のメールの署名にブログのURLが付けてあり、クリックするとアート展の話題や美術館めぐりの感想、交遊録などが綴られ、そのうちに「アクセスIP数6000突破!」などと、いかにも本来のブログ(日記風)を楽しんでいるといった様子が目に浮かんだ。彼も私ももともとライターを生業(なりわい)としていた時期があって、書くことの楽しさというものを感覚と共有している。有り体に言えば、彼がちょっと羨ましくなったのである。
もともとブログを始めたのは秋田市に住む友人Y・M氏の影響だ。ブログそのものは2003年12月にニフティとライブドアが無料ブログのサービスを開始してから、気にはなっていた。Y・M氏のメールの署名にブログのURLが付けてあり、クリックするとアート展の話題や美術館めぐりの感想、交遊録などが綴られ、そのうちに「アクセスIP数6000突破!」などと、いかにも本来のブログ(日記風)を楽しんでいるといった様子が目に浮かんだ。彼も私ももともとライターを生業(なりわい)としていた時期があって、書くことの楽しさというものを感覚と共有している。有り体に言えば、彼がちょっと羨ましくなったのである。 こけたような静寂、との意味だろう。人の眠りは「死」と同意語だ。先日、人生の大先輩、Y・Sさんの訃報を受けた。
こけたような静寂、との意味だろう。人の眠りは「死」と同意語だ。先日、人生の大先輩、Y・Sさんの訃報を受けた。




