神奈川の聖光学院って、すごい。進学成績が。
東大理三の合格者で、ついに開成に並びました。
来年はついに開成を抜くぞ!って息巻いているはず。
聴くところによると、塾に活かせず、勉強ばっかりらしい。
それが中高生の心身の健全な発達に良いか悪いかはともかく。
新時代がやってきたようです。
凋落した我が母校桐蔭学園から1人。1人でもすごいじゃないか。あっぱれ。
ブログ化しようと思っていたら先に産経新聞に記事にされちゃった。
中学受験は年々?激化している。我々が中学受験した頃とは大違いの、レベルの高さ。
でも、合格の倍率は、高くない。
いわゆる御三家でも、軒並み、2倍くらい。
麻布に至っては2倍を切っている。
こちら(産経新聞記事)
3を超えるのは、筑駒(4倍)と、2月4日の聖光学院(6倍)くらい。
だから何だというわけではないですが、世相の一つとして。
堅実志向の表れ、というこの産経のまとめ方にはなるほどと思いました。
アドラー心理学とかを学んだからだろうか、子どもをとても冷静に嗜める/叱ることができた。
一つの成功体験として記録しておく。
【出来事】
- 小学生の子どもが、夜7時半~8時、行方不明に
- 親が指定したお迎えの待ち合わせ時間に来ずに、友達と歩いて帰宅
- 親は待ち合わせ場所で30分くらい待ちぼうけに
- 誘拐を恐れて気が気ではない思いをした…
【私がしなかったこと】
- なんで来なかったんだ!
- なんで待たせたんだ!
- 心配したんだぞ!
- ちゃんといつどこに来てと言っただろ!
的な、感情的な叱責は一言も言わなかった。
【私が伝えたこと】
君は信頼関係を失った。親との間の。
親との約束を忘れたのか、何か勘違いしたのかは、問わない。
結果論として、親との約束を守れずに、親や周りに迷惑をかけた。
これは、親との約束ないしは親そのものに対する、優先順位が低かったから。
仮にこれが天皇陛下との約束や大谷翔平との約束だったら?
忘れたり勘違いしたりすることはなかったはず。
だから、忘れるとか勘違いするってのは、その相手に対する優先順位が低いということ。
優先順位が低いということは、十分にリスペクトしていないということ。
人は、「リスペクトされていない」と思うと、信頼関係を失う。
リスペクトを払わない相手との間では、信頼関係を築けない。
今回のことはもういい。親に対してはリスペクトを支払わないといけない。
特に、迎えに来てくれている親に対しては。
失った信頼関係は、すぐには取り返せない。
数日では無理。
数週間、ないし、数ヶ月かけて、親との信頼関係を回復するように努めなさい。
____________
ちょっと理詰めすぎたかもしれませんが、、、
子育てってのは正解がない歩みですねぇ。
長男中2が、私が中学生を過ごした神奈川で中学生生活を送っている。私と同じ野球部。
私が中2~中3のとき、横浜市大会で優勝して、横浜スタジアム開催の第六回全日本少年軟式野球大会に出場した。平成元年。
こちら(前年にはイチローも出ている)
それを知っている長男が、「春の大会全勝して、お父さんみたいに全日本に出る」と息巻いている。
いいぞ、その志。
息子の成長が嬉しい反面、おぉ、私が中学時代からもう一世代経っちゃったのねと、ちょっと寂寥感というか、黄昏感というか、老化感というか、そんな秋の香りを感じました。
本日行われた、伊藤塾同窓会「まこと会」第四回定時総会で、伊藤塾のスローガンみたいな
やればできる、必ずできる
の誕生秘話を、伊藤真塾長から教わった。
司法試験で苦労している自分には「ちくしょー、できる奴が結果論で言いやがって」的に斜に構えて恨み骨髄的に捉えることもあった、「やればできる、必ずできる」。
「必ずできる」なら司法試験の合格率2%(当時)は説明できないよ、と当時から批判はあった。
でも。
結果論だと批判されても構わない。論理的でなくても構わない。稲盛和夫的なポジティブすぎる精神論であっても構わない。
今の私は「やればできる、必ずできる」には肯定的。
若者を鼓舞するにはこういう「非論理的な」仕掛けが必要。教祖になるには不合理性がないといけない。
理屈と確率論を考えすぎる奴には、何の挑戦もできない。
____________
その「やればできる、必ずできる」は、、、
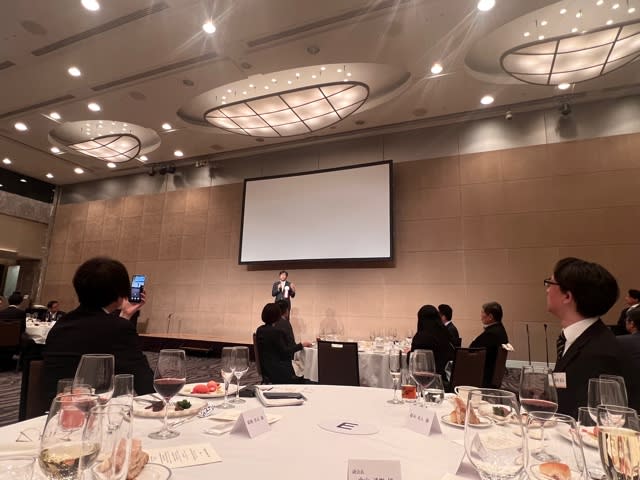
伊藤真塾長オリジナルではなかった。
ご尊父(95歳)のお言葉だった。
伊藤真塾長のご尊父(当時は中学教師)のところに、学生がやってきて、「南極に行きたい」と。
伊藤真塾長ご自身も中学生の頃の話だから、今から52年くらい前、1973(昭和48年)ころの話。
伊藤真塾長ご尊父が、その「南極へ行く」夢を抱く青年に、「うん、南極に行くにはな、勉強して、気象庁に入ったりして…」と懇々と丁寧にその道筋を説いた。
ご尊父がいつも仰っていた「やればできる、必ずできる」と添えて。
____________
それから10年くらい。
ご尊父のところに、その青年がふらっとやってきた。伊藤真塾長も大学生くらいで、同席していた。
青年は、お土産を持っていた。
お土産が、、、、
南極の氷。
伊藤先生(ご尊父)のお陰で、本当に南極に行きました、これがそのお土産の、南極の、氷です。
伊藤先生、本当に、「やればできる、必ずできる」んですね。やれば、できました。
本当にありがとうございました。
____________
※ 30年前に、聞きたかったエピソード。
これを聞いていれば、私はもっと早く司法試験に受かっていたのでは。
#子どもたちよ。
理想を高く持ちなさい。
誰を理想とするかで人生は決まる。
「この状況だったら誰だってこういうことするだろ」と自分を正当化しない。
自分を基準にするのではない。
平凡人を基準にするのではない。
「理想とする人物ならどうするか」を基準にしよう。
理想とする人物は、言い訳はしないはずだ。
私・お父さんが尊敬する人物の一人が中島敦『李陵』に出てくる蘇武。
蘇武持節という故事になって、19年の極寒と孤独に耐え忍んだ義士。
彼は決して「やむを得ない」と自分を正当化しなかった。
自分を正当化するのは逃げで、負けだ。
やせ我慢して、歯を食いしばり、「やむを得ない」と言わない。
人生はそこから始まるのだとお父さんは思っているよ。
~~~以下引用~~~
ここに一人の男(蘇武)があって、いかに「やむを得ない」と思われる事情を前にしても、断じて、自らにそれは「やむを得ぬのだ」という考え方を許そうとしないのである。
飢餓も寒苦も孤独の苦しみも、祖国の冷淡も、己の苦節がついに何人(なんぴと)にも知られないだろうというほとんど確定的な事実も、この男にとって、平生の節義を改めなければならぬほどのやむを得ぬ事情ではないのだ。
~~~引用終わり~~~
■ 娘
小5になる娘の中学受験に備え、私立中学校見学。
男子中と違って、女子中はセキュリティ上、決して校内を見学させてくれない。(男子校は、だいたい中を見せてくれる。駒東なんか、校舎内まで、どうぞどうぞって感じで自由に見せてくれた、、、)
先週末に東京の8校、今週に神奈川の5校をチラ見。
パンフレットだけはくれる学校が多い。東京では要求したら7校中、7校がくれた。神奈川ではなぜか5校中、2校のみ、、
娘のモチベーションが上がってくれれば。
■ 次男
受験が終わった漫画を読みまくる1ヶ月が終了。
英語の勉強を私と始めた。a から z までと、自分の名前くらいは筆記体で書けるように。
筆記体なんて、中1の今教わらないと一生書けない? 大人になってサインをするときに、ブロック体では、、、
私は中高の試験でも筆記体で解答していたのかなぁ。英語の塾の講師をしているときも黒板には筆記体で書いていたはずだ。
____________
野球のスイングはここ数年ドアスイング気味だったのですが、「体の軸の近くをまとわりつくようにバットを振る」ことを教えたら、一瞬でドアスイングが治った。
小手先ではなく、軸なんですね。
ちなみに、肩を傷めない投げ方も、「軸の近くでリリース」するように投げればいい。これはいつか子どもたちにも教えよう。
■ 長男
英語も野球もがんばっているよう。野球はもう私よりスイングが鋭い。
将棋と社会が得意。
私の身長をいよいよ超えそう。志の高さは負けん!と父は強がっています。
____________
最近気がついたのですが、うちの家族は、お風呂に入ったあと、次に入る人に、「上がったよ~ ◯◯、入りなよ~」って声をかけている。
私の実家ではやっていなかった。
これは愛情のある良い声掛けだ、微笑ましい。
私が大学受験した1993(平成5)年、東大入試を受けながら、世界史の問題のクオリティの高さに感動したのを覚えている。
さすが東大だなあと。
嬉々として頑張って解答用紙を埋めた。
ベトナム戦争と朝鮮戦争の問題だった。
って記憶していたけど、今調べると、ベトナム戦争とベルリンの壁の問題。
50歳の私が今見ても、ちんぷんかんぷんですが。18歳の理解力というのは、たいしたもんなんですね、、、
こちらのサイト
____________
第1問
現在、世界は冷戦の終わりを迎えている。
第二次世界大戦後、長期にわたって世界史の流れに大きな影響を与えた冷戦は、世界の各地域で異なった現われかたをした。
冷戦下の深刻な問題の一つが分裂国家の出現であったが、これまでにヴェトナムとドイツの二つの分裂国家が統合されている。
この二つの分裂国家の形成から統合への過程を、冷戦の展開と関連づけて略述せよ。
解答は、下に示した語句を一度は用いて、解答欄(イ)に20行以内(600字)で記せ。また、使用した語句には下線を付せ。
ゴルバチョフ ジュネーヴ会議 封じこめ政策 平和共存 ベルリンの壁
____________
以上、社会が好きな長男たちと、社会の勉強とか大学受験とかの話題になったので、家庭で話したネタでした。























