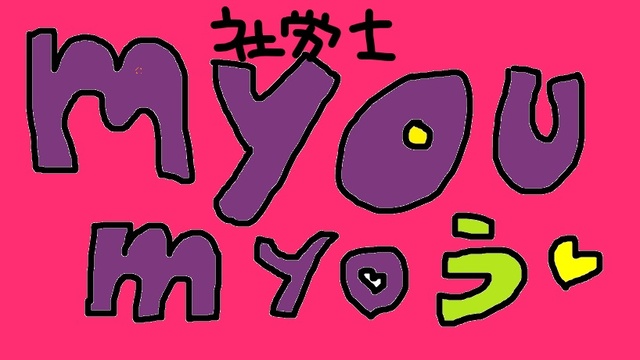特養に勤務する介護士の方から話を聞く機会があった。4~5年前に比べ、業務量が格段に増えたうえに、あまりの人手不足のため休日を買い取って勤務にあたっているとのことだ。人手不足もさることながら、なぜ業務量がそれほど増えたのかということだが、とにかく〇〇委員会というものがいくつもあり、すべてが通常の勤務外で行われるということだ。そのなかで、ある介護者が悲鳴をあげているのが「介護力向上委員会」なるものだ。全国老人福祉施設協議会(老施協)が推進している「科学的介護」を実践し・報告する委員会だそうだ。科学的介護?センスのないネーミングだな…という意見はさておき、それはなんですか?ということですが、「基礎知識」「理論」「技術」「経験知」を下敷きにした介護です。って…まだわからないな。科学的介護の提唱者・指導者である国際医療福祉大学院の竹内孝仁教授によれば、高齢者の基本ケアは「水分」「食事」「排便」「運動」であり、これらは相互にリンクしているので徹底してやるべし!というようなことらしいのだが…これって新しい理論なんですかね…
昔から言われ続けていたことのような気がしますが。
では、なぜこれを実践すると、介護者は悲鳴をあげるのでしょうか。
1日1500ml以上の水分を全入居者に流し込み、こうしゅくといって、手足の関節が固まっている人をトイレに座らせ、数人がかりで歩行訓練を実施するからです。水分を流し込んで数十分後腹部に圧力をかけるので、嘔吐する入居者が後をたたず、全身浮腫で亡くなる入居者が数人でているにもかかわらず、ブレーキのきかない車のようにこの取り組みを中止することができないからです。「介護力向上委員会」どころか「人殺し委員会」だと半泣きで話してくれました。この科学的介護は提唱者の名前をとって「竹内理論」と言われていますが、心酔している職員が多く、何を言っても「やるか、やらないかだ」といった調子で、聞く耳持たずだそうです。竹内教授も「特養はこれをやって生き残るか、やらずに自滅するかだ」といった調子でガンガン推し進めています。これはもう完全に思考停止状態です。典型的な二分法です。科学的介護の中身はともかく、どのようにやるかといった議論はまったくなされていません。
注目されている方法を実践することで、いくらかのお金が施設にはいるのかもしれません。しかし施設のトップは、煽動的な言葉に踊らされるのではなく、冷静に現状を見極めるべきです。心酔してしまい、これをやらねば介護ではない、となっている職員に迎合するのではなく、施設運営者として逃げずに対処していただきたいです。
昔から言われ続けていたことのような気がしますが。
では、なぜこれを実践すると、介護者は悲鳴をあげるのでしょうか。
1日1500ml以上の水分を全入居者に流し込み、こうしゅくといって、手足の関節が固まっている人をトイレに座らせ、数人がかりで歩行訓練を実施するからです。水分を流し込んで数十分後腹部に圧力をかけるので、嘔吐する入居者が後をたたず、全身浮腫で亡くなる入居者が数人でているにもかかわらず、ブレーキのきかない車のようにこの取り組みを中止することができないからです。「介護力向上委員会」どころか「人殺し委員会」だと半泣きで話してくれました。この科学的介護は提唱者の名前をとって「竹内理論」と言われていますが、心酔している職員が多く、何を言っても「やるか、やらないかだ」といった調子で、聞く耳持たずだそうです。竹内教授も「特養はこれをやって生き残るか、やらずに自滅するかだ」といった調子でガンガン推し進めています。これはもう完全に思考停止状態です。典型的な二分法です。科学的介護の中身はともかく、どのようにやるかといった議論はまったくなされていません。
注目されている方法を実践することで、いくらかのお金が施設にはいるのかもしれません。しかし施設のトップは、煽動的な言葉に踊らされるのではなく、冷静に現状を見極めるべきです。心酔してしまい、これをやらねば介護ではない、となっている職員に迎合するのではなく、施設運営者として逃げずに対処していただきたいです。