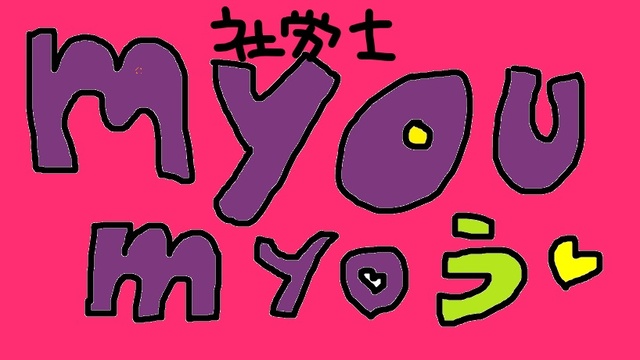ショッピングセンター内でのテナント社員の事故は業務災害(労災)なのか、通勤災害なのか。
特定社労士:皆川夕美さんのブログを興味深く読ませていただきました。
社労士なればこそ、労災か通災か?という疑問がでてくるわけで、雇用されている労働者や経営者にしたら、自分のお店(テナント)から一歩でも出れば、お店は関係ないと思っている人が多いはずです。
骨折とかの大きな事故ならともかく、飲食店のちょっとした(実際はちょっとしたなんてもんじゃないが)火傷などのけが程度だと、人手が足りなかったり、忙しかったりで応急処置だけして、仕事の後に「健康保険」(業務以外ということです)を使って受診したりしています。そんなわけですから、テナントが入っているSC内でのけがなど、当たり前のように業務外と思うのです。仕事中にトイレへ行った場合の事故でさえ、業務中の災害とは思わないくらいです…
通勤という概念だって、一般労働者と法律の規定するところでは大きくずれています。労災・通災を労働者がきちんと理解していれば、申請数はもっと多くなると思います。事業主への遠慮もありますが、認識のズレも大きいのです。救済されるべき人が救済されていないのが現実ではないでしょうか。
皆川さんのブログでは、「SC内の事故は業務災害」と判断されてました。
SC内は、①閉館後施錠され、誰でも自由に往来できる場所ではないこと②共用部分の諸経費を、テナント面積に応じて負担している、ことなどから「駐車場も含めて労災になる」ということでした。
私は過去にSC内のテナントで働いた経験がありますが、私用で買い物をする時のルールなどが決められてはいますが、守られていないことも多いです。制服着用のルールも店によって様々で、表向き更衣を義務付けているが家からの着用を黙認していたり、ビルの入退室管理も曖昧なところがあり、SC内は労災といわれても、経営者として納得できないこともあるかと思います。
例えばですね、こんなケースがあったとします
13時からの勤務なのに、11時ごろに来てビルの入室チェックもすませ、テナントの控室で制服に着替えて(私服の上着をはおります)、SC内をぶらぶらしています。12時45分ごろ一旦控室に戻る際、転倒して骨折しました。
これって、なんですか?
こんなふうに考え出すとキリがないのですが、労災か通災か、あるいは業務外か以前に「労務管理に問題あり」です。
あっ、それと「各労働局で見解に相違があるのが大きな問題」と皆川さんは言ってます…
特定社労士:皆川夕美さんのブログを興味深く読ませていただきました。
社労士なればこそ、労災か通災か?という疑問がでてくるわけで、雇用されている労働者や経営者にしたら、自分のお店(テナント)から一歩でも出れば、お店は関係ないと思っている人が多いはずです。
骨折とかの大きな事故ならともかく、飲食店のちょっとした(実際はちょっとしたなんてもんじゃないが)火傷などのけが程度だと、人手が足りなかったり、忙しかったりで応急処置だけして、仕事の後に「健康保険」(業務以外ということです)を使って受診したりしています。そんなわけですから、テナントが入っているSC内でのけがなど、当たり前のように業務外と思うのです。仕事中にトイレへ行った場合の事故でさえ、業務中の災害とは思わないくらいです…
通勤という概念だって、一般労働者と法律の規定するところでは大きくずれています。労災・通災を労働者がきちんと理解していれば、申請数はもっと多くなると思います。事業主への遠慮もありますが、認識のズレも大きいのです。救済されるべき人が救済されていないのが現実ではないでしょうか。
皆川さんのブログでは、「SC内の事故は業務災害」と判断されてました。
SC内は、①閉館後施錠され、誰でも自由に往来できる場所ではないこと②共用部分の諸経費を、テナント面積に応じて負担している、ことなどから「駐車場も含めて労災になる」ということでした。
私は過去にSC内のテナントで働いた経験がありますが、私用で買い物をする時のルールなどが決められてはいますが、守られていないことも多いです。制服着用のルールも店によって様々で、表向き更衣を義務付けているが家からの着用を黙認していたり、ビルの入退室管理も曖昧なところがあり、SC内は労災といわれても、経営者として納得できないこともあるかと思います。
例えばですね、こんなケースがあったとします
13時からの勤務なのに、11時ごろに来てビルの入室チェックもすませ、テナントの控室で制服に着替えて(私服の上着をはおります)、SC内をぶらぶらしています。12時45分ごろ一旦控室に戻る際、転倒して骨折しました。
これって、なんですか?
こんなふうに考え出すとキリがないのですが、労災か通災か、あるいは業務外か以前に「労務管理に問題あり」です。
あっ、それと「各労働局で見解に相違があるのが大きな問題」と皆川さんは言ってます…