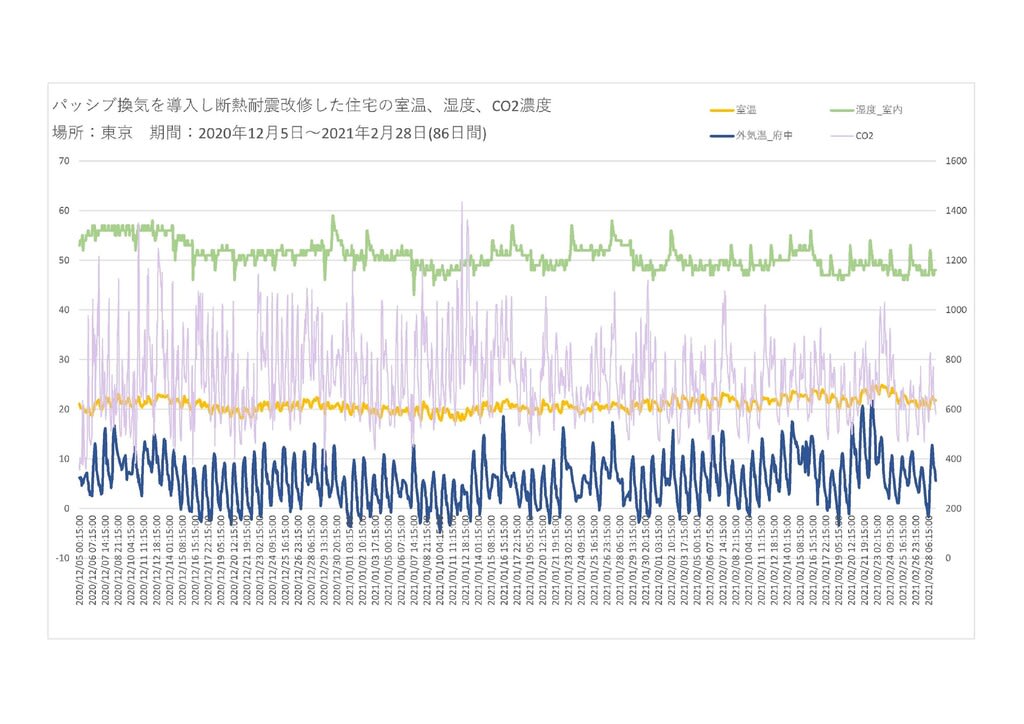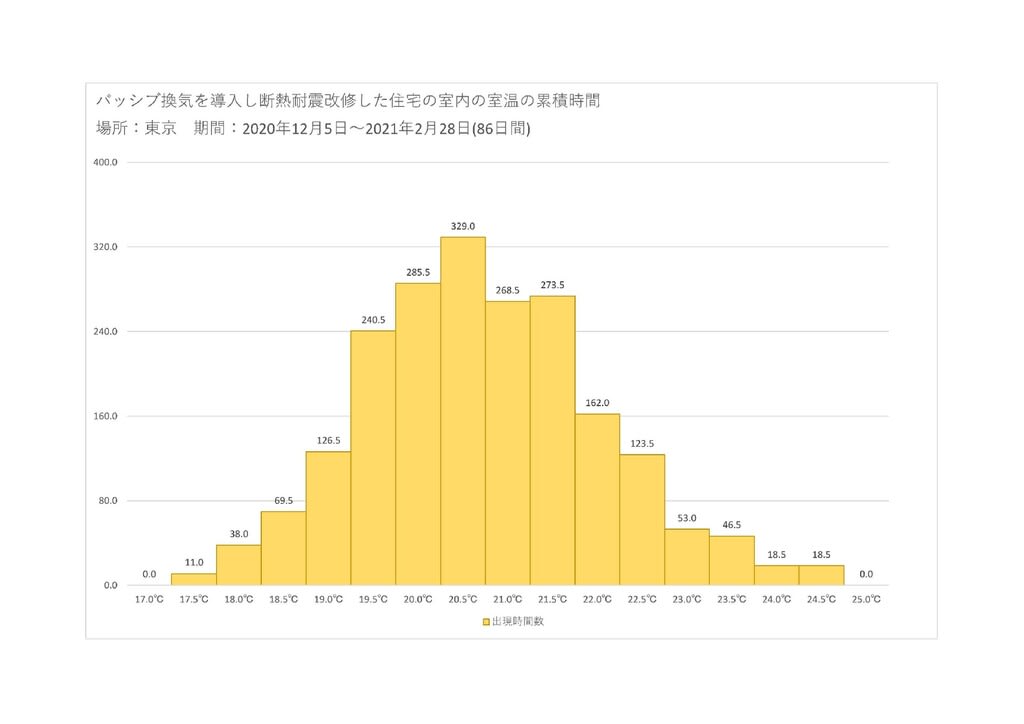断熱耐震改修したお客さんの家に追加工事の打合せで訪問してきました。
ついでに先日受けたオンライン講習で習ったことを早速活用すべく、エアコンの吸込みと吹き出し口をケストレルで測定してきました。
あいにくの曇り空で外気温も21℃程度と除湿には不利な条件(?)で、
給気口のすぐそばの空気は21.2℃-87.6%(≒14g/kgDA)
吸い込み口まわりの空気は21.3℃-86.6%(≒14g/kgDA)
吹き出し空気は12.7℃-97.6%(≒9g/kgDA)でした。
エアコン吹き出し口からの気流の風速は2m/s程度だったので、エアコンからの吹き出し風量は340㎥/h程度と概算しました。
空気線図で見るとエアコン入り口、出口の空気の比エンタルピの差は19kJ/kgDA
上記のデータを用いてエアコンの働きぶりを以下のように計算しました。
340㎥/h÷0.83㎥/kgDA≒410kgDA/h
19kJ/kgDA×410kgDA/h=7,790kJ/h
7,790kJ/h≒2,160W
容量2.2kWのエアコンなので、ほぼ能力一杯に働いてくれているということかと思います。
消費電力は200W程度だったのでCOP2160/200=10.8
→条件によると思いますが、こんなにこのCOPが高くなることがあるんですかね。
このエアコンが置いてあるのは2階の納戸で、1階の居間は23℃-60%(≒10.65g/kgDA)でした。
2階の納戸と1階の居間の間には扉はありませんが、吹き抜けのような大空間でつながっているわけではありません。
梅雨時期もエアコンの配置と運転方法で、全館空調等特殊な方法を用いなくても家全体の絶対湿度を抑えらていると思います。
もう少し調整してより絶対湿度が下げられないか工夫してみます。
ついでに先日受けたオンライン講習で習ったことを早速活用すべく、エアコンの吸込みと吹き出し口をケストレルで測定してきました。
あいにくの曇り空で外気温も21℃程度と除湿には不利な条件(?)で、
給気口のすぐそばの空気は21.2℃-87.6%(≒14g/kgDA)
吸い込み口まわりの空気は21.3℃-86.6%(≒14g/kgDA)
吹き出し空気は12.7℃-97.6%(≒9g/kgDA)でした。
エアコン吹き出し口からの気流の風速は2m/s程度だったので、エアコンからの吹き出し風量は340㎥/h程度と概算しました。
空気線図で見るとエアコン入り口、出口の空気の比エンタルピの差は19kJ/kgDA
上記のデータを用いてエアコンの働きぶりを以下のように計算しました。
340㎥/h÷0.83㎥/kgDA≒410kgDA/h
19kJ/kgDA×410kgDA/h=7,790kJ/h
7,790kJ/h≒2,160W
容量2.2kWのエアコンなので、ほぼ能力一杯に働いてくれているということかと思います。
消費電力は200W程度だったのでCOP2160/200=10.8
→条件によると思いますが、こんなにこのCOPが高くなることがあるんですかね。
このエアコンが置いてあるのは2階の納戸で、1階の居間は23℃-60%(≒10.65g/kgDA)でした。
2階の納戸と1階の居間の間には扉はありませんが、吹き抜けのような大空間でつながっているわけではありません。
梅雨時期もエアコンの配置と運転方法で、全館空調等特殊な方法を用いなくても家全体の絶対湿度を抑えらていると思います。
もう少し調整してより絶対湿度が下げられないか工夫してみます。