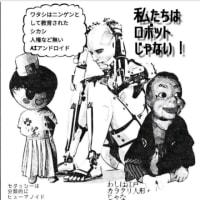昨夜も当店では面白い話で盛り上がった。
前来店時にポルトガル演歌「ファド」を即興で披露してくれたマチャコ様がダンナ様を連れて来店してくれた。
その前に呑みに来てたオヤジ(自称68歳)とカウンターでの会話、偶然3人ともキューバに行ったことがあり、むつごろうオーナーも最近キューバ旅行に行って、チエ・ゲバラの顔の土産が店に飾ってあったので、キューバの音楽や政治の話に、もってこう!と思った円ジョイマスター。
失敗しました(笑)
何故か、吉原遊郭の話に発展したヨ
マチャコ様はファドやキューバ音楽、ダンスだけでなく、吉原や花魁にも強い興味があるようだ。
そして、そのオヤジは千束(旧吉原)で女郎屋のせがれだった。(花魁行列の子役にも参加)
まあ円ジョイも古典落語の研鑽に吉原には足シゲに通ったから(笑)現在のソープランド街の様子から江戸風俗を想像しています。
吉原の概観を知るには立川談志師匠の「二階ぞめき」が適当かと思われるので紹介します。
これは藤浦 敦氏が談志師匠に提供した「ご贔屓 二階ぞめき吉原素見記」という作品から抜粋。
吉原の張見世と申しますのは、花魁が、格子を通しまして表通りに面した部屋にずらりと並びます。
これをお客が格子越しに見立てまして今夜の相方をきめようという、まことに結構なもので。
この客と花魁との間に掛ります格子を小格子、またの名を、ちょんちょん格子と申しますが、女はここの格子の間から長い煙管を差し出しまして外のお客にたばこを振る舞う。俗にいう吸付けた
何処へ行ってももてるお客はあっちからもこっちからも吸付けたばこ。「こりゃ、妙だ。今夜は月夜
というに、煙管の雨が降るようだ...」実に、羨ましい気分でござんすな。
この張見世がございましたのは吉原でも格式の低い小見世に限ったもので、三浦屋、角海老、大文字
などと申します大どころは、これを大まがきと申しまして花魁は見世へは出ません。
此処は引手茶屋を通しませんと、登楼れない仕組みになっております。
日が暮れますと吉原へ行きの、ひと廻り、冷かしをしませんと寝られない、なんという厄介な連中
が多かったようで、これを素見と申します。
「素見ぞめきは椋鳥の群れつつ、きつつ格子先」
吉原へは舟と駕籠と行き方が二通りあるね(馬禁止)
先ずは舟といきやしょう。神田川は柳橋辺の船宿から猪牙を仕立てる、この猪牙てえものは明歴の昔
玉屋勘五兵衛と笹屋利兵衛が拵えたのが始まりだ。舟の造りが細長くって華奢に出来てるから舟足
が早い代り、乗るのが難しい。下手をすると客の体がつんのめったりひっくり返ったりする。
「猪牙で小便千両も捨てた奴」
漕いでる猪牙から小便が出来るぐらい乗り慣れるには吉原通いの古強者、千両ほども遊びに使った男
でなければこの真似は出来ない。始めての奴はその速さに恐れをなして
「手を突いて猪牙に乗ってる恥ずかしさ」なんという具合になる。
つまり吉原は、大奥とは別の女の園で、大奥の落語の噺は一切ないので、庶民には一切知られてなく風刺にもならなかったんだ、でもお上も認めた廓で、地方大名もやってくる場所だったのヨ
でも花魁、太夫の地位は高く、花魁が、馬糞の匂いが嫌いと言えば、大名も豪商も馬では吉原に来れナかったし、いくら金を積んでも、花魁に嫌われたら相手されない文化だったのさ
だから吉原はステータスも高く、現代と同じ結婚できない独身が6.70パーセントの江戸時代においては、花魁を抱くことは夢のまた夢、憧れだったのヨ
ただ古典落語は、呑む、打つ、買うの野郎バナシ
是非、花魁女子目線の廓話を演る落語家出て来ないカナとおもうネ
マンガの「さくらん」を原作にしてもイイネ
前来店時にポルトガル演歌「ファド」を即興で披露してくれたマチャコ様がダンナ様を連れて来店してくれた。
その前に呑みに来てたオヤジ(自称68歳)とカウンターでの会話、偶然3人ともキューバに行ったことがあり、むつごろうオーナーも最近キューバ旅行に行って、チエ・ゲバラの顔の土産が店に飾ってあったので、キューバの音楽や政治の話に、もってこう!と思った円ジョイマスター。
失敗しました(笑)
何故か、吉原遊郭の話に発展したヨ
マチャコ様はファドやキューバ音楽、ダンスだけでなく、吉原や花魁にも強い興味があるようだ。
そして、そのオヤジは千束(旧吉原)で女郎屋のせがれだった。(花魁行列の子役にも参加)
まあ円ジョイも古典落語の研鑽に吉原には足シゲに通ったから(笑)現在のソープランド街の様子から江戸風俗を想像しています。
吉原の概観を知るには立川談志師匠の「二階ぞめき」が適当かと思われるので紹介します。
これは藤浦 敦氏が談志師匠に提供した「ご贔屓 二階ぞめき吉原素見記」という作品から抜粋。
吉原の張見世と申しますのは、花魁が、格子を通しまして表通りに面した部屋にずらりと並びます。
これをお客が格子越しに見立てまして今夜の相方をきめようという、まことに結構なもので。
この客と花魁との間に掛ります格子を小格子、またの名を、ちょんちょん格子と申しますが、女はここの格子の間から長い煙管を差し出しまして外のお客にたばこを振る舞う。俗にいう吸付けた
何処へ行ってももてるお客はあっちからもこっちからも吸付けたばこ。「こりゃ、妙だ。今夜は月夜
というに、煙管の雨が降るようだ...」実に、羨ましい気分でござんすな。
この張見世がございましたのは吉原でも格式の低い小見世に限ったもので、三浦屋、角海老、大文字
などと申します大どころは、これを大まがきと申しまして花魁は見世へは出ません。
此処は引手茶屋を通しませんと、登楼れない仕組みになっております。
日が暮れますと吉原へ行きの、ひと廻り、冷かしをしませんと寝られない、なんという厄介な連中
が多かったようで、これを素見と申します。
「素見ぞめきは椋鳥の群れつつ、きつつ格子先」
吉原へは舟と駕籠と行き方が二通りあるね(馬禁止)
先ずは舟といきやしょう。神田川は柳橋辺の船宿から猪牙を仕立てる、この猪牙てえものは明歴の昔
玉屋勘五兵衛と笹屋利兵衛が拵えたのが始まりだ。舟の造りが細長くって華奢に出来てるから舟足
が早い代り、乗るのが難しい。下手をすると客の体がつんのめったりひっくり返ったりする。
「猪牙で小便千両も捨てた奴」
漕いでる猪牙から小便が出来るぐらい乗り慣れるには吉原通いの古強者、千両ほども遊びに使った男
でなければこの真似は出来ない。始めての奴はその速さに恐れをなして
「手を突いて猪牙に乗ってる恥ずかしさ」なんという具合になる。
つまり吉原は、大奥とは別の女の園で、大奥の落語の噺は一切ないので、庶民には一切知られてなく風刺にもならなかったんだ、でもお上も認めた廓で、地方大名もやってくる場所だったのヨ
でも花魁、太夫の地位は高く、花魁が、馬糞の匂いが嫌いと言えば、大名も豪商も馬では吉原に来れナかったし、いくら金を積んでも、花魁に嫌われたら相手されない文化だったのさ
だから吉原はステータスも高く、現代と同じ結婚できない独身が6.70パーセントの江戸時代においては、花魁を抱くことは夢のまた夢、憧れだったのヨ
ただ古典落語は、呑む、打つ、買うの野郎バナシ
是非、花魁女子目線の廓話を演る落語家出て来ないカナとおもうネ
マンガの「さくらん」を原作にしてもイイネ