小中高といずれもコスモタイガーの最大の得意科目は「社会科」。
特に地理、次が歴史。
小学校の5年だったか6年だったか、クラスで成績1番の秀才M君も、社会科のテストだけは、コスモタイガーに手も足も出せなかった(笑)。
そりゃそうだよね、小さいころから時刻表ばっかり見てたから(爆)。
さらに遡って小学校3年か4年の授業参観。
社会の授業で、黒板に大きな日本地図が掲げられ、「都市の名前を言うから、正確な位置を示しなさい。自信のある人!」なんて言うから「かーんたん!」なんて言いながら自信満々で挙手。
最初の2問は政令指定都市で、問題なく正解した気がするが、生意気なガキとでも思われたんだろう、先生もいたずらで少しマイナーな?都市を言い始めた。
「明石!」
なんだ、新幹線に西明石駅があるじゃん、はい、ここ!
「高崎!」
なんだ、群馬県の大きな街じゃん、高崎線もあるし、はい、ここ!
ということで全問正解。
不思議と今も覚えてる光景だ。
勉強してると、教科書が基本!なんて良く云われたけど、もちろんそれも正解だとは思うけど、コスモタイガーの場合、社会科に限っては「時刻表」が教科書みたいなもの。(笑)
鉄道路線網を中心に地名がびっしりと書き込まれ、日本の地図が自然と頭に叩き込まれる。
時刻表オタク・鉄道ファンが全国にどれだけいるか知らないけれど、「鉄道だけ異常に詳しく、地理はさっぱり」というケースはほとんどないだろうと思う。
青森県の産業は~、なんて授業聞いてても、青森県の場所すらわかってなければ聞いてても面白くないだろうし。
「太平洋ベルト地帯」と聞けば、東京名古屋大阪に繋がる工業地帯。
新幹線があるから移動に便利だよね、と子供ながらにすぐに鉄道と結びつけて考えることができた。
いわゆる丸暗記じゃなく、「なぜ?」と疑問に思いつつ、好きな鉄道といろいろ関連付けて覚えていくから面白いよね。
歴史も同じ。
年号と事実だけをひたすら丸暗記すれば、受験対策や偏差値稼ぎとしてはOKなんだろうけれど、それじゃ面白くも何ともない。
ちょっと乱暴な言い方をすれば、ただ「記憶力」の訓練をしているだけだ。
関ヶ原の合戦とか長篠の合戦なんて名前はわかってても、それが日本のどこで起きたのか?なぜその場所なのか?なぜ戦いが起きたのか?が理解できてないと、歴史の楽しさなんて全く感じないだろう。
歴史こそ、「点」じゃなく、「線」で理解する学問だもんね。
(関ヶ原の合戦については、さわりだけ、旧中山道編6、7参照してね♪)
源平の合戦で活躍した、木曽義仲や源義経と、平家軍との戦い。
倶利伽羅峠とか、屋島とか壇ノ浦といった地名が絶対に出てくるけど、それぞれの場所、ちゃんと時刻表巻頭地図に載ってるからね、頭の中にスッと出てくるし。
羽柴(豊臣)秀吉の備中高松城の水攻めからの中国大返し。
ここから明智光秀と戦う山崎の合戦までの距離感とかが咄嗟に判るから、自然と歴史も得意になる。
地理も歴史も共通にして最大に重要なのは、「位置関係」を把握すること、かな。
時刻表オタクや鉄チャンは、この位置関係を把握する能力が抜群に長けてるからね、だから両方得意な方が多いと思う。
コスモタイガーの感覚では、地理と歴史は相乗効果とでも云えばいいのか?
一緒に連動してるイメージだから、この2つを分けるなんて、とてもナンセンスな気がする。
「漂走記」の中でも書いたと思うけれど、鉄道と旧街道の関係もそうだ。
あえて分類するならば、鉄道は「地理」に属し、旧街道は「歴史」に属すると思うけれど。
人が集まれば集落となり、集落と集落を行き来したり物資を運んだりするために道ができる。
主要な道は街道となり、さらに人が集まり、宿場もできる。
時代とともに、今度は物資をより早く運ぶため、より多くの人を運ぶために鉄道ができる。
街道沿いに鉄道が発展するのは必然であり、鉄道の敷設とともに産業がますます発展する。
その町の歴史の積み重ねがあって現在(地理)があるわけで、地理と歴史を別々に学ぶということ自体、疑問に思ったりしたものだ。
例えば地理のテストで、「長野県の特産を1つ上げろ」、と出題されたら、「りんご」と回答すれば○。
丸暗記の試験ならこれで終了。
でも、なぜりんご?と思い始めると面白い。
遡って調べてみると、ここ信濃の国はかつて養蚕が盛んだったことがわかる。
でも第2次大戦後の高度経済成長により、日本の産業構造は大きく変わり、繊維工業が衰え、重化学工業中心に。
だから養蚕では飯が食えなくなって、多くの農家がりんごに転換したんだね。
じゃ、そもそも養蚕はなぜ始まったの?
これも調べる。
もちろんいろんな理由があるんだろうけど、一言で無理矢理おさめれば、初代松代藩主、真田信之公が、養蚕を奨励したってことかな。
浅間山の麓。
火山灰が多い痩せた土地で、稲作には不向きだったんだよね。
それを知って養蚕を奨励したってわけね。
真田信之。
昨年の大河ドラマ「真田丸」の主人公、真田幸村のお兄さん。
大泉洋さんが好演してた、あの信之ね。
「真田丸」は夏の陣で幸村が華々しく散るところで終わっちゃうけれど(主人公が幸村だから当たり前だけど…)、その大坂夏の陣終了後、兄信之は徳川家康の論功行賞により、上田10万石から松代13万石に加増。
もっとも「加増」とは名目で、肥沃な上田から、火山灰だらけ?の松代(現長野市松代地区)への転封は、実質的には大減収だったとも言われている。
豊臣方についた弟の幸村の活躍が強烈に怖かったってことだね。
家康からすれば、この際、胡散臭い?真田にはなるべく遠くに行って欲しかったってのが本音なんでしょう。
(確かに江戸からだと、上田より松代の方が遠く、主要路線・主要街道からも外れてるってことも、普段から時刻表見てればすぐわかります、はい。)
信之もそんな仕打ちにめげず、松代の土地に合う養蚕を奨励し、徐々に松代藩を立て直していったんだね。
信之が亡くなった際には、かなりの備蓄があり、のちの真田家を随分と助けることとなった。
そんな真田家は、江戸中期に「真田騒動」という内紛も経験、恩田木工民親という名家老を輩出しつつ、その後も幕末の混乱期を無事すり抜け、現在も連綿と続いている。
って長くなっちゃったけど、地理で「長野=りんご」というだけで、「なぜ?」「なぜ?」を繰り返していけば、ここまで歴史は広がるのだ。
別の言い方をすれば、どこまでが地理でどこまでが歴史なのかも曖昧な感覚。
にも関わらず、高校になってから、いつしか「地理」と「歴史」は別物として扱われ、どちらかを選択しろ!と。
コスモタイガーの中では「そんな殺生な…。繋がってるのに…」という感じ。
まぁそれでも、「地理」の方がやや得意だったし、主戦場(時刻表♪)に近いと云う妙な意地があって、「地理」を選択したものの、片肺飛行を強いられた気分はずーっと続いた。
受験戦争から随分と月日がたち、大人になってから、学校によっては、或いは年代によっては「地理歴史」と1つの科目として扱われていたという話も聞いたけれど、羨ましい限り。
お世辞にも優等生ではなかった上、理数系が大の苦手だったコスモタイガーにとって、地理歴史はそれをカバーする圧倒的な得点源だっただけに、両方で勝負できたら、もう少しマシな結果になったかもしれないなぁ。
もっとも自分も年を取って丸くなった?のか、別の角度で考えてみたりすると、理系人間からすると、「物理と化学を分けるのはおかしい!」なんて突っ込みも入りそうだし。
それより何より、大人になって「知りたい!」と思ったことは凄く身についているけれど、受験のために学んだ知識なんて、この年齢になると全くと言っていいほど役に立ってない。
それこそ勉強が全てじゃない。
今となってはどうでもいい話なんだけどね。










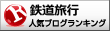
















私が唯一読んでいる人生相談欄が、週刊文春の伊集院静の「悩むが花」です。
先日、この欄への”定年後は何をテーマに生きていったら良いのでしょうか?”という相談への回答が下記でした。
小学校の高学年の頃に最も興味を持った事、やりたかった事が何か、を思い出して、定年後の人生はそれをテーマに生きると良い、とあったのを思い出しました。
コスモタイガーさんの小学校の高学年の頃の得意科目の話しとダブりました。
それなら私は小学生の心のまま、40代を送ってることになります(笑)。
ピュアな心を持った人間、ということにしといてください。(爆)
地理はある場所の「現在」を学び、歴史はそこに至るまでの「過去」を学ぶようなものでしょうか。
でもいろんな過去があっての現在なわけで、過去と現在を分けて学びなさい、と云われてるようなもの。
こんな理不尽な話はありません。
というより、地理(現在)の時間に地理の先生が、歴史(過去)の時間に歴史の先生が、それぞれバラバラに講義をするため、「かえって話をややこしくしてないか?」とすら思ったこともありました。
私が60代になる頃に定年が何歳になってるのか、あと少子化の影響もあり、年金がちゃんといただけるのか?などと現実的な話もあったりしますが、地理や歴史への好奇心だけは生涯続きそうです。
> 歴史こそ、「点」じゃなく、「線」で理解する学問だもんね。
歴史版「点と線」ですね。
iinaが『もののはじめ』を冠するのは、
数でリズムをとりながら日本古代史にこだわって、「もののはじめ」をまとめました。
「 縦軸に数! 横軸に古代史! 」 です。
http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/9560cda38e79a714ab38d2123ff0756b