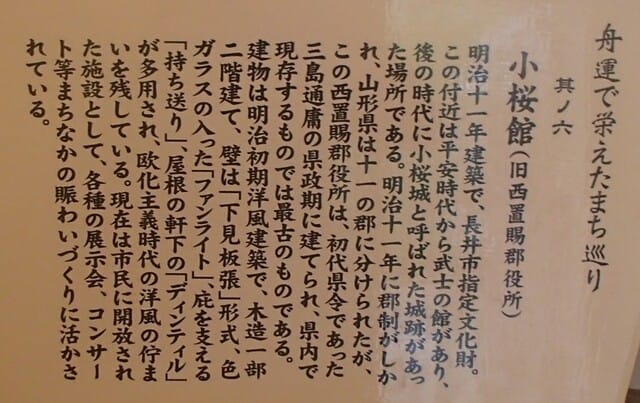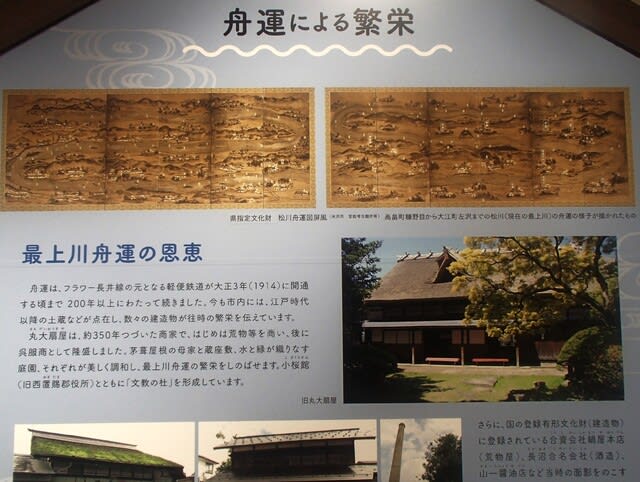日本は知識経済化ーイノベーティブ福祉国家へ トランプ・IT長者のフェイクファシズムに抗して
慶応大学名誉教授 金子勝さんに聞く
2025/2/8 [現代の理論] 第40号 DIGITAL─2025冬号 VOL.40 特集 混迷の世界をどう視る
3.アベノミクスの失敗は未だに日本の経済・社会を停滞させている
さて、問題は日本です。ここから日本の話です。
非常に厳しいのはアベノミクスを未だに総括できていないこと。明らかに失敗しているのに、まだアベノミクスに乗って減税、減税と言っています。減税はいいとして、本当の争点は、赤字国債依存の減税なのか、それともお金持ちや企業から税を取って所得再分配的な税制改革をするのかということです。そこを忘れて、アベノミクス残党と一緒になって、減税派か増税派かという敵・友概念を使うフェイクファシズムに紙一重になってきています。
日銀は円安とインフレの進行の下で、0.25パーセント金利を上げました。今は短期金利が0.5%ですが、1%まで上げるとしています。そうすると、長期金利も2%くらいに上がり、今後じわじわ国債利払い費が上がってくる。財務省は2028年に現在の倍以上の16.1兆円まで上がると試算しています。やらざるを得ないとは思いますが、それで持つのか。だからといって、この状況の中、アベノミクスで財政赤字を膨らまして金融緩和を続ける限り、円安、インフレは止まりません。今年直面するのは、利上げはやらざるを得ないだろうが、より問題なのは金融緩和を縮小するかどうかです。
前述のように、年初に日銀は0.25パーセントの短期金利の引上げをやった。同時に、2024年7月末に、25年度に金融緩和の量、国債の買入れ量を半減させると宣言していますが、石破政権は115兆円の巨大な予算を組んでいる。これは、インフレ課税路線です。インフレにすると民間の金融資産はその分目減りする一方で財政赤字も目減りして行きます。庶民は生活が苦しくなるが、税率を上げなくても所得税や消費税は増える。円安であれば法人税も上がってくる。実際に、対GDP比で見る財政赤字は減少傾向になっています。それを当てにしている今の財務省と、円安インフレを抑えるべき立場の日銀とは全く矛盾しています。
先に述べたように、トランプの政策がインフレ的で、思うほどに利下げしてドル安を誘導できそうもないので、日銀は金融緩和をやめたい。インフレを正常化したい。しかし政府は、議席が過半数割れなのでばらまきをやりたい。これが真っ向対立している状態です。もし2024年7月末の金融政策決定会合で決めた通りに日銀が金融緩和を半減させる方針を真面目に実行する、つまり月間買取量を6兆円から3兆円に変えると、日銀が引受けない国債が60兆円は市中に出てくるはずです。
すでに国債残高のうち銀行保有は12%ほどでしかない。その理由は、金融緩和でどんどん銀行の国債が買い取られたことが一つと、日本の国債はゼロ金利だったのでうま味がないため、円安を誘導しながら、海外に投資して儲けるやり方をやっていたことです。そこに60兆円の国債を日銀が買い取らないで市中に出したら、とても吸収できない。すると国債は売られ、金利が暴れながら上がるでしょう。結局それはできないから、3月に予算案を通すために日銀が国債を買い取らざるを得ないという中途半端な状態がやってくる可能性が高い。
一方、国民民主党と妥協するために金持ち減税をやる。「103万円の壁」というのはほとんど嘘で、すでに存在していません。かつては配偶者控除を適用できる上限で103万円が壁だったのですが、すでに2017年に配偶者特別控除が設けられており、150万円を超えて控除がなだらかに減少する仕組みになっています。さらに、基礎控除を上げると累進税率だから金持ち減税になります。政府試算でも、年収210万円ぐらいの人は9万円ぐらいしか減税がなくて、年収500万円で約13万円、2300万円で38万円となります。さらに日本の所得税は、1億円超えたら金融所得が多くて税率が下がっていく金持ち優遇の仕組みです。
欧米諸国では給付付き税額控除という仕組みがあります。たとえば、500万円以下の所得層に限定して、支払う税額から一律10万円の税金支払い額を差し引くのです。低所得層には減税で足りない分を給付で補足します。これだと、所得が低いほど、減税額が多くなります。金持ち優遇の所得税をそのまま減税するのに7兆円も出すという話はどう見てもおかしい。しかも、赤字国債でやったら、結局円安、インフレに戻ってしまい、なんの効果もない。
SNSしか見ていない人たちはフェイク減税をそのまま信じている。そして国民民主は支持率を保つために嘘を通そうとするわけです。115兆円の巨大・史上最大の予算がさらに膨らむ可能性がある。そうすると、日銀の利上げと金融緩和の縮小という政策は維持できない。そういう矛盾が3月にまずはっきり出てくる。6~7月も同じで、都議選と参議院選でとにかく補正予算を組みたい、なんらかの形でばらまきをやりたいというのが多分石破政権の政策だと思います。方向感が全くない。
もっと言うと、アベノミクスの総括をきちんとしなかったことのツケが今一気に出てきています。アベノミクスはなぜ間違いかと言えば、2点はっきりした理由がある。
一つは、デフレ脱却と言いながら、それが8年以上にわたってできなかったのに、新型コロナウィルスの世界的流行とロシアのウクライナ侵略を契機に、世界中でインフレになって、外からインフレがやってきて、抜けるに抜けられない状態に入ったことです。あまりに大量の国債を日銀が買い続け、発行し続けたという状態で、「出口のないネズミ講」状態に入った。庶民がインフレで苦しんでいるのに、デフレ脱却のためのアベノミクスを続けるという。インフレになるのは当たり前という巨大予算を組んで、かつ日銀が金融緩和を続けていけばどうにもならない。それがまず第1点。
食品の値上げが激しく、エンゲル係数が上がっているわけです。非正規雇用の人の割合は4割で、高齢者や女性が増えているのはあるけれど、雇用の中身はそう変わってないのにエンゲル係数だけが急激に上がっているから、要するに所得の低い人たちは食費の支出が非常に増えているという問題に直面している。法人税減税を元に戻して財源的に対応できるのは食品ゼロ税率でしょうか。ところが、赤字国債依存で減税をやって、例えばれいわ新選組が言うように消費税を全廃したら、地方消費税も含めて30兆円がなくなる。円と日本国債は投げ売りです。2022年4月以降、消費者物価上昇率が2%を超え続けており、まともな学者はリフレ派や日本版MMTから離れています。今もアベノミクスの失敗を認めず、ポピュリズムに頼って、財源を言わずに30兆円以上歳入欠陥でも減税を先行してやると平気で言っていますが、とても正気とは思えません。
4.根本問題は日本の経済・産業の大衰退
アベノミクスのもう一つの問題は、根本的に日本経済が衰退していることです。
かつて民主党政権が「コンクリートから人へ」と提起した。間違いが多かったけれども、コンクリートから人へと、教育を無償化しながら、既存の重化学工業中心の土建国家のありようを変えていこうとして、北欧諸国を中心とした知識経済化の流れ――とくに神野直彦さんなどが言っていました――を進めようとしていたわけです。ところが、アベノミクスはそれを全部投げ捨てて「3本の矢」だと言って、既存のミクロ経済学、マクロ経済学の破綻した路線、つまり財政赤字と規制緩和を目一杯やってみようとした。風邪ではなくて肺炎になっているのに、風邪薬が効かないなら風邪薬一瓶飲めば治る式の「処方箋」です。
結果起きたことは、産業の衰退は深刻で、当然にも貿易赤字が定着しました。実質賃金は低下し続け、1人当たりGDPはIMFの2023年統計によれば34位で、31位の韓国にも抜かれてどんどん落ちています。子供が生まれない状態になって人口減少が急激になっているのが今起きている結果です。アベノミクスの失敗を本格的に総括するのが何よりも最初に必要です。

貿易赤字の推移
なぜ日本経済はこんなに衰退してしまったのか。イノベーティブ福祉国家という考え方がポイントだと思います。北欧諸国を見ると、明らかに1990年代に日本との分かれ目があった。
90年代、バブルが崩壊した後にフィンランドとスウェーデンは銀行を全部国有化して、不良債権を切り分けて再民営化した。多額の公的資金を入れた。そしてイノベーションを猛烈に進めていったのです。その際に、知識経済化のために、教育の重要性を強調し、教育の無償化などを進めた。
また、高福祉高負担で有名な福祉国家ですが、現金給付中心はやめていくのです。そこだけ見ると福祉が減っているように見える。実際は、医療や介護、教育などの対人社会サービスに力点を入れて雇用を増やして賃金を上げていきました。つまり、知識経済化して先端産業を作り、その結果経済が成長して貿易収支が改善し、ロシアに依存していた貿易構造が変わって、EU側に向かう先端産業に転換していくことが起き始めたわけです。
先端企業の名前を挙げると、デンマークでは有名な風力発電会社のヴェスタスや製薬会社のノボルディスク(肥満防止の薬)とルンドベック、フィンランドはノキア、スウェーデンはエリクソンです。新しい先端産業をどんどん作り出していくという点で大きな変化があって、製造業も農業もIT化して、就業人口が減りながらもITを中心にサービス産業が増えてきた。そして福祉、医療、介護など対人社会サービスの雇用が大きく増え、教育関係や研究職に就く人たちが急激に増えていくようになった。

高齢者の非正規雇用の増加
日本の場合は、アベノミクスで雇用が増えたかのように言われますが、間違いです。実際は人口の塊がいる団塊の世代(1947年から51年生まれの世代)がリタイアするに従って人手不足になっているのです。2012年以降、高齢者の臨時雇用が増えています。2013年から団塊の世代が65歳を超え、皆定年退職して非正規になっているわけです。2017年に70歳を超えて、また高齢者非正規がもう一段増えていきます。2023年以降の人手不足は、団塊の世代が皆後期高齢者になって、どんどん労働市場から退出しているからです。若い人の非正規雇用がそんなに増えないのは、団塊の層の人が辞めた後に正社員になることがあるからです。人手不足になるのは景気がいいからではなく、団塊の世代の引退で労働市場の中のマスが動き、年齢構成が変わったから。非正規の比率は全然変わっていないし、先端産業はどうしようもなく遅れています。

デジタル赤字5.5兆円→6兆円へ
デジタル赤字が2024年には6兆円を超えると言われています。2023年が5.5兆円だったので、どんどん増えている。スマホを使う度にアプリ使用料や広告料を我々が払ってアメリカへ流れている。バカげた構図が生まれています。
薬の分野でも、ヒトゲノムを読んで、ゲノム医療、ゲノム創薬、ゲノム診断と大きく変化して、劇的に治す薬ができています。ゲノムで癌を診断し、それに対応した薬を複数使うことによって、癌の治りが非常に良くなるということで、劇的な変化が起きています。が、日本の製薬メーカーは低分子薬作りで成功しましたが、ヒトゲノムで薬を作るのに失敗した。コロナの時のメッセンジャーRNAワクチンがその例ですが、ファイザーなどの製薬会社は膨大な投資をしています。
車の自動運転は、テスラも失敗するだろうとは思いますが、Googleはうまくいき始めている。これは軍事技術です。地図認識や自動運転など無人兵器の技術で、Googleはそういう面を持つ企業です。日本は電気自動車と自動運転という点でも大きく負け始めています。その象徴が日産とホンダの経営統合でしょう。日産も三菱も電気自動車に取り組んだのが早かった。ところが、中国市場で全然勝てなくなった。多分、車のコンセプトが違うのです。ある意味でBYDなど中国では、ITの端末として自動車を作っている。4輪にモーターを付けただけという自動車は、電気自動車として対応できなくなっている。ITの力が全然違う。日本はダメです。その中国は自動運転も相当進んでいる。そういう意味では、日本は本当に非常に厳しい。
情報通信は世界ではクラウドが当たり前になっているのに、日本ではオンプレミスで、企業や病院ごとにサーバーを売りつけて、そこでソフトを動かすという時代遅れのやり方がずっと続いているため、どんどん競争力が落ちている。それを救済する事業がマイナ保険証です。今どき4桁の番号のプラスチックカードです。全く信じがたい状態です。