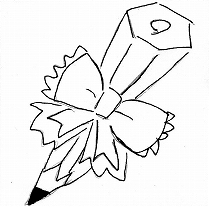本文詳細↓
「……なら、アダムが僕と一緒にいてくれたのは、僕がその『英雄』だと思ったからか?」
ぐっと握る手にさらに力がこもった。爪が食い込んでいるのが分かる。きっとくっきり痕が残っているだろう。
「さて、それはおぬしが決めることだ」
「ぐっ!」
いきなり後頭部を蹴りつけられて、固い甲板とぶつかった額がジンジンと痛んだ。何をするんだと、抗議するためほぼ反射的に顔を上げて、僕は初めてアダムと同じ高さで顔を突き合わせた。
「おぬしが英雄になるというのであれば、今も言った通り手助けしてやろう。だが逆を選んだからといって、べつにおぬしに失望したりはせぬ。我は存外、トルヴェール・アルシャラールという男を気に入っているのでな。それこそ、おぬしが我を釣り上げ、母上殿が作った握り飯を譲ってくれたときからな」
そこで持ってくるエピソードがそれか。なんだかとてもアダムらしくて、少し肩の力が抜けた。
「お前、それ自分が餌付けされただけだって言ってるようなもんだけど、いいのか?」
「美味いは正義だからかまわぬ!」
久しぶりに声に出して笑って、僕は体を起こした。
「僕は、英雄にはなりません」