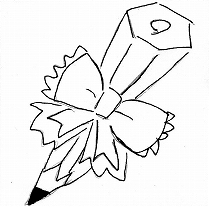答えは、『古今和歌集が時の天皇・醍醐天皇に奏上された日』です。905年5月21日(旧暦では延喜5年4月18日)のことでした。ちなみに延喜5年4月15日だとする説もあるそうですが、そうするとこのブログのネタに困るので21日でお願いしますm(_ _)m
現存する日本最古の和歌集は、万葉集(750年前後ぐらい成立)です。この万葉集以後の時代を「古」、撰者の時代を「今」として、「万葉集に入らなかった古い歌と、選者たちの新しい歌を中心とした歌集」という意味で『古今和歌集』と名付けられたそうです。
醍醐天皇から最初の勅撰和歌集を作れと命じられたのは、紀友則、紀貫之、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね)の時代を代表する歌人たち。と言っても、古典や歴史の授業で習うときに出てくる名前はだいたい紀貫之ぐらいでしょう。後ろ二人なんて、初見一発読み方を当てるの難しくないですか? これを書くために久しぶりに高校時代の便覧を引っ張り出してきましたが、これを見るまで聞いたことありませんでしたし。
その中身は季節の歌やら恋の歌が整然と主題別に並べられていて、この構成は後に作られる他の勅撰和歌集の模範とされたそうです。
ちなみに『刀剣乱舞ONLINE』には、この古今和歌集から名をとった『古今伝授の太刀』という名前の刀がつい先日実装されました。

私なんかは変な名前の刀やなあと思ったわけですが、どうやら「戦国時代の武将・細川幽斎から烏丸光広へ古今伝授がなされた際、共に渡されたことが名の由来」だそうです。ではこの古今伝授が何かというと、「古今和歌集の解釈や関連分野に関する学説を師から弟子へ秘密裏に伝えていくこと」だそうです。ざっくりいうと。
詳しくはこちらへどうぞ。
...我ながら今日は特に、変な方向へ話が飛んでいったなあ。