そばにいた堀内貞行らは伏姫の自決を止められず、あえなくも美しい花を散らせてしまったことが残念で仕方がなかった。
そんな中に金碗大輔孝徳は、男に勝る姫君の末期の一句に奮わされて、身を置くところがなくなったのか、亡骸の近くに落ちていた血に染まった刀を拾った。そして再び腹を切ろうとする。
その時、里見義実は大きな声を出して、
「大輔よ、うろたえたか。その身に大きな罪がありながら、私の命令を待たずに自害しようとは奇妙なことをするものよ」
金碗大輔は震えた。
「伏姫が一旦蘇生したので罪を一等減じることができるが、この山に入る者は首を刎ねよと掟を定めているので、法度を曲げて私が決めるのだ。腹を切ることは許さんぞ、観念せよ」
と進んで近づき、刃を引っ提げて立った。
「願うところでございます」
金碗大輔は、居直って合掌しうなじを伸ばす間もなく、煌めく刃の稲妻。はっしと打った太刀風は、思い掛けなくも大輔の髻だけを切り捨てていた。
「これは」
と見返る罪人も、諫めることができずに呆然としていた堀内貞行も驚き、そして仁君の恩義に大いに畏まった。
里見義実は氷の様に輝く刀をいきなり鞘に納めて、堪えていた涙を振り払い、
「蔵人、見ろ。私がみずから罪人に刑罰を与えた。法度は主君の制定するところ、主君がまたそれを破るというのは昔の人の金言、もっともなことだ。私がもし皆と今日この山に登らなかったら、大輔に咎はなかった。その首に代えた髻は、大輔の亡父へのわずかながらの厚意である。幼い時から名を大輔としたのは、大国の補佐の臣になれ、と行く末を期待し、私の官職もようやく進んで治部大輔となった。読み方こそ異なるが、文字面は変わらず、主従は同名だ、だからこそ主人である私の身が受けるべき祟りをその身に受けてしまったのかもしれない」
星祭りの苦い思い出が里見義実に甦る。
「未来洋々たる若者が世の中の埋もれてしまうこと、返す返すも不憫である。親の八郎孝吉は大功があり、大輔も忠がある。親といい子といい、勲功あるが行賞を受けずに、死に臨んで罪に陥ることになっては、主人の私も助けられないなど、我が子の不幸にまして、哀傷の涙を堪えきれない」
改めて大輔をきっとにらんだ。
「良いか、大輔よ、孝徳よ。我が心を良く悟って、亡き親のため、姫のために、命を保ち、自分自身を愛し、仏に仕え苦行して高僧となって知識を蓄えよ、良いか、心得たか」
と丁寧に諭すので、金碗大輔は主人の優しさに対し、地に伏して、返答しようにも落ちる涙にむせび、声が出ない。仕方がないとばかりに、堀内貞行は鼻をかんでから進んで前に出てこう言った。
「今に始まらず、主君の仁のお心、大輔、お主の身に取っては、一郡の守護になるより、あるいは万貫の禄をいただける様になるより、満足であろう」
と言われてようやく頭をもたげ、
「私は真に不肖ではございますが、如是畜生も菩提に入りました。今より日本を回国して、霊山霊場を巡礼し、伏姫の来世を弔い、我が君ご父子の武運をお祈りします。姫上のご落命も剃髪も、みんな八房が原因でございます。犬という字を二つに割り、犬にも及ばない大輔が、大の一字をそのまま、犬の点をいただいて、ヽ大(ちゆだい)と法名にいたします」
金碗大輔がそう言うと、里見義実は叫んだ。
「良く言った。件の犬は全身に黒白の八つの斑があったから八房と名づけたが、今から思えば八房の二字は、つまり一尸八方に至るという意味だ。一尸は一人の屍。それだけではない、伏姫は亡くなる間際、傷口から白い煙がたなびき、仁義八行の文字が現れた。百八の珠が閃き、文字のない珠は地に落ちて、残りの八つは光を放ち、八方へ散ってとうとう消えてしまった。それには理由があるはずなのだ」
言い聞かせるように続けた。
「後になれば分かることもあるかもしれない。菩提の門出の餞別には、この数珠の他にはない。大事にするのだぞ、ヽ大入道」
主君が諭して幾つかの数珠を与えたので、金碗大輔は手で受けて、再三大切に額にかざすのだった。
「これはありがたき我が君の賜物、今から諸国を遍歴して、飛び去った八つの珠の落ちたところを尋ね求めます。元の様に数珠を繋ぎ、百八の数に満たなければ、安房に帰りませんし、お会いいたしません。何年かたっても音沙汰なければ、旅から旅の野ざらしになり、亡骸は飢えた犬の腹を肥やしているとお思い下さい。今日こそ今生のお別れでございます」
と決心して返答した。
すでにこの時日は暮れて、夜は早くも初更(午後七時ごろ)を回っていた。
しかし昼よりもなお明るい月には雲もなく、山にはたくさんの木々の影があった。激しく流れる水の音、強く吹き松を揺らす風の声は、断腸の思いを一層悲しくさせた。更に鹿は山の上で鳴き、白露が霜となっていく寂しさ。猿は深山幽谷に叫び、孤独の旅の宿を寒くさせていく。
滅多に来たこともない者でも訪れれば寂しく感じる深山幽谷である。こんな山奥で、ただ独り心強くも菩提に努めた伏姫のことを考えると、里見の主従はしきりに嘆いた。
堀内貞行は金碗大輔と話していた。
「姫上の自決で思わぬ時間が掛かってしまった。日は暮れてしまい、山道は険しく、下山は不安である。しかし夜をここで明かすのであれば、姫上の亡骸をいかがいたそうか。毒蛇や猛獣の心配がないとは言えないぞ。進退は困難だが、お主はどう思う」
と問われて、しばらく考えていたが、金碗大輔は、
「おっしゃることはごもっともでございます。ここで夜を明かすことは配慮がないと言えます。あなた様と私で姫の亡骸をお運びし、我が君にはみずから松明をお持ちいただき、急いで下山いただきましょう。麓にはお供の人々がいる、と承っておりますので、お迎えに参ることでしょう。例え迎えの者たちが怖がって谷川を渡らなくても、向こう岸から会うことができます。この手段はいかがでしょう」
と語り合う。
これを聞いた里見義実は、
「伏姫ですらただ独り去年からここにいたものを、弓矢取る身分の主従三人が毒蛇、猛獣を恐れるあまり、一晩亡骸を守ることもかなわず、慌てて麓に下るというのか。それを聞いて姫を思うと、伏姫の覚悟の立派さを知らなかった親として、恥ずかしいものがある。ああ、姫が男に生まれて来れば良かったと思う。妻の五十子に泣き立てられて、心弱くもはるばると自分から姫を訪れたことは、今更ながら慚愧に堪えない。だからこそ、今その死に及んでも私は一滴の涙も出ない。もし姫の魂が未だここを去っていなければ、お前たちの議論は女々しいと、伏姫に笑われてしまうぞ。枝を折って火を焚きつけよ。今更だが私も弁当箱を開こう、急ぐことはない」
と言うので、堀内貞行と金碗大輔は感激して、まず伏姫の亡骸を洞の中へ入れた。
主従は入口近くの木の下で車座に座り、静かに夜明けを待った。
その時、向かいの岸に数多くの松明が閃くのが見え、人々の声もかすかに聞こえてきた。
堀内貞行は遥かにこれを見て、
「ようやくお供の方々がお迎えに参りましたぞ。さあ、この瀬を渡ってもらおう」
と言って、すぐに水際に走り寄って、
「そこにおいでの松明は、お迎えの方々か。殿はこちらにいらっしゃいますぞ。私はすでにこの川を渡りました。風聞とは反対に、意外と流れは緩く瀬は浅うございます。早くお渡りなされ」
声を限りに呼び掛けた。折よく追い風となり、その声は確かに向う側に届いた様である。
松明があちこちで閃き、坂を下って岸に降り立つと思われる者、先に進む者、後に続く者、声を合わせて馬を引入れながら、多くの人が渡って来る様であった。
こちらの岸に近づくのを見てみると、思いがけずも現れたのは、釣台にくくりつけられた婦人用の駕籠である。体格の良い男が七八人、赤裸になって駕籠を運んでいた。その他は、麓に残されていた従者や新たに滝田からやってきた者もいた。
堀内貞行はそれを見て不審に思い、
「あれは何だ」
と問うと、男たちは水際で駕籠を降ろすと、こう返答した。
「我々は申し合わせておりました。日が沈むまでに殿がお帰りにならなければ、途中までお迎えに参ろうとしていたのです。出発したところに、奥方様から火急のお使いが参られました。そこで一緒に山に入り、急いで向かったものの、しばらく行くほどに日も暗くなり、何とかあちらの岸まで参りました」
堀内貞行はうなずいて先を促せた。
「そこでお声を掛けていただいたのですが、我々だけで川を渡す手段もございませんでしたので、雨具と松明などを乗せてきた釣台に奥方様からのお使いの駕籠をくくりつけ、どうにか渡らせたのでございます」
再び堀内貞行はうなずき、
「それは良く話し合ってきたものだ。さあ、使者よ、こちらへ急ぎ参られよ」
急がせると五六人が立ち上がり、手早く細引きの麻縄を解いて、駕籠の戸を引き開けた。中を見ると、使いの者は侍女の長で年のころは四十あまり、名前を柏田(かへた)といった。かつて伏姫の安否を知るために、使いの命を受けて、向かい側の岸までやってきた者であった。
火急の使いであったので、道すがらずっと駕籠を担ぐ者たちを急がせてやってきた。駕籠の中には三尺(約90センチ)あまりの白布を結んでおり、その身には衣服の下に帯からみぞおち辺りまで白い練り絹を何周にも巻き、身体を締めている。鉢巻も捩じり巻いていた。
これは俗に駕籠を早く走らせる早打ちというもので、大変厳しいものだ。長い距離を揺られて来たので、柏田はめまいを起こして、左右の介添えがなければ立つことができないでいた。男たちは、柏田を助けて外に出してやった。
堀内貞行はまず里見義実の近くに行って、状況を伝えると、柏田も後について里見義実に目通りを行った。
「何の用件で来た。気がかりであるから、早く申してみよ」
訪問の理由を問えば、柏田は臆することもなく、頭を上げて返答した。
「殿には今朝早く館を出発なさってから、奥様の具合がますます重くなられました。殿はお帰りにならないか、と何度も聞かれ、あるいはうわごとでございますが、姫上がすぐそばにおいでになるような感じでお話になり、そしてお嘆きになるのです。私には奥様が痛ましいこと、限りなく思えました。他の侍女も姥たちも言うまでもありません。義成御曹司もとうとうお慰めに困りなさって、実は父上は姉上を自らお訪ねなさって富山に行かれております、明日は必ず姉上を連れてお帰りになりますとなだめられたのですが」
柏田は言葉を切って里見義実を見た。しかし何も言わないので続けるしかなかった。
「奥様はひどく驚きになって、富山は名だたる魔所と聞く、殿がそこへ行ったのなら何かが起きずにお帰りにならない、すぐに呼び返してあげなさいとご機嫌悪くされました。これにはいよいよ義成御曹司もなすすべもなくお困りになりました。柏田は富山の案内を知っていると聞いた、と御曹司は言われました。父上が出発なされてからまだひと時も立っていない、急げば途中で追いつくかもしれないので、今すぐ行って事情を話してくれ、とおっしゃいましたので、とりあえず慌てて館を出たのです。一緒に参った者が疲れれば、里々で駕籠を担ぐ者を替えて、歩みを急がせ、辛くもここに参りました」
と言ったところで、外にいた従者たちが騒ぎ出した。
「向かいの岸にちらちらと見える火の光が見えていたが、今はもう水際に来ている。まさしくあれは駕籠だ。そうであろう、それとも違うのか」
とばかりに、大きな声でうるさいのである。
堀内貞行と金碗大輔は聞いた途端、走り出て川岸を見た。
「再度の早打ちか、心もとない様子だ。こちらからも助けてやり、川を渡れる様にせよ」
そう命じすると、屈強な下僕たちは承ったと返答した。十人ばかりで例の釣台を抱え上げて、川の流れを切り、石を踏み避けて、向う側に行った。
【使者の早打ち、夜に水を渡す】

扇子を持った堀内貞行さんと馬。
左の川の中には駕籠が見えますが、何かあっぷあっぷしてそうで怖いです。
ちょっと激流すぎませんか?
柏田の時と同じ様に新しい駕籠と釣台をくくりつけ、従者とともにやがてこちら側に渡ってきた。駕籠を下ろして戸を開くと、中からまた一人の侍女が現れた。年頃はまだ二十になっておらず、名を梭織(さおり)と呼ばれる者である。艶やかで美しい髪と額にねじ切りの鉢巻きをして、強そうに見える格好は、柏田よりも見映えがした。
梭織は駕籠を出た途端、気絶してしまい、たちまち倒れてしまった。堀内貞行と金碗大輔孝徳は驚きながらも、顔に清水を注ぎ、薬を飲ませてやった。
介抱しているとやがて梭織は我に返り、二人に礼を言い挨拶をした。元から使いの役に選ばれた者であるから、長駆の疲れをものともせず二人に誘われて、里見義実の前に出た。
里見義実は声を掛けて、
「一度ならず再度の使いとはいよいよ気がかりなことだ。五十子はいかがした」
と聞けば、梭織ははらはらと流れる涙を拭わずに、
「奥様は今朝、巳のころ(午前9時から午前11時の間)に」
最後まで言えずに沈黙してしまえば、先に来ていた柏田が泣き出してしまった。
里見義実は嘆いて、
「こと切れたか」
梭織はわずかに頭をもたげ、
「ご臨終のことをお話いたしますのは、容易なことではございません。柏田がお使いに出発した後、すぐにお亡くなりになりました。義成御曹司が言われるには、騎馬でこのことをご報告するのは簡単だが、お忍びのご入山であるので差しさわりがある。お前は以前に柏田とともに密命を受けて富山に行ったことがあると聞いているので、山に向かって父上にお伝えして欲しい。今晩を過ごすな、早く行けとお急がせになるので、そのまま駕籠に担がれて参りました」
と言ったので、金碗大輔と堀内貞行は顔を見合わせてから、頭を垂れてため息を吐く。
里見義実は子細を聞くと、
「五十子の今際の願い、聞き届けられなかったことを残念に思うが、娘の末期に逢えなかったのも幸いなのかもしれん。もしも明日まで生き永らえたとしても、姫が帰っても何と言うべきだろう。お前たち、あれを見よ」
侍女たちは、里見義実の指し示す洞穴を見て、置かれている亡骸に気づいてしまった。柏田と梭織は胸を騒がして、差し込む月の明かりを頼りに、洞穴の中を何度も見て、等しく同時に声を出していた。
「これは姫上におわします。猛獣に傷つけられなさいましたか、そうでなければ刃で果てなさいましたか。何という浅ましいことでございましょう、お痛ましいことでございましょう」
亡骸の周囲で二人は伏して、涙でむせ帰る様に泣いた。
さすがの里見義実も見ておられずに、堀内貞行らに言う。
「義成がさぞかし待ちくたびれてことだろう。人々がたくさんいるので、朝に掛けて山を下ろう。金碗大輔は十余人の下僕とともに留まって、明日は伏姫の亡骸をこの辺りに埋葬せよ。また犬の八房も埋めよ。思いもがけず姫が話し相手を得ることができた。柏田も梭織もこのまま、今宵一夜は残ってくれ。母の使いを今は亡き姫の御霊に手向けとして、通夜をせよ。埋葬の儀はこの様にせよ」
と、丁寧に指示し、侍女たちを労い、従者たちをも賞してやった。そして従者が引いて来た馬に乗り、川岸に向かっていく。
残った者は金碗大輔とともに主人を見送り、主人に従う者は堀内貞行とともに松明を照らして、川の瀬踏みをしつつ渡って行った。
次の日昼過ぎになって、富山の麓の村長は、僧侶と百姓とともに棺を担いで、喘ぎながら洞穴を目指してやってきた。明け方に里見義実は滝田へ帰城の折り、途中で堀内貞行に命じて、麓の村長らに俄かに棺と葬式の道具を作ることとそれを山中の金碗大輔に渡すことを行わせたのである。
またこの日から木こり、炭焼き人の他すべての山で生活する者に、富山の出入りの自由が許される様になった。
こうして入道となった金碗大輔は、村長から棺を受け取って、まず伏姫の亡骸を納めてやった。洞穴を浄めて墓所とする。しかし墓のしるしとなるものがない。ただ松と柏の常緑樹が繁っていて、それが自然と墓標となった。
後に麓の人々が伏姫のことを伝え聞き、これを呼んで義烈節婦の墓と言う様になる。
また八房も土葬にした。八房の亡骸は厨子に納めて、敢えて棺を用いなかった。
そしてその厨子を、伏姫の墓から三丈(約9メートル)ばかり戌の方角(西北西)、ひのきの老木の下に埋めた。人々はそれを呼んで犬塚と言う。
葬送がこの様にすべて質素に行われたのは、里見義実がかねてから金碗大輔に命じたためである。姫の志を汲んだのだ。
すべてが終わってから柏田と梭織は、下僕たちを連れて泣く泣く滝田へ帰っていく。麓の村長や法師たちもそれぞれの里へ帰っていく。
その中で金碗大輔孝徳は、円頂黒衣、つまり髪を剃り、法衣を身にまとって、ヽ大坊と法名をつけてしばらく山に留まることにした。伏姫の遺した法華経を読んで唱えること、一日一夜も休むことなく四十余日に及んだのである。
滝田では奥方五十子の葬式が執り行われ、亡き人々のためにお布施の米がふるまわれて、貧しい民を賑わせた。また洲崎の行者の石窟へ堀内貞行を遣わして、寄進をして、参詣者のために参道の整備を行った。
人は皆、この上ない功徳であると言った。
早くも五十子と伏姫の四十九日が近づくと、里見義実の嫡男義成を施主として、滝田の菩提院で大斂忌の四十九日法要を行うと人々は囁いた。
里見義成は、この法要にヽ大坊を呼べ、と使いの者を富山に遣わしたが、ヽ大は山には不在であった。尚、あちこち探す中で、木こりらが以下の様に言った。
例の法師は前から準備をしていた。仏具を入れた笈の箱を背負い、錫杖を衝き鳴らして、今朝山を下る時、木こりたちを見返って、滝田の殿からこの入道をお尋ねになることがあれば、その様に申せ、と言ってどこかへ出て行ってしまった。
お待ちになられても、きっと法師はお帰りになりません。
成果なく戻った使者は、滝田へ立ち返り、木こりから聞いた話を報告すると、里見義実は感心した。
「大輔は、いやヽ大は、以前、六十余国を遍歴して、飛び去った八つの珠を繋げなければ生涯安房には帰らないと誓っていた。再会は恐らく無理であろう。残念であるが」
そう呟いて、二度と行方を探さなかった。
しかし心には絶えず気に留めていたのだろう、ヽ大坊が無事に帰ってくることがあれば、と身を寄せる場所として、翌年伏姫の一周忌のころまでには、富山に一棟の観音堂を建立した。伏姫の生涯、八房のことさえ書き記して、姫の遺書とともに厨子の中に納めたのだ。
今なお富山に観音堂がある。
こうして何年経っても、ヽ大坊は音信はなかった。結局、ヽ大法師の行方はどうなったのか。それは後々の巻で明らかとなる。
作者曰く、この書の物語の第一巻から今この巻までは、すなわち一部小説の開幕部分であり、八士出現の発端である。これより次の回は年月は続くことがなく、大分後のことに及んでしまう。
その間に物語はない。例えば水滸伝で、龍虎山において洪信たちが石碑を開くところから、林冲たちの出現までの間は数十年、物語はないに等しい。
またこの回の挿絵で金碗大輔孝徳が川を渡る図は、文外の画、画中の文である。この挿絵に頼らなければ、突然、雲霧が晴れていくことが分かりにくい。
また侍女の早打ちに、柏田、梭織を描くのに、それが描かれているところを第十一回で表し、実際に登場するところを後に、今回の第十四回で出した。侍女たちの小伝、来歴、後に登場人物の口から語ることもある。出演を先にして、経歴を後にすることもある。
挿絵もそれに従うのである。しかし挿絵画家は絵を描くのが主であるから、作者の意を捉えられないこともある。時には齟齬があるものだ。
読者もよろしく察して欲しい。
(続く……かも)










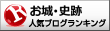

















だいたい、端折られることが多い…それゆえ、モヤモヤしていたのですが、よくわかりました。
ここをちゃんと読んでいると、本編がさらに面白くなる。
伏姫を連れて帰らなかったというのは意外でした。
犬塚…ここからでしたか。
今回も難しいのをわかりやすい超訳、ありがとうございました。
ますます面白くなってまいりました。
な、長かった~
ご指摘の通り、仏教めいた話はカットされることが多いですからね。
伏姫の亡骸は館に連れて行っても良かったのですが、富山が八犬伝の聖地になるには、姫が必要なのかもしれませんね。
次には犬塚信乃関連で大塚が出てきますが、東京の豊島区大塚なんです。。。
面白く、と読んでいただきありがとうございました。