子ども被災者支援法はとてもいい基本法として制定されました。
被災者を分断することなく、より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「順支援対象地域」を設定し、きめ細かな被災者支援を実施するよううたわれています。しかし、実際には、33市町村だけの対象と区切られてしまいました。
この日は「SAFLAN」事務局次長・江口智子弁護士、自主避難者「Snow Drop」代表・二塀和子さん、たねまきネット・遠藤がスピーカーでした。
二塀さんは、この日も避難中のママたち手作りのアクセサリーやマスク、雑誌、ケーキを持ってお子さん二人を連れて参加。



 ふたりが黒板一杯に描いた絵
ふたりが黒板一杯に描いた絵
「福島から避難しているからこそ関東の人に考えて貰うことができる。子どものためにやっていることが、夜も子ども連れで出なくてはならず、会のための活動になってしまうが、でも自分の子どものためだけでなく活動している。すでにセシウムが出ている子がいる。



「あなたの健康を見守ります」と「しらじらしく」描かれた一人ずつに渡される管理ファイル
自主避難者への支援何もない。33市町村だけの対象に区切られたこと悔しい。裁判のことをきかれるが、私は支援法での活動が理解されやすいと思っている。これ一本ならわだかまりがないし、分断されない。


色々な支援や助成金の報告はあるが、その後の継続した活動がなくなっている。自分たちは研究材料のために支援されたような気持ちになる。そういう支援はしてほしくない。
2年たつともうそこの生活者になる。避難者としての特別なカフェなどにはもう行かない。そこで生きる権利を持ちたい!」
と力強く話されました。
江口弁護士からは、支援法の詳しい内容。そして今それがどのくらい運用されているかいないかが詳細に話されました。「
「東電への賠償請求を自主避難者へも摘要させたい。チェルノブイリ法を倣って実施させたい。被爆を避ける権利もある。支援法具体化訴訟も考えられている。避難者の声を届けていくしくみが必要だ。当事者団体がそれぞれ活動しているが、全国的な当事者団体がないので、なかなか当事者の声としてまとめられない。弁護士団体でなく当事者団体でそれができたら良いと思う。」
この後、参加者からも活発に意見が出されました。法律を実施しない政府や行政へのいらだちをみんな持っています。大きな政治を動かすことと同時に、民間で、地域でそれぞれの所でできることを実現することも急務だと思いました。



































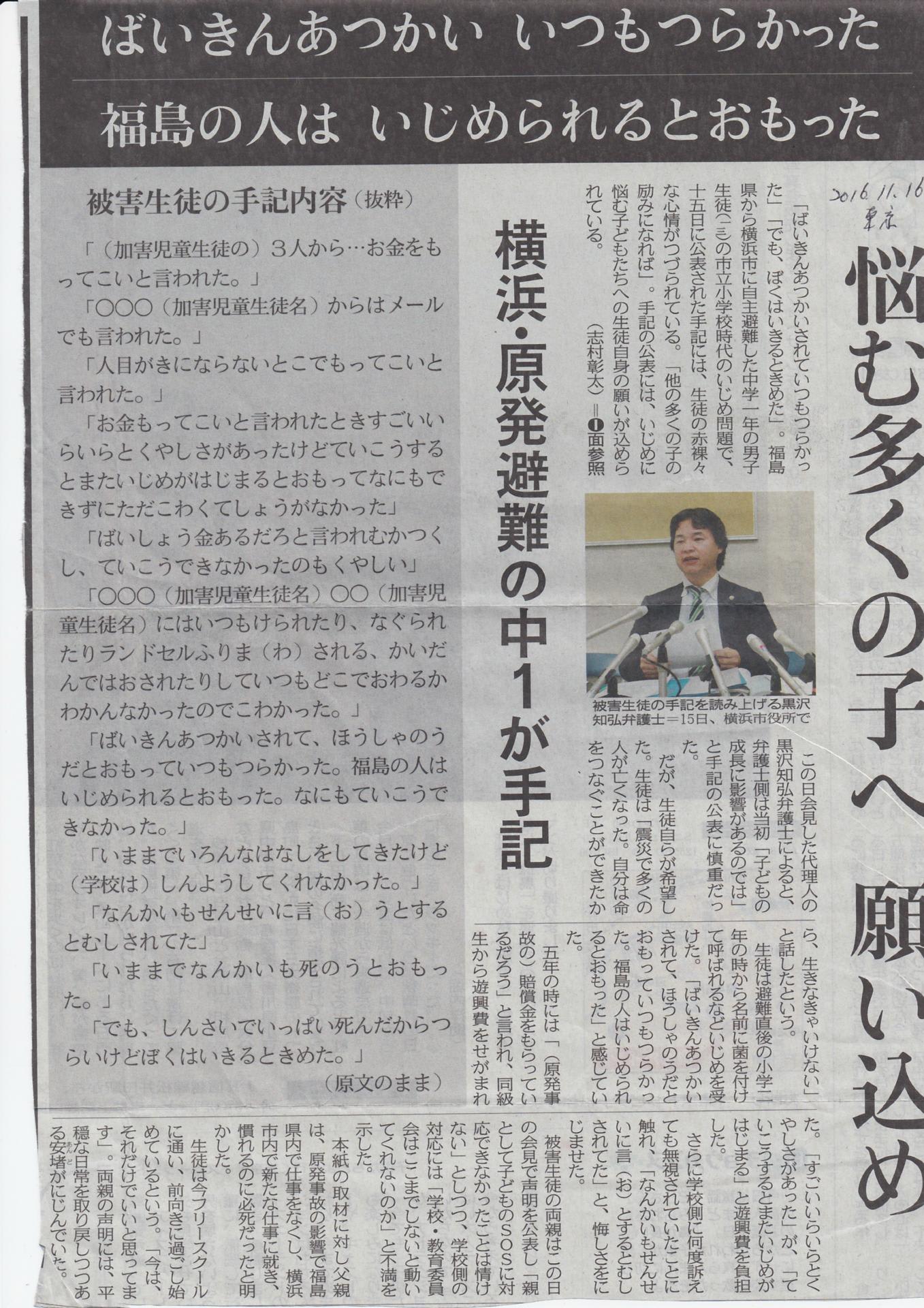














 ふたりが黒板一杯に描いた絵
ふたりが黒板一杯に描いた絵







