2013.8.30「あひる通信」から
寄付の趣旨と、その下には「あひるの家」で扱っている商品の放射能分析結果も載っています。

2013.8.30「あひる通信」から
寄付の趣旨と、その下には「あひるの家」で扱っている商品の放射能分析結果も載っています。

ヨウ素剤を配った三春町の決断
NHKの宣伝をするつもりはありませんが、これもたまたま、台風情報を気にしてつけていたテレビで始まったので、思わず携帯に収めた次第です。ですのでまたしても映像が不鮮明ですがとりあえずの紹介です。
原発事故直後の、国や県の対応、それに対する三春町行政担当職員の決断は、とても対照的です。私たちは何を信じ、何を基準に生きていけばよいのか、考えさせられます。
自分の命は自分で守るしかないのか?いやいや、まだまだ信頼できる公・行政もあるのだと、この震災・原発事故に際して思います。誰を信じ、誰とともに生きていくのか、その答えを一人一人とつながりながら、丁寧に関係性をつくりながら、見いだし、そうしたつながりの中で生きられる社会を目指していくしかないのかもしれません





















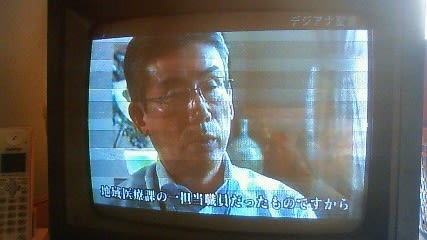
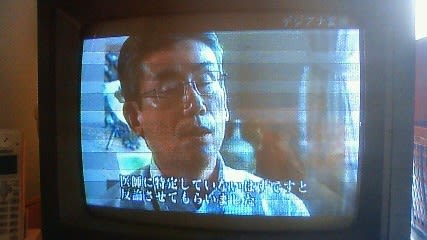






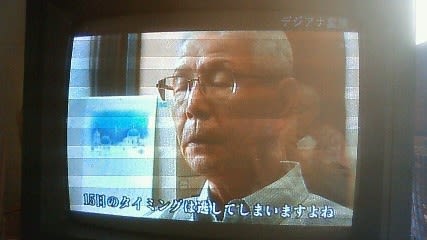










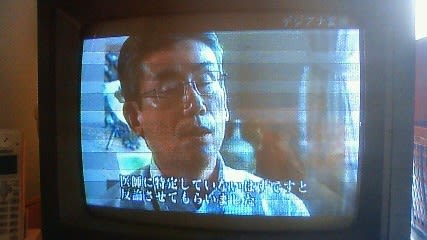
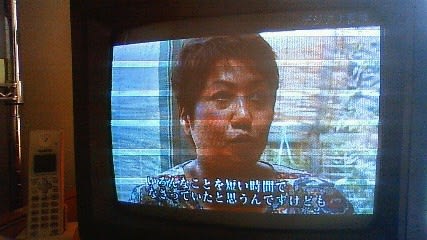


この他にも、子どもに飲ませたかったが、本人の意思で副作用があるので飲まないというので飲ませなかったが、後悔している。その後、できるだけ被爆しないような生活をさせるようにしているという母親の声もありました。
沢山のことが自己責任に帰されてしまう社会。人の良い私たち市民の「自己責任」を無駄にしないで、そこから学びとったことを共有し学びあいながら、生きやすい地域作りをしたいものです。
ベラルーシからの報告をご覧になりましたか?
9月16日の夜10時~のETV特集をご覧になりましたか?そして23日にもシリーズ2回目が放送されました。30日にも第3回放送があります。ご覧になってください。
私は、16日しか見れなかったので、それを載せます。事故後も近くの土地にとどまり農地を農地として守り、子や孫に土を土として残すために自らの被爆よりも未来のために作物としては食べられない作物を作り続ける姿から、何を読み取ったらよいのか。
今まさに日本の私たちが問われていることが、今もまだ問われ続けているベラルーシの姿です。

1986年4月に起きたソ連のチェルノブイリ原発事故で国土の4分の1が放射性物質に汚染されたベラルーシ共和国。原発からの距離が15キロから80キロの範囲に位置するホイニキ地区(日本の郡に相当)はその大部分が汚染地域となり多くの村人が故郷を離れざるを得なかった。(注:ベラルーシで汚染地域と呼ばれるのはセシウム137で、1キュリー/平方キロメートル=37000ベクレル/平方メートル以上のエリア)
しかし農場長(村長に相当)のニコライ・サドチェンコさん(65)は村に残り、この26年間、放射能汚染と格闘しながら農業の再生に取り組んできた。一方汚染地域から避難した人々の中には、故郷を失った悲しみや移住先での差別にいまも苦しんでいる人が少なくない。故郷で死にたいと、全村避難した村に戻って暮らす老人たちもいる。
事故から26年、ベラルーシの人々はどのように放射能汚染と戦ってきたのか。農業再生に取り組んできたニコライさんと故郷を失った移住者たちの今を取材した。
















汚染情報の公開を求めたベラルーシの物理学者マリコ氏
以上は携帯電話で慌ててとった写真なので、大変画像が悪くてすみません。
来週の NHK ETV特集
シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地帯からの報告 「第2回 ウクライナは訴える」
なぜ?原発再稼働?!
4万人の人々が集まったそうです。














多くの人の不安をよそに原発再稼働を決定する政府の論理は、誰を救うのか?
昨年は被災者救済と復興が第一で計画停電を決定できた政府が、
1年しか立ってない今、ゴーサインを出すのは、誰のため?
政治に翻弄されることなく、現地と現地の生の声をしっかりと耳目におさめ、
伝え、私たちが求めるものを、福島とともに見いだしていきたいものです。
二本松のいたましい事故!!
先日の9日、二本松市、国道349号線で、原発事故のため避難していた方々の乗ったワゴン車と大型トレーラーが正面衝突した事故のことが、朝日新聞社会面で大きく報じられていました。









 (ツアー担当)
(ツアー担当)


恒例の落ち葉はき 東京都西多摩郡瑞穂町 S農園にて
福島原発事故による放射能汚染はこの三多摩地区にも及んでいる。落ち葉を堆肥として利用する有機農家にとっては深刻な問題。今年はどうするか。生産者と運営委員で検討した結果、例年通り「落ち葉掃き」を実施することにした。ただし、今年の落ち葉は堆肥には使用せず、別途保管することにした。因みにこの雑木林の線量(地表面での測定)は0.11~0.12マイクロシーベルト/毎時。
落ち葉掃きには絶好のお天気。今年は子どもたちの声が聞こえない。マスクをつけて黙々と作業を行う。
三多摩たべもの研究会