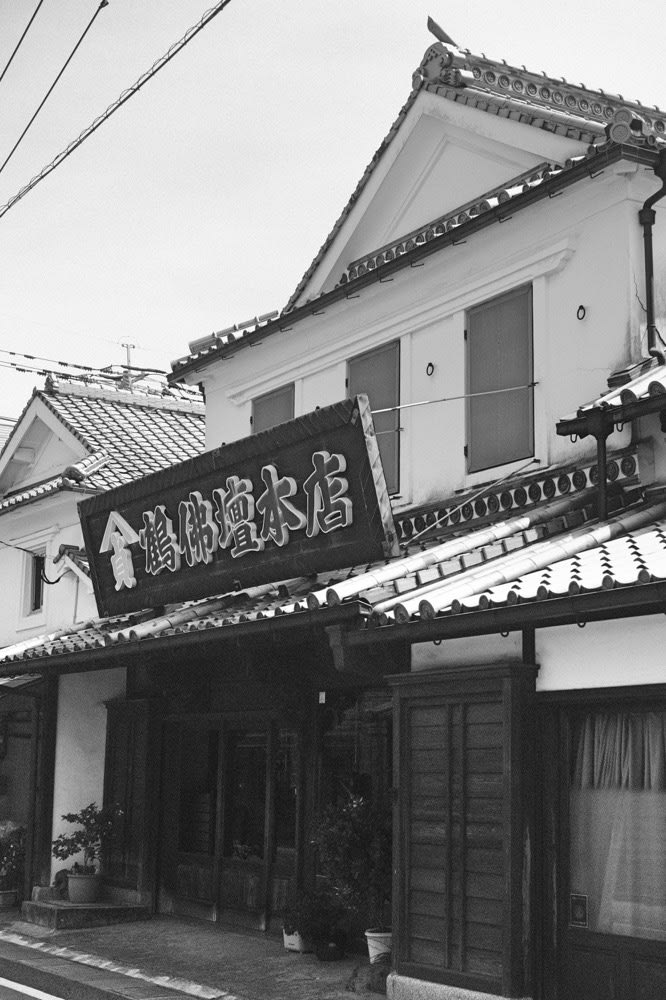Kyushu Railway History Museum, Moji Ward, Kitakyushu City, Fukuoka Pref.
さてさて、門司港駅の素晴らしい駅舎を見学したワタクシ達は次の目的地へ向かいました
 。
。

門司港駅のすぐ隣に、「九州鉄道記念館」という九州の鉄道の歴史を学べる記念館があるんです。
ワタクシ達はこの記念館で、九州の鉄道史を学ぼうと思ったんですよ。
入口の横にある機関車は9600型蒸気機関車。大正時代に生産が始まったSLです。
この車両は最後に筑豊地区で石炭を運搬するために使われていたそうです
 。
。

これはC59で、この機関車は東海道本線や山陽本線で寝台列車を牽引して活躍しました。
廃車になるまでに地球62周の距離を走行したそうです
 。
。

C59の「C」というのは動輪の数を表し「C」は動輪が3つ。有名なD51だと「D」ですから動輪の数は4つになるわけです
 。
。

ワタクシはさすがにこの車両は知りませんでした。キハ07というこの気動車は、戦前に造られたものなのですが、
昭和44年まで宮原線で使用されていたそうです。なお宮原線というのは大分県の豊後森駅と熊本県の肥後小国駅を結んでいましたが、
昭和59年に廃線になっています
 。
。

クリーム色と赤色に塗られたこの特急電車は、皆さんにも馴染み深いのではないでしょうか。
昭和33年に東京〜大阪間を結んだ「こだま」型車両を、交直両用にした480系特急列車です。
九州で特急「にちりん」「かもめ」「有明」として利用されました
 。
。

これは新台電車特急の580系特急列車ですが、「月光」という名前がワタクシには懐かしいんですよ。
ワタクシが鉄道に興味を持った頃、「月光」は新大阪〜博多間を結ぶ寝台特急でした。
その頃はまだ山陽新幹線は無く、九州に向かう寝台列車が数多くあったんです。
ワタクシはよく日曜日の朝早く大阪駅に行き、九州各地から大阪へやって来る寝台特急や寝台急行を見に行っていたんです。
「月光」「明星」「彗星」「あかつき」「なは」なんていう名前を覚えていますわ
 。
。

この赤煉瓦の建物は旧九州鉄道の本社ビルで、現在は鉄道記念館の本館になっています。
内部には鉄道模型のジオラマ、運転シミュレーター、記念グッズのお店などがありました
 。
。

でも、ワタクシの目を一番惹いたのは、かつての九州行き寝台列車のヘッドマークでした。
小さなハーフサイズのカメラを手にして、このヘッドマークを誇らしげに掲げた寝台列車を撮りに行ったんですよねぇ
 。
。

ワタクシは鉄道少年だった頃を懐かしく思うと同時に、今でもやっぱり鉄道が好きなんだと再認識したのでありました
 。
。
使用したカメラ:FUJIFILM X-Pro2
小学生の頃、私は鉄道少年であり野球少年でした。脳みその8割くらいは鉄道と野球のことで使っていたような気がします。
その時はまさか国鉄が無くなるなんて想像もしませんでしたし、日本各地でローカル線が廃線になっていくとは思いませんでした。
小学校の卒業文集の「将来の夢」という欄に、「将来は国鉄に就職して車掌になりたい。
その前に高校野球で甲子園に行きたい」と書いていたのですが、その夢はどちらも叶うことはありませんでした。
ブログランキングに登録しています。こちらをクリックしたいただくと嬉しい限りです。
 にほんブログ村
にほんブログ村

さてさて、門司港駅の素晴らしい駅舎を見学したワタクシ達は次の目的地へ向かいました

 。
。
門司港駅のすぐ隣に、「九州鉄道記念館」という九州の鉄道の歴史を学べる記念館があるんです。
ワタクシ達はこの記念館で、九州の鉄道史を学ぼうと思ったんですよ。
入口の横にある機関車は9600型蒸気機関車。大正時代に生産が始まったSLです。
この車両は最後に筑豊地区で石炭を運搬するために使われていたそうです

 。
。
これはC59で、この機関車は東海道本線や山陽本線で寝台列車を牽引して活躍しました。
廃車になるまでに地球62周の距離を走行したそうです

 。
。
C59の「C」というのは動輪の数を表し「C」は動輪が3つ。有名なD51だと「D」ですから動輪の数は4つになるわけです

 。
。
ワタクシはさすがにこの車両は知りませんでした。キハ07というこの気動車は、戦前に造られたものなのですが、
昭和44年まで宮原線で使用されていたそうです。なお宮原線というのは大分県の豊後森駅と熊本県の肥後小国駅を結んでいましたが、
昭和59年に廃線になっています

 。
。
クリーム色と赤色に塗られたこの特急電車は、皆さんにも馴染み深いのではないでしょうか。
昭和33年に東京〜大阪間を結んだ「こだま」型車両を、交直両用にした480系特急列車です。
九州で特急「にちりん」「かもめ」「有明」として利用されました

 。
。
これは新台電車特急の580系特急列車ですが、「月光」という名前がワタクシには懐かしいんですよ。
ワタクシが鉄道に興味を持った頃、「月光」は新大阪〜博多間を結ぶ寝台特急でした。
その頃はまだ山陽新幹線は無く、九州に向かう寝台列車が数多くあったんです。
ワタクシはよく日曜日の朝早く大阪駅に行き、九州各地から大阪へやって来る寝台特急や寝台急行を見に行っていたんです。
「月光」「明星」「彗星」「あかつき」「なは」なんていう名前を覚えていますわ

 。
。
この赤煉瓦の建物は旧九州鉄道の本社ビルで、現在は鉄道記念館の本館になっています。
内部には鉄道模型のジオラマ、運転シミュレーター、記念グッズのお店などがありました

 。
。
でも、ワタクシの目を一番惹いたのは、かつての九州行き寝台列車のヘッドマークでした。
小さなハーフサイズのカメラを手にして、このヘッドマークを誇らしげに掲げた寝台列車を撮りに行ったんですよねぇ

 。
。
ワタクシは鉄道少年だった頃を懐かしく思うと同時に、今でもやっぱり鉄道が好きなんだと再認識したのでありました

 。
。使用したカメラ:FUJIFILM X-Pro2
小学生の頃、私は鉄道少年であり野球少年でした。脳みその8割くらいは鉄道と野球のことで使っていたような気がします。
その時はまさか国鉄が無くなるなんて想像もしませんでしたし、日本各地でローカル線が廃線になっていくとは思いませんでした。
小学校の卒業文集の「将来の夢」という欄に、「将来は国鉄に就職して車掌になりたい。
その前に高校野球で甲子園に行きたい」と書いていたのですが、その夢はどちらも叶うことはありませんでした。
ブログランキングに登録しています。こちらをクリックしたいただくと嬉しい限りです。