
布薩
ふさつ
と読みます。

これはどういうことかというと「火もしくは神に近住する意」だそうです。
そして
「婆羅門教(ばらもんきょう)の新月祭と満月祭の前日に行われた儀式を仏教に取り入れたもの」
ちょっと難しいですよね💦
要は、
毎月二回お坊さんたちが集まって、僧侶としての戒の条目を唱えて、自分自身を反省する儀式のことを言います。

私の実家が須磨寺にお墓があるので、その須磨寺では毎月の新月と満月に布薩を行うので、それが今日にあたります。
布薩なんて言葉は今まで知らなかったのですが、香川県から兵庫の須磨寺に墓じまいし、須磨寺について色々調べていると、小池陽人副住職さんにたどりつきました。
小池陽人副住職さんが布薩についてYouTubeでお話されていたのがきっかけで、布薩をはじめ、いろいろと学ぶことになりました。
話それました‼️
布薩は、全体の儀式の中で、百の礼拝行を通して戒の条文を読むのですが、
単なる形式的な儀式ではなく、現代語訳を読むことによって、自覚を促されるということなんです。

戒という言葉だけで見ると「いましめ」であると思われますが、原語の意味からすると、
「いましめ」というよりも「良き習慣」であると受けとめるようにです。
習慣といっても、「戒を守るように習慣づける」というより、
「戒を守れていないことに気がついて、今一度戒に戻ることを習慣づける」という意味なのです。
この布薩を行う意味は、雑念が起こったなら、そのことに気づいてもう一度戻ることが大切だと。
百礼拝はまだできていないけれど、今日は布薩ということで、戒に戻る、習慣づける、気づく日と思って月2回これから布薩を行っていきます。











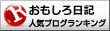

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます