社会を動かした個性/永井道雄/講談社現代新書/1965
三木内閣時代、文部大臣を務めた、京大文学部卒の教育社会学者が書いた、十河信二、高碕達之助、安部磯雄、松村謙三、角田柳作、幣原喜重郎が登場する偉人伝。
道徳の教材としていいかもしれない。
この本の最初の文章にハッとすることが書かれているので転載させていただく。
http://ameblo.jp/osamuari/entry-10037400013.html
<1>個性の人
孤独の底にある連帯
私はいま『社会を動かした個性』と題する本を書こうとしている。その理由はなにか。
もっとも単純な理由は、今日の日本には個性の人が少ないが、私は、日本が個性の人を必要としていると考えるからだ。では個性の人とはなにか。――
個性の人とは、他の大多数の人々とは異なる人だ。しかしそれは奇人・変人ではない。私が個性と名づけるのは、科学・技術・思想・経済・芸術など、領域をとわず、個人として努力し、苦しみ、自分の力によって新しいものを創造する人間である。
ことばをかえれば”異色の人”といってもよい。しかし、この表現はつかい古されており、しかも抽象的で意味がわかりにくい。個性の人は異色なのである。職場や家や、学校や政党など、既成の集団の権威にはよりかからない。彼はだれよりも彼自身と対話する。対話を通して、あるときは神を、科学を、芸術をまたあるときは政治的、また社会的理想をさがし求め、その過程で自らをきたえる。だから個性の人は独立はしているが孤独ではない。彼のよりどころは良心であり、理想であり、思想であって、それがもつ普遍性は、家や、政党や、学校や、職場など、かぎられた世界がもつ権威を越える。だから個性の人はまた公の人である。個人を深めることによって、人類の幸いと平和など、よりよい価値とその実現を求める、独立した生活の底で人類との連帯に生きる人である。
読んだ感想としては、永井道雄が、この本の中で見せる、戦後民主主義を消極的ながらも肯定するような姿勢、どちらかと言うと左翼主義的な人が6人の中に入っている点、特に幣原喜重郎について肯定的に評価している点が不満である。
ただ、それも永井道雄という人が、外交を含めあまりに性善説的に物事を考える人だったと理解すればすむことなのではあるが。
ただ、幣原喜重郎についてまとまった記述をしている本が少ないので、そういう意味では読む価値があるだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%A4%96%E4%BA%A4
肯定的評価 [編集]自主的な外交による日本の国際社会における地位向上に貢献した、との評価[誰?]がある。すべての観点に必要な点は対米債務を背負ったまま、中国市場を堅持しつつ、対米輸出も促進させた当時の日本には選択の余地がなかった点である[要出典]。
否定的評価 [編集]その一方で地政学の立場からは、対中協調外交の結果として日英同盟などの軍事同盟の維持が不可能になり[1][2]、結果として軍人による対外拡張政策に歯止めを与える存在を無くしてしまう結果になった[3]などの指摘がある。さらに、中国の排外ナショナリズム抑制の機会を逸したこと、英米からは「抜け駆け」として不審を買ったこと、対中宥和政策へと転換した英米が、蒋介石の北伐軍の進撃を日本の利権が集中する華北や満洲へと助長させたことが済南事件や満洲事変を誘発する結果となったことなどが挙げられる[4]。そのため、中国における排日運動が明確な国際法違反の侵略行為である[5][4]との観点から、幣原の譲歩が結果的に「満洲事変への道」を不可避ならしめた[4]点で、第一級の戦争責任を負うべき人物であるとの批判を中西輝政が行っている[4]。
1925年11月の郭松齢事件の際、奉天総領事であった吉田茂は、「満洲における帝国の特殊の地位に鑑み我勢力圏内においては軍閥の死闘を許さざるの儀を鮮明にするを機宜の処置と思考す」と上申し、幣原外交を批判した。
三木内閣時代、文部大臣を務めた、京大文学部卒の教育社会学者が書いた、十河信二、高碕達之助、安部磯雄、松村謙三、角田柳作、幣原喜重郎が登場する偉人伝。
道徳の教材としていいかもしれない。
この本の最初の文章にハッとすることが書かれているので転載させていただく。
http://ameblo.jp/osamuari/entry-10037400013.html
<1>個性の人
孤独の底にある連帯
私はいま『社会を動かした個性』と題する本を書こうとしている。その理由はなにか。
もっとも単純な理由は、今日の日本には個性の人が少ないが、私は、日本が個性の人を必要としていると考えるからだ。では個性の人とはなにか。――
個性の人とは、他の大多数の人々とは異なる人だ。しかしそれは奇人・変人ではない。私が個性と名づけるのは、科学・技術・思想・経済・芸術など、領域をとわず、個人として努力し、苦しみ、自分の力によって新しいものを創造する人間である。
ことばをかえれば”異色の人”といってもよい。しかし、この表現はつかい古されており、しかも抽象的で意味がわかりにくい。個性の人は異色なのである。職場や家や、学校や政党など、既成の集団の権威にはよりかからない。彼はだれよりも彼自身と対話する。対話を通して、あるときは神を、科学を、芸術をまたあるときは政治的、また社会的理想をさがし求め、その過程で自らをきたえる。だから個性の人は独立はしているが孤独ではない。彼のよりどころは良心であり、理想であり、思想であって、それがもつ普遍性は、家や、政党や、学校や、職場など、かぎられた世界がもつ権威を越える。だから個性の人はまた公の人である。個人を深めることによって、人類の幸いと平和など、よりよい価値とその実現を求める、独立した生活の底で人類との連帯に生きる人である。
読んだ感想としては、永井道雄が、この本の中で見せる、戦後民主主義を消極的ながらも肯定するような姿勢、どちらかと言うと左翼主義的な人が6人の中に入っている点、特に幣原喜重郎について肯定的に評価している点が不満である。
ただ、それも永井道雄という人が、外交を含めあまりに性善説的に物事を考える人だったと理解すればすむことなのではあるが。
ただ、幣原喜重郎についてまとまった記述をしている本が少ないので、そういう意味では読む価値があるだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%A4%96%E4%BA%A4
肯定的評価 [編集]自主的な外交による日本の国際社会における地位向上に貢献した、との評価[誰?]がある。すべての観点に必要な点は対米債務を背負ったまま、中国市場を堅持しつつ、対米輸出も促進させた当時の日本には選択の余地がなかった点である[要出典]。
否定的評価 [編集]その一方で地政学の立場からは、対中協調外交の結果として日英同盟などの軍事同盟の維持が不可能になり[1][2]、結果として軍人による対外拡張政策に歯止めを与える存在を無くしてしまう結果になった[3]などの指摘がある。さらに、中国の排外ナショナリズム抑制の機会を逸したこと、英米からは「抜け駆け」として不審を買ったこと、対中宥和政策へと転換した英米が、蒋介石の北伐軍の進撃を日本の利権が集中する華北や満洲へと助長させたことが済南事件や満洲事変を誘発する結果となったことなどが挙げられる[4]。そのため、中国における排日運動が明確な国際法違反の侵略行為である[5][4]との観点から、幣原の譲歩が結果的に「満洲事変への道」を不可避ならしめた[4]点で、第一級の戦争責任を負うべき人物であるとの批判を中西輝政が行っている[4]。
1925年11月の郭松齢事件の際、奉天総領事であった吉田茂は、「満洲における帝国の特殊の地位に鑑み我勢力圏内においては軍閥の死闘を許さざるの儀を鮮明にするを機宜の処置と思考す」と上申し、幣原外交を批判した。











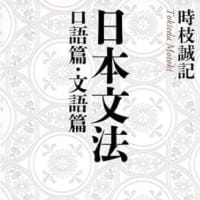




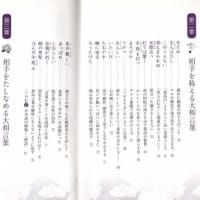
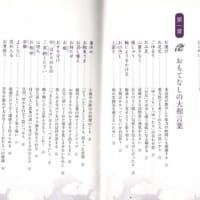
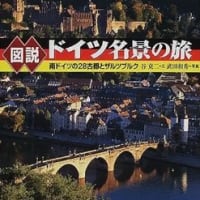
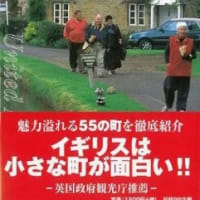







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます