先週、静岡で2日間の仕事、テニスをやった後だったので、新幹線では満席の自由席に何とか席を確保し、居眠りしながら駅前のホテルに到着。
翌朝、食事前に駿府城公園まで速足で散歩、城下町だけあって大手門までの商店街は条里制で整然とした感じだ。
市役所を抜けると、お堀と櫓が見える。
駿府城は明治維新で廃城となり、今は石垣と中堀と一部の内濠が残っているだけで、散策コースに適した公園になっている。
去年は、夜のライトアップで公園内を歩き回ったが、朝の雰囲気はまた違ってさわやかな感じ。
公園内は夕方に見ることにして、帰りは県庁前を通って、急ぎ足でホテルに戻った。

5時過ぎに仕事を終え、ホテルからまた公園に足を伸ばした。
県庁の駐車場脇で文化財調査中という囲いがあったが、4,5年前に秀吉が築城した遺跡が出てきて話題になった場所だと後で知った。
家康は、3度静岡で暮らしたという。
最初は今川家に人質として8歳から18歳までの10年間、2回目は戦国時代の居城として築城、3回目は関が原で勝利し征夷大将軍となった後、1607年に将軍職を退き天下普請として拡張修築して移り住んだとのこと。
静岡駅前には人質の竹千代時代の銅像と後年の原寸大といわれる鎧兜に身を包んだいかめしい銅像が立っている。
かなり背が低い感じで、160cm足らずか?

公園内の天守跡にも家康像、すぐ前には「家康お手植えのミカンの樹」とあるが、どうも疑わしい。
タクシーの運転手さんの話では、駿府城の再建計画はずっと以前からあるが、確かな図面がないので実現できないらしい。
天守跡も工事中の囲いがしてあり、城郭の跡らしい石垣があちこちに見られる。
静岡は、最後の将軍:徳川慶喜が大政奉還で江戸無血開城の後、静岡藩で謹慎生活を送った地。
駅前に、慶喜が住んだという縁りの老舗料亭がある。
明治維新は「世界に遅れた幕府と進取の気風に富んだ薩長」と言う成功のイメージが強いが、明治政府は、すでに幕府が進めていた変革(安政・文久・慶応など欧米をモデルとした近代化)を、幕府が育てた人財の力を借りて行ったに過ぎない、という見方がある。
勝海舟も慶喜に殉じて静岡に住んだが、彼の書では、幕臣33,400名中、5,000名が新政府に入り朝臣となった。
他に、大蔵省140名、外務省100名など、今でいうノンキャリアの活躍がめざましかった。
慶喜を慕って、静岡に移り住んだ旗本が溢れるくらい大勢いたという。
お札の顔になる渋沢栄一も、欧州使節から帰国して、大政奉還後に静岡蟄居中の慶喜に帰国報告。そのまま1年間、静岡藩にお勤めしていたとか。
その後、新政府に請われ、日本資本主義の父と呼ばれるまでに!
静岡の誇りの一つは、無血開城の陰の主役;山岡鉄舟だろう。
1968年、官軍を率いて江戸に迫る西郷隆盛と会見、慶喜の使者として直談判した。
西郷は「金も要らぬ、名誉も要らぬ、命も要らぬ人は始末に困る」として、彼の人物と胆力を評価し、江戸城での勝海舟との会見の下地を成したという。文武両道、188cmの威風堂々とした風格を備えていたらしい。
後に、10年の約束で明治天皇の教育侍従として宮内庁に勤めた。
静岡藩に仕えたとき、清水次郎長とも交友があり、牧之原のお茶の開拓事業にも貢献したという。
朝の散策中、市役所の前に、教導石という碑を見つけたが、これにも鉄舟が揮毫している。
この碑の趣旨は、「富や知識の有無、身分の垣根を超えて互いに助け合う社会をめざす」とあり、明治の庶民の志の高さに敬意を表さざるを得ない。
お堀の前の歩道にも、静岡学問所の碑があり、徳川家が有為の人材を育てるため、早くも明治元年に創立したと解説されている。
慶喜さんと旗本あってこその維新!と言う面があった。静岡は、江戸と明治をつなぐ地でもあったという気がする。
”勝てば官軍”とばかりに、刷り込まれてきた“薩長史観”が、150年を経て見直されてきている。
最近、勝海舟、山岡鉄舟に高橋泥舟を加え、幕末の三舟と言われた事を、近くに住む泥舟の子孫から聞いた。
翌朝、食事前に駿府城公園まで速足で散歩、城下町だけあって大手門までの商店街は条里制で整然とした感じだ。
市役所を抜けると、お堀と櫓が見える。

駿府城は明治維新で廃城となり、今は石垣と中堀と一部の内濠が残っているだけで、散策コースに適した公園になっている。
去年は、夜のライトアップで公園内を歩き回ったが、朝の雰囲気はまた違ってさわやかな感じ。
公園内は夕方に見ることにして、帰りは県庁前を通って、急ぎ足でホテルに戻った。

5時過ぎに仕事を終え、ホテルからまた公園に足を伸ばした。
県庁の駐車場脇で文化財調査中という囲いがあったが、4,5年前に秀吉が築城した遺跡が出てきて話題になった場所だと後で知った。

家康は、3度静岡で暮らしたという。
最初は今川家に人質として8歳から18歳までの10年間、2回目は戦国時代の居城として築城、3回目は関が原で勝利し征夷大将軍となった後、1607年に将軍職を退き天下普請として拡張修築して移り住んだとのこと。

静岡駅前には人質の竹千代時代の銅像と後年の原寸大といわれる鎧兜に身を包んだいかめしい銅像が立っている。
かなり背が低い感じで、160cm足らずか?


公園内の天守跡にも家康像、すぐ前には「家康お手植えのミカンの樹」とあるが、どうも疑わしい。
タクシーの運転手さんの話では、駿府城の再建計画はずっと以前からあるが、確かな図面がないので実現できないらしい。
天守跡も工事中の囲いがしてあり、城郭の跡らしい石垣があちこちに見られる。
静岡は、最後の将軍:徳川慶喜が大政奉還で江戸無血開城の後、静岡藩で謹慎生活を送った地。
駅前に、慶喜が住んだという縁りの老舗料亭がある。
明治維新は「世界に遅れた幕府と進取の気風に富んだ薩長」と言う成功のイメージが強いが、明治政府は、すでに幕府が進めていた変革(安政・文久・慶応など欧米をモデルとした近代化)を、幕府が育てた人財の力を借りて行ったに過ぎない、という見方がある。
勝海舟も慶喜に殉じて静岡に住んだが、彼の書では、幕臣33,400名中、5,000名が新政府に入り朝臣となった。
他に、大蔵省140名、外務省100名など、今でいうノンキャリアの活躍がめざましかった。
慶喜を慕って、静岡に移り住んだ旗本が溢れるくらい大勢いたという。
お札の顔になる渋沢栄一も、欧州使節から帰国して、大政奉還後に静岡蟄居中の慶喜に帰国報告。そのまま1年間、静岡藩にお勤めしていたとか。
その後、新政府に請われ、日本資本主義の父と呼ばれるまでに!
静岡の誇りの一つは、無血開城の陰の主役;山岡鉄舟だろう。

1968年、官軍を率いて江戸に迫る西郷隆盛と会見、慶喜の使者として直談判した。
西郷は「金も要らぬ、名誉も要らぬ、命も要らぬ人は始末に困る」として、彼の人物と胆力を評価し、江戸城での勝海舟との会見の下地を成したという。文武両道、188cmの威風堂々とした風格を備えていたらしい。
後に、10年の約束で明治天皇の教育侍従として宮内庁に勤めた。
静岡藩に仕えたとき、清水次郎長とも交友があり、牧之原のお茶の開拓事業にも貢献したという。
朝の散策中、市役所の前に、教導石という碑を見つけたが、これにも鉄舟が揮毫している。

この碑の趣旨は、「富や知識の有無、身分の垣根を超えて互いに助け合う社会をめざす」とあり、明治の庶民の志の高さに敬意を表さざるを得ない。
お堀の前の歩道にも、静岡学問所の碑があり、徳川家が有為の人材を育てるため、早くも明治元年に創立したと解説されている。

慶喜さんと旗本あってこその維新!と言う面があった。静岡は、江戸と明治をつなぐ地でもあったという気がする。
”勝てば官軍”とばかりに、刷り込まれてきた“薩長史観”が、150年を経て見直されてきている。

最近、勝海舟、山岡鉄舟に高橋泥舟を加え、幕末の三舟と言われた事を、近くに住む泥舟の子孫から聞いた。











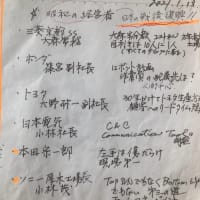
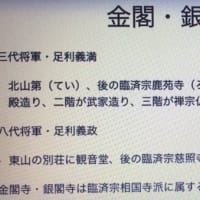
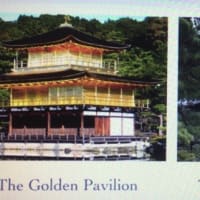
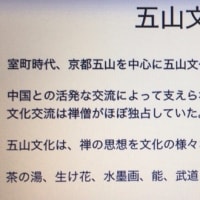
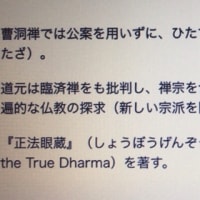
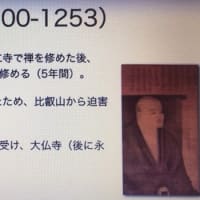
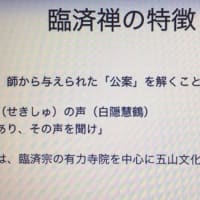
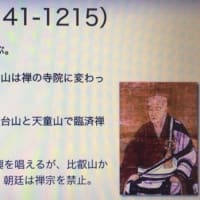
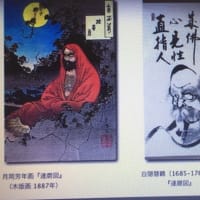
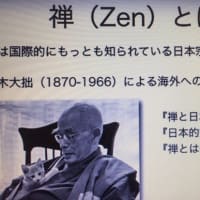
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます