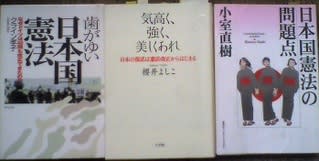
以下、2007年2月7日の記録
圧倒的な自民党政権で、いつの間にか「改正基本法」が2006/12/22施行された。
約60年ぶりの改訂。(1947/3/31旧法制定、その後1948/6/19教育勅語廃止)
いろいろと、改正の評価が行われているが、
私は、今のところ、次のような感想:
→ これまでと同じように実施されなければ”絵に書いたモチ”だから。
<良い点>
1.家庭教育(新設)、父母の責任と公的機関の支援(新設)、とくに幼児教育の重要性を明記
←旧法では、空白部分?そこに教師の独断と偏見が蔓延していた?
2.学校、家庭、地域住民の相互連携・協力を明記
←旧法では、家庭の役割がちょっとだけ。主体は公的機関(国、県、市町村)
3.宗教一般教育に言及(新設)
←宗教に無防備な国民から反省?オカルト宗教/占いのハビコリ。
<問題点:失望!>
”教育”という対象を、幼児・学校教育として、「私は教育する人」「される人」と、安易に考えていないだろうか?
教育する人:教師・親(広く組織の先輩/上司)それに役人→ こちらの方が問題?とするとこの新法に沿って、やればやるほど致命的になるのではないか。
(とくにまじめな国民だけに、ワナに堕ちやすい?)
これからの高齢社会は、”生涯学習”とともに成熟して行くはず。
学校教育は、その基礎作りの段階で、教育のすべてであるはずがない。
つまり、改正は”拙速”にすぎた感を禁じえない。
改正の趣旨は理解できても、これまでと大差なく、余り期待はできない気がする。
(実に残念!)
戦後60年の復興の功罪の総括として、
「個人の自由(放任?)・経済至上主義」をベースに「経済成長=幸せ」という”夢”に向かって「教育」は組み立てられてきたこと。
→ 今になってみれば”享楽的生活”と個人的価値観だけが支え。
→ この先にあるはずの共有できる「普遍的価値観」の喪失
(ここで”美しい国”を具体化したものが欲しいなぁ)
ということを、共通認識とした上での改正だったのだろうか。
小手先の対症療法では、いくら法で「民主、自由、真理」など表現しても、”お題目”は空々しいものになるだろう。
*今日の新聞*
「国旗・国家懲戒処分、教職員173人、都を起訴」「思想の自由侵害」・・・喧嘩?両成敗! どっちもどっち!戦後の民主教育が”砂上の楼閣”だったことの証明か?
極端な例:「教育勅語」では、
絶対(天皇)からの教えという形で、
”臣民”として、国民全体に対する徳目を示し、とくに家族への愛、友人への信義などを謳いあげている。
この中では、「教育される人」だけを対象にしていない。
むしろ「教育する人」に対して、常に心がけるべき方向を示している。
(だから、両親はもちろん年配者が
教育勅語を暗唱しているのを、子供心に厳粛に感じたものだ)
教育勅語は、天皇を絶対化し、帝国主義の元凶のように言われるが、
参考にすべき点もある。
とくに声を出して読んでみると、ムダがなく格調高く美しい。
当時の為政者の、伝統重視かつ国際的認識が伺われ、反って普遍性があるように思う。
圧倒的な自民党政権で、いつの間にか「改正基本法」が2006/12/22施行された。
約60年ぶりの改訂。(1947/3/31旧法制定、その後1948/6/19教育勅語廃止)
いろいろと、改正の評価が行われているが、
私は、今のところ、次のような感想:
→ これまでと同じように実施されなければ”絵に書いたモチ”だから。
<良い点>
1.家庭教育(新設)、父母の責任と公的機関の支援(新設)、とくに幼児教育の重要性を明記
←旧法では、空白部分?そこに教師の独断と偏見が蔓延していた?
2.学校、家庭、地域住民の相互連携・協力を明記
←旧法では、家庭の役割がちょっとだけ。主体は公的機関(国、県、市町村)
3.宗教一般教育に言及(新設)
←宗教に無防備な国民から反省?オカルト宗教/占いのハビコリ。
<問題点:失望!>
”教育”という対象を、幼児・学校教育として、「私は教育する人」「される人」と、安易に考えていないだろうか?
教育する人:教師・親(広く組織の先輩/上司)それに役人→ こちらの方が問題?とするとこの新法に沿って、やればやるほど致命的になるのではないか。
(とくにまじめな国民だけに、ワナに堕ちやすい?)
これからの高齢社会は、”生涯学習”とともに成熟して行くはず。
学校教育は、その基礎作りの段階で、教育のすべてであるはずがない。
つまり、改正は”拙速”にすぎた感を禁じえない。
改正の趣旨は理解できても、これまでと大差なく、余り期待はできない気がする。
(実に残念!)
戦後60年の復興の功罪の総括として、
「個人の自由(放任?)・経済至上主義」をベースに「経済成長=幸せ」という”夢”に向かって「教育」は組み立てられてきたこと。
→ 今になってみれば”享楽的生活”と個人的価値観だけが支え。
→ この先にあるはずの共有できる「普遍的価値観」の喪失
(ここで”美しい国”を具体化したものが欲しいなぁ)
ということを、共通認識とした上での改正だったのだろうか。
小手先の対症療法では、いくら法で「民主、自由、真理」など表現しても、”お題目”は空々しいものになるだろう。
*今日の新聞*
「国旗・国家懲戒処分、教職員173人、都を起訴」「思想の自由侵害」・・・喧嘩?両成敗! どっちもどっち!戦後の民主教育が”砂上の楼閣”だったことの証明か?
極端な例:「教育勅語」では、
絶対(天皇)からの教えという形で、
”臣民”として、国民全体に対する徳目を示し、とくに家族への愛、友人への信義などを謳いあげている。
この中では、「教育される人」だけを対象にしていない。
むしろ「教育する人」に対して、常に心がけるべき方向を示している。
(だから、両親はもちろん年配者が
教育勅語を暗唱しているのを、子供心に厳粛に感じたものだ)
教育勅語は、天皇を絶対化し、帝国主義の元凶のように言われるが、
参考にすべき点もある。
とくに声を出して読んでみると、ムダがなく格調高く美しい。
当時の為政者の、伝統重視かつ国際的認識が伺われ、反って普遍性があるように思う。










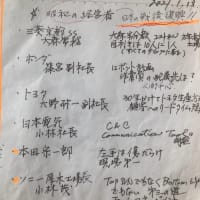
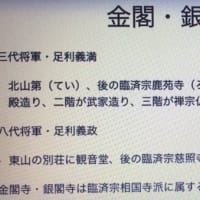
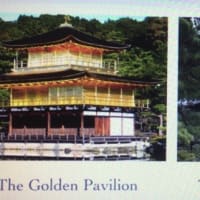
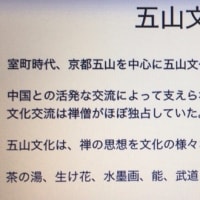
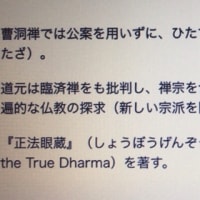
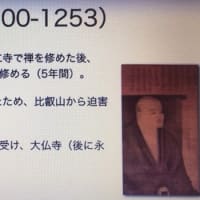
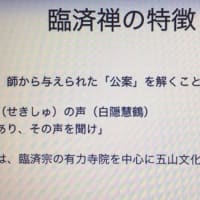
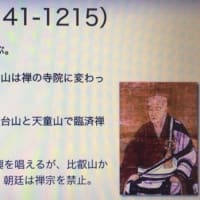
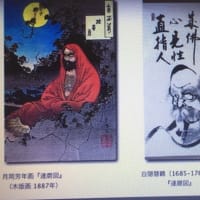
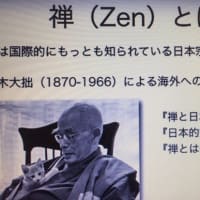
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます