
最近、外国ものミステリーにはまっている。
本ではなく、ケーブルTVのMysteryチャンネル。
各国の人気シリーズだけに、それぞれのキャラクターとストーリーが面白い。
[名探偵モンク(米)]:
潔癖症の私立探偵の細かな観察力と推理で、コメディを交えて難問解決。明るく聡明な美人アシスタントも魅力的で、花を添える。
[REX(オーストリア)]:
シェパード犬が主役、訓練された演技と犯人逮捕のスピード感のあるアクションが見もの。ハンサム刑事のプライベートな女性関係をちりばめ、犬が嫉妬する様がほほえましい。
[バーナビー警部(英)]:
ロンドン郊外の田園を舞台に、素朴な村人たちに起こる陰惨な事件には、ほとんど高齢の男女がらんでいる。
老いてなお、恋と性の飽くなき追求、個人主義の国の面目躍如といった感じ。
[ミス・マープル(英)]:
アガサクリスティ原作、人間観察と詮索好きなおばあチャン(マープル)の推理力は鋭く、冷静で緻密。
[グルメ探偵ネロ・ウルフ(米)]:
美食と蘭が趣味の肥満の探偵ネロ、食卓には、毎日お抱えのシェフ自慢の豪華な料理が並ぶ。
捜査はアシスタント任せ、それに基く天才的な推理が強み。
そして一番のお気に入りは、
[女警部ジュリー・レスコー(仏)]:
美人な上に、男顔負けの正義感とトラブルに対する決断力は、部下の厚い信頼とチーム力を引き出す。
別居中の夫(弁護士)とも時々bed in、新しい恋人もよく登場し、いかにも性に寛容なフランスを実感できる。
娘2人も、boy friendの関係で、よく犯罪に絡むが、本人の自由と責任を尊重。
外泊にも、「ゴム製品は持った?」と、母レスコーは、わが子を一人のladyとして扱う。
それぞれの国の生活・習慣や題材が違うが、共通して感じるのは、
警視や警部、刑事、探偵が、仕事の中でも自分の個性とか人間性を生かしていること。
悪を取り締まる側にも、個人的なミスや邪悪な心もあり、犯罪に絡むこともある。
それを認めた上での組織のあり方やストーリーの展開が、日本とはだいぶ違うように感じる。
彼らは、自由にやっているようでも、捜査力や勇敢さや推理力などプロとしての誇りを何よりも大切にしている。
先月、アメリカ人の牧師に、
「欧米では、白黒をはっきりさせて割り切るので、日本のあいまい文化が理解できないのでは?」
彼曰く「白黒をはっきりさせて、敢えて”自由”をとる。自分の責任で」
なるほど、と思った。アメリカの銃規制も、個人の自由を侵す、として容認されている。
日本のあいまいさは、世間とか空気に支配されていて、”自由”とは程遠いような気がする。
警察、学校、会社で、それぞれに「らしさ」が求められ、個人の都合は抑えなければならない。
警察官が悪いことをするとはけしからん、先生はまじめで模範的、会社のイメージを壊さないように、とか、誰でも自分の組織を、強く意識して働いているのではないだろうか。
今、地球規模で世界は狭くなり、それぞれの組織は昔ほど広い世間ではなくなった。
狭くなってきた世間を意識して、個人を殺して職務を果たすこと、そうだとすると自分のやりたいこと、本当の自由は無いことになる。そこには、自分の責任や使命感の自覚もなく、経営のプロ、技術のプロといった専門能力も必要としない。
経営者、政治家から一社員まで、これが蔓延してきた背景にあるのではないか。
福島第一原発の事故の謝罪で、東電の経営者がいかにもうつろな表情で頭を下げていたが、彼らは自分の自由意志ではなく、国策や組織に預けて職務をこなしただけ、だから責任も感じようがないのかも知れない。
"みんなで渡れば怖くない、事なかれ主義”これは日本の組織にまだ強く残っている、どうしょうもなく根強い文化だと思う。
組織という狭くなっている世間で完璧を目指すだけでなく、もっと広い世界に目を向けて組織の中で、個人の自由と責任を考える働き方が大切な気がする。仕事という部分から、人生という全体最適へ。
「もしドラ」ですっかり有名になったP.F.ドラッカーも、「個人が幸せなるために、組織のマネジメントが重要なんだ、その逆ではない」という意味のことを言っている。
本ではなく、ケーブルTVのMysteryチャンネル。
各国の人気シリーズだけに、それぞれのキャラクターとストーリーが面白い。
[名探偵モンク(米)]:
潔癖症の私立探偵の細かな観察力と推理で、コメディを交えて難問解決。明るく聡明な美人アシスタントも魅力的で、花を添える。
[REX(オーストリア)]:
シェパード犬が主役、訓練された演技と犯人逮捕のスピード感のあるアクションが見もの。ハンサム刑事のプライベートな女性関係をちりばめ、犬が嫉妬する様がほほえましい。
[バーナビー警部(英)]:
ロンドン郊外の田園を舞台に、素朴な村人たちに起こる陰惨な事件には、ほとんど高齢の男女がらんでいる。
老いてなお、恋と性の飽くなき追求、個人主義の国の面目躍如といった感じ。
[ミス・マープル(英)]:
アガサクリスティ原作、人間観察と詮索好きなおばあチャン(マープル)の推理力は鋭く、冷静で緻密。
[グルメ探偵ネロ・ウルフ(米)]:
美食と蘭が趣味の肥満の探偵ネロ、食卓には、毎日お抱えのシェフ自慢の豪華な料理が並ぶ。
捜査はアシスタント任せ、それに基く天才的な推理が強み。
そして一番のお気に入りは、
[女警部ジュリー・レスコー(仏)]:
美人な上に、男顔負けの正義感とトラブルに対する決断力は、部下の厚い信頼とチーム力を引き出す。
別居中の夫(弁護士)とも時々bed in、新しい恋人もよく登場し、いかにも性に寛容なフランスを実感できる。
娘2人も、boy friendの関係で、よく犯罪に絡むが、本人の自由と責任を尊重。
外泊にも、「ゴム製品は持った?」と、母レスコーは、わが子を一人のladyとして扱う。
それぞれの国の生活・習慣や題材が違うが、共通して感じるのは、
警視や警部、刑事、探偵が、仕事の中でも自分の個性とか人間性を生かしていること。
悪を取り締まる側にも、個人的なミスや邪悪な心もあり、犯罪に絡むこともある。
それを認めた上での組織のあり方やストーリーの展開が、日本とはだいぶ違うように感じる。
彼らは、自由にやっているようでも、捜査力や勇敢さや推理力などプロとしての誇りを何よりも大切にしている。
先月、アメリカ人の牧師に、
「欧米では、白黒をはっきりさせて割り切るので、日本のあいまい文化が理解できないのでは?」
彼曰く「白黒をはっきりさせて、敢えて”自由”をとる。自分の責任で」
なるほど、と思った。アメリカの銃規制も、個人の自由を侵す、として容認されている。
日本のあいまいさは、世間とか空気に支配されていて、”自由”とは程遠いような気がする。
警察、学校、会社で、それぞれに「らしさ」が求められ、個人の都合は抑えなければならない。
警察官が悪いことをするとはけしからん、先生はまじめで模範的、会社のイメージを壊さないように、とか、誰でも自分の組織を、強く意識して働いているのではないだろうか。
今、地球規模で世界は狭くなり、それぞれの組織は昔ほど広い世間ではなくなった。
狭くなってきた世間を意識して、個人を殺して職務を果たすこと、そうだとすると自分のやりたいこと、本当の自由は無いことになる。そこには、自分の責任や使命感の自覚もなく、経営のプロ、技術のプロといった専門能力も必要としない。
経営者、政治家から一社員まで、これが蔓延してきた背景にあるのではないか。
福島第一原発の事故の謝罪で、東電の経営者がいかにもうつろな表情で頭を下げていたが、彼らは自分の自由意志ではなく、国策や組織に預けて職務をこなしただけ、だから責任も感じようがないのかも知れない。
"みんなで渡れば怖くない、事なかれ主義”これは日本の組織にまだ強く残っている、どうしょうもなく根強い文化だと思う。
組織という狭くなっている世間で完璧を目指すだけでなく、もっと広い世界に目を向けて組織の中で、個人の自由と責任を考える働き方が大切な気がする。仕事という部分から、人生という全体最適へ。
「もしドラ」ですっかり有名になったP.F.ドラッカーも、「個人が幸せなるために、組織のマネジメントが重要なんだ、その逆ではない」という意味のことを言っている。










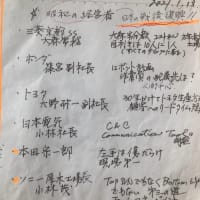
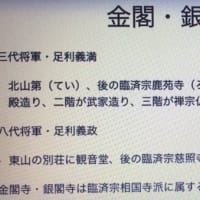
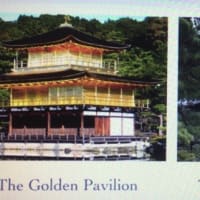
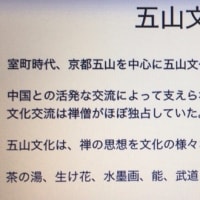
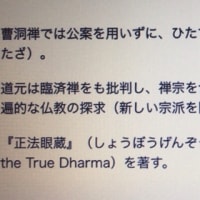
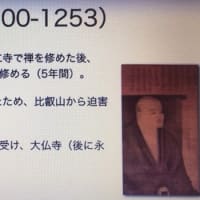
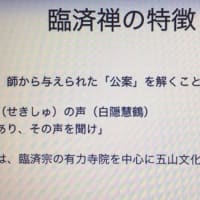
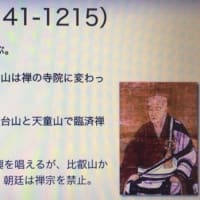
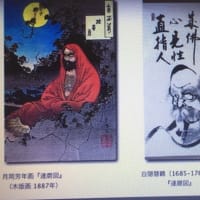
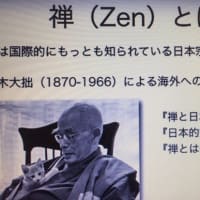
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます