
今、国会での“税と社会保障の一体改革”でのテーマは、、財政赤字・増え続ける社会保障費・消費税アップ。
民主党の頼りなさはあるが、一昔前の自民党政権のときよりも、何が問題か、分かりやすくなってきた。
(青っぽい財務、上っ面理解の厚労、問題外の防衛という各大臣には失望)
国会中継からも、ますます政府への信任が崩れ、財政破綻が現実味を帯びて感じられる。
楽観論もあるが、悲観論に目を向けて調べてみた。
日本の国債は、95%が国内で消化されているから安心」というのはおかしいようだ。
閉鎖的な国内政策のせいで、海外からの魅力が薄れている証拠。
国内資金が、何かのきっかけ(大災害、大不況)で、国債から引き揚げたら、海外の受け皿がないということだ。
2010年からは、ついに税収より国債発行額の方が大きくなった。
幸(政府には)か不幸か、年金基金・ゆうちょなど機関投資家は、資金運用のノウハウがないから、
今は国債で安心を買っているだけ。
厚生年金積立金の国債残高:2010末119兆円(2003/3月138兆円から目減り)
国民年金積立金では:同上75兆円(同上99兆円から目減り)
年金受給者が積みたてていると思っている保険料は、ほとんどが国債で運用され、
このままいくと、両方とも2020~2030年には尽きる。
ゆうちょ銀行:150兆円(残高の80%)、簡易保険70兆円(残高の70%)が国債で運用。
分散投資するにはノウハウがないから、過ぎた国債依存は危うい?と言える。
郵政改革前の公社時代は、一括して財投→国債で消化されていたからやむ負えない。
これは、銀行・生保も同じ、金融機関全体が“空気”に左右され安全第一、自己責任でリスクをとらない、状態。
海外の破綻国の事例:
(ケース1)
2000アルゼンチン国債の格下げ→国民の政府不信から資金が流出
2001.12.1預金凍結、海外送金、外貨取引の国内禁止、対外債務支払いの一時停止
IMF研究report:
「国家債務危機の“経験則”」1972~2002年IMF支援国(22ケ国)での共通点
①累積債務が増大と支払い不能 →××日本も該当(GDPの2倍)
②外貨準備高に比べ過剰な短期債務の累積 →◎該当せず(外貨準備1兆ドル/対外純資産266兆円)
③自国通貨の過大な評価、景気の大幅悪化 →〇今のところ問題無し
日本国債の暴落のシナリオ
ケース1)国民が金融機関の“いい加減な運用”と政府の信任の限界のNO!→国債資金引き上げ→暴落
ケース2)海外の機関投資家がデリバティブを使い“カラ売り”→日本国債暴落→市場金利の上昇→日本経済への不信→国債売り・・・負のスパイラル。
*ヘッジファンドなどが、世界で一番大きく暴落を仕掛けやすいのが日本国債と言われる。
2010/3末から海外投資家のデリバティブ取引(先物、オプション)が増大していると言われる。
(実際に2009年に発生、このときはゆうちょ銀行が引受け収まった)
ケース3)財政再建→歳出削減・税収アップ→消費冷え込み・経済成長鈍化→税収減→国債返済能力低下
*まさに、今国会で議論されている消費税アップか成長戦略が先か?の問題につながる。
アクセルとブレーキの踏み加減が難しい。
ケース4)更なる国債の格下げ→海外の日本経済への不信(国内グローバル企業の海外移転)→国内空洞化に拍車
海外での日本国債は、スペイン、イタリア並みのリスク・プレミアム(上乗せ金利)が課せられている。
2010/1月には、中国より大きくなった。
(米)S&P格付けも、2010/ 1月AAからAAネガティブに、
ムーディーズでも、2009年Aa3からAa2に、それぞれ格下げされている。
『超低金利が続いた後に、国債暴落が起きるのはなぜか?』
経済大国からの没落の直前の低金利:1619伊ジェノバ、1700代後半オランダ(チューリップ・バブル)、1897大英帝国の事例に学ぶ。
経済繁栄→ 資本蓄積→ 資産バブル→ 不況→ 低金利→ 他の経済大国の追い上げ→ 主力産業の没落→一段の不況→ 不況対策のため金融緩和→ 過剰資金で国債消化→ 長期金利の低下→ 国債増大→ ××ある日突然国債の暴落・金利急騰 →財政破綻へ。
昨日の国会でも、日銀と政府の連携を強め、場合によっては日銀法の改正の話まで出ている。(日銀の国債直接引受け?円を刷ること)
この連鎖によると、日本の現状は最後の段階にあることは間違いない。
追記)2012.2.14ついに、日銀は全員一致で、インフレ目標1%(緩やかなインフレ理解から)、資金供給65兆円(10兆上積み)を公式宣言した。消費税アップの中では、期待通りの消費拡大と積極投資がうまくいくとは思えないが、、、
民主党の頼りなさはあるが、一昔前の自民党政権のときよりも、何が問題か、分かりやすくなってきた。
(青っぽい財務、上っ面理解の厚労、問題外の防衛という各大臣には失望)
国会中継からも、ますます政府への信任が崩れ、財政破綻が現実味を帯びて感じられる。
楽観論もあるが、悲観論に目を向けて調べてみた。
日本の国債は、95%が国内で消化されているから安心」というのはおかしいようだ。
閉鎖的な国内政策のせいで、海外からの魅力が薄れている証拠。
国内資金が、何かのきっかけ(大災害、大不況)で、国債から引き揚げたら、海外の受け皿がないということだ。
2010年からは、ついに税収より国債発行額の方が大きくなった。
幸(政府には)か不幸か、年金基金・ゆうちょなど機関投資家は、資金運用のノウハウがないから、
今は国債で安心を買っているだけ。
厚生年金積立金の国債残高:2010末119兆円(2003/3月138兆円から目減り)
国民年金積立金では:同上75兆円(同上99兆円から目減り)
年金受給者が積みたてていると思っている保険料は、ほとんどが国債で運用され、
このままいくと、両方とも2020~2030年には尽きる。
ゆうちょ銀行:150兆円(残高の80%)、簡易保険70兆円(残高の70%)が国債で運用。
分散投資するにはノウハウがないから、過ぎた国債依存は危うい?と言える。
郵政改革前の公社時代は、一括して財投→国債で消化されていたからやむ負えない。
これは、銀行・生保も同じ、金融機関全体が“空気”に左右され安全第一、自己責任でリスクをとらない、状態。
海外の破綻国の事例:
(ケース1)
2000アルゼンチン国債の格下げ→国民の政府不信から資金が流出
2001.12.1預金凍結、海外送金、外貨取引の国内禁止、対外債務支払いの一時停止
IMF研究report:
「国家債務危機の“経験則”」1972~2002年IMF支援国(22ケ国)での共通点
①累積債務が増大と支払い不能 →××日本も該当(GDPの2倍)
②外貨準備高に比べ過剰な短期債務の累積 →◎該当せず(外貨準備1兆ドル/対外純資産266兆円)
③自国通貨の過大な評価、景気の大幅悪化 →〇今のところ問題無し
日本国債の暴落のシナリオ
ケース1)国民が金融機関の“いい加減な運用”と政府の信任の限界のNO!→国債資金引き上げ→暴落
ケース2)海外の機関投資家がデリバティブを使い“カラ売り”→日本国債暴落→市場金利の上昇→日本経済への不信→国債売り・・・負のスパイラル。
*ヘッジファンドなどが、世界で一番大きく暴落を仕掛けやすいのが日本国債と言われる。
2010/3末から海外投資家のデリバティブ取引(先物、オプション)が増大していると言われる。
(実際に2009年に発生、このときはゆうちょ銀行が引受け収まった)
ケース3)財政再建→歳出削減・税収アップ→消費冷え込み・経済成長鈍化→税収減→国債返済能力低下
*まさに、今国会で議論されている消費税アップか成長戦略が先か?の問題につながる。
アクセルとブレーキの踏み加減が難しい。
ケース4)更なる国債の格下げ→海外の日本経済への不信(国内グローバル企業の海外移転)→国内空洞化に拍車
海外での日本国債は、スペイン、イタリア並みのリスク・プレミアム(上乗せ金利)が課せられている。
2010/1月には、中国より大きくなった。
(米)S&P格付けも、2010/ 1月AAからAAネガティブに、
ムーディーズでも、2009年Aa3からAa2に、それぞれ格下げされている。
『超低金利が続いた後に、国債暴落が起きるのはなぜか?』
経済大国からの没落の直前の低金利:1619伊ジェノバ、1700代後半オランダ(チューリップ・バブル)、1897大英帝国の事例に学ぶ。
経済繁栄→ 資本蓄積→ 資産バブル→ 不況→ 低金利→ 他の経済大国の追い上げ→ 主力産業の没落→一段の不況→ 不況対策のため金融緩和→ 過剰資金で国債消化→ 長期金利の低下→ 国債増大→ ××ある日突然国債の暴落・金利急騰 →財政破綻へ。
昨日の国会でも、日銀と政府の連携を強め、場合によっては日銀法の改正の話まで出ている。(日銀の国債直接引受け?円を刷ること)
この連鎖によると、日本の現状は最後の段階にあることは間違いない。
追記)2012.2.14ついに、日銀は全員一致で、インフレ目標1%(緩やかなインフレ理解から)、資金供給65兆円(10兆上積み)を公式宣言した。消費税アップの中では、期待通りの消費拡大と積極投資がうまくいくとは思えないが、、、










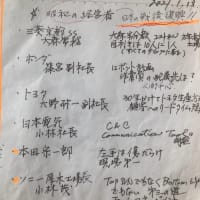
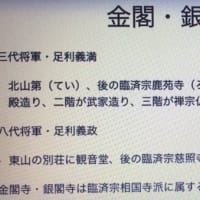
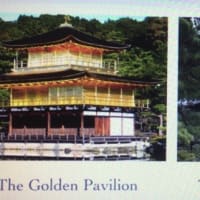
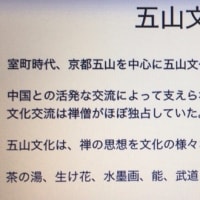
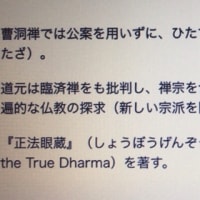
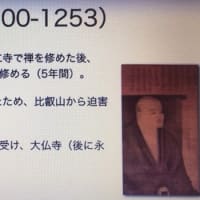
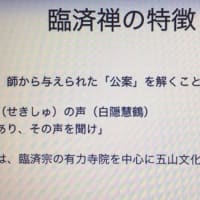
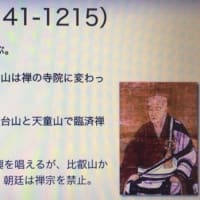
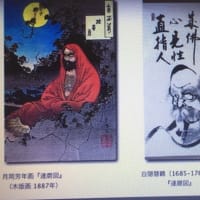
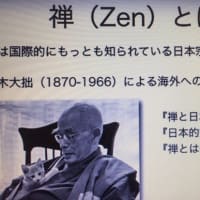
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます