
国家予算は、社会保障費増で95兆円に膨らみ、反面、デフレと円高で税収は落ち込む一方で、半分は赤字国債に頼る。
累積負債は1,000兆円、このままでは国家財政破綻の怖れがあり、消費税のアップは避けられないという。
財政赤字が、どのように財政破綻とつながるのだろうか?
ケース1:
2010/10アイルランド政府が自国の銀行の債務を肩代わりして、IMFやEU諸国からお金を借りて、債務返済した。政府の債務ではなかったが、民間銀行から政府に債務が転嫁された。
ケース2:
2011/秋、ギリシャ財政破綻は、過去の公務員や年金受給者のために、EU諸国から借金し、給与や年金を使い果たした。
その尻拭いとして、現在の国民からの増税や公共サービスの削減により、外国への返済に苦しんでいる。
まさに“孫子の代に借金”
背景には、20%を占める公務員の労組が強いなど、歳出削減ができず、ついには“政府の粉飾会計”までしてユーロに加盟していた。
2004に批判され、2009秋には、ギリシャ政府も認めた。債務不履行(デフォルト)に陥る可能性が大きい。
日本の国の借金はどうか?
対外純資産=対外資産574兆円―対外負債330兆円=244兆円(これは“世界最大のお金持ち国家”)2010年末現在。
日本政府の負債総額は、1,050兆円(2010年末現在、地方自治体分も含み)
うち、国債727兆円で、40%が銀行/保険20%/年金10%強/日本銀行8%/年金基金4%/海外と個人が各5%。
つまり、外国からの借金は極めて少なく、大半が国民からの借金。
個人家計1,450兆円のほとんど800兆円強が現金・預金→銀行預金→預金超過分が国債で消化されている。
「日本政府が、銀行など金融機関を経由し、国民から借金し、利子を含め返済している」
国民はお金を貸している立場で、「国民一人当たり何百万円の借金」という表現はおかしい。
でも、政府がこの借金を、国民からの税金に肩代わりさせたとき、政府の借金が国民の借金になる。(消費税などの増税で)
一方、政府の資産総額1,050兆円には、国債等77.2兆円/外貨準備115.5兆円など金融純資産は471兆円強で、世界最大。(純負債は約580兆円)このほか、莫大な固定資産も持つ。
参考)アメリカ連邦政府に負債残高は、法定上限14兆2900億ドル(1,100兆円)を突破する見込み。2011/8月時点。
また、政府の利払い/GDP比率は1.3%で、主要国中最低。GDP比参考)ギリシャ9%、アメリカ1.8%、イギリス2.3%、イタリア5.8%。意外に、借金の負担は少なく収まっている。
これは国債金利が世界最低水準(10年以上1.5%程度)で推移しているから。
長期金利参考)EU破綻国(ギリシャ、アイルランド、ポルトガル)は軒並み8%を超え、さらに急騰、それでも外国はお金を貸してくれない。政府の債務不履行とは、こういう状態のことで、日本は“財政破綻から最も遠い国“と言える。
国会でも、歳出削減と消費税10%アップで財政優先か、デノミ・円高是正による景気対策優先か、
各党の主張が対立していて、それぞれのストーリーも論理的でないようで、素人には分かりにくい。
アメリカもEU諸国の財政危機も、原発と同じで、”制御不能”の状態。
今、世界は「歴史の危機の真っただ中」、グローバリゼーションの終焉の流れに向かいつつある、という見方がある。
いわく、グローバリゼーションとは、欧米人の「蒐集コレクション」の一手段とか。
米英は、マネー蒐集のために金融のグロ-バル化→2008リーマン・ショックに至った。
独仏は、「領土」蒐集のためにEUの統一により域内のグローバル化に突き進んだ。
その結果が、EU諸国の債務危機の連鎖だという。
世界経済を俯瞰するという意味で、なかなか説得力がある。
国民経済は、次の3つの指標で観るべきだという。
①バランスシート
日本の全経済主体の資産と負債の状況(2010年末現在)
資産/負債額(兆円)政府:471/1,050、金融機関:2,787/2,769、一般企業:813/1,170、家計:1,490/360、NPO:54/18、純資産249(総資産約5,615兆円)
つまり、一般企業も、政府を上回る負債残高を持っているが、将来への投資・成長のためには当たり前と言える。
同じように、政府の借金もゼロにすることはないし、税率が極端に高い北欧諸国を除き、すべての国が中長期的に政府の負債残高を増やしている。
参考)2000/2009年比:米・仏・英1.8~2.4、中国・韓国3.4~3.8、これに対して日・独・伊は1.5以下に収まっている。とくに、中国・韓国の「国の借金」の増え方は、この10年間日本の倍以上で推移している。
(ロシアだけは、資源・エネルギー価格の高騰による政府の歳入が増大→外国からの借金返済で10年前の水準を維持)
家計資産:バブル崩壊時(1990)に1,017兆円だったが、2010年末には1,490兆円に増えた。
ゼロ金利なのに、日本人はお金を貯めこむ一方なのはなぜか?
デフレが長期化し、雇用不安や将来不安が大きくなり、政府の景気対策が家計の「金融資産」に化けている。
日本銀行は、日本政府の「子会社」、そのため「日本円とは、政府の借用証書(負債)そのもの」、つまり「国の借金と日本円の紙幣とは、ほとんど同じこと」違うのは、金利の支払いが必要か否か。
②GDP
マクロ的には、「GDPが速いスピードで増えている場合は、景気がいい、遅いか減少しているときは景気が悪い」
GDPとは、その国の「生産の規模」と「支出の規模」そして「所得の規模」という三つの面を同時に図ることができる。“GDPの三面等価”と呼ぶ。
マクロでは、国民一人あたりのGDPが、経済的な豊かさを表す。
社会保障を充実させようとしたら、最終的にはGDPを拡大させるしかない。
福祉は天から降ってこない(田中角栄)
国内の付加価値の積み上げ=生産面のGDPで、最終生産財の販売価格から「輸入」という外国企業の付加価値を差し引いた=支出面のGDPで、両者は完全に一致する。これと分配面のGDPもすべて一致する。
政府の負債/名目GDP比率の推移:(2000/2010比)
分子が余り増えていないのに、比率が200%以上→分母の名目GDPが全く増えていないから。
参考)米・英・独・仏は100%未満、成長する中国・韓国・ロシアは40%未満
しかし、財政破綻しつつあるギリシャは140%。
日本の財政悪化は、政府の借金が増えているためではなく、名目GDP(付加価値)が成長していないことが主因。
③経常収支
経常収支=(1)貿易収支(モノの輸出入)+(2)サービス収支(海外旅行)+(3)所得収支(海外投資)+(4)経常移転収支(開発国への援助)の4つの合計。
日本の対外純資産は、20年近く「世界一」、理由は単に日本の経常収支の黒字を延々と続けているから。
円高対策として、政府が為替介入で円をドルと交換したら、外貨準備高が増える。
2011年度は、ついに(1)貿易収支が31年ぶりに赤字、したがって経常収支も大きく縮小した。(2010/17兆円から10兆円に)
原因は、東日本大震災、円高、タイ洪水の影響が大きいと言われるが、日本経済の前ブレとなるかも?
(2)サービス収支と(4)経常移転収支は、常に赤字、今後は(3)所得収支で黒字を稼ぐ構造になっており、
大手企業の海外シフトが潮流になっているから、これは加速されるだろう。
すでに、モノ作り大国・貿易立国から投資立国になっている。(2005からは貿易収支<所得収支に)
今のところ、この3つの指標からは、楽観論になりそうだ。










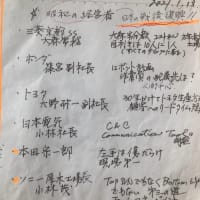
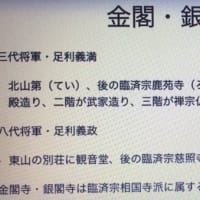
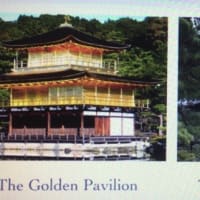
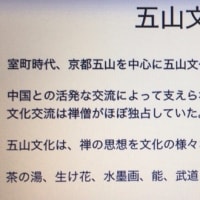
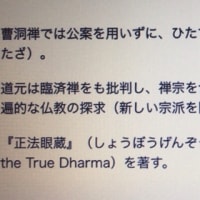
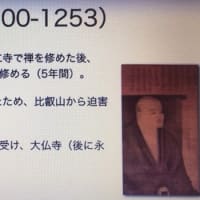
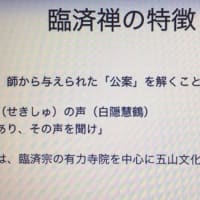
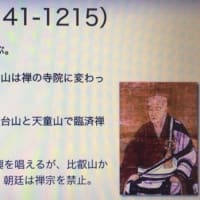
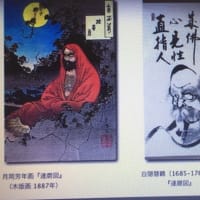
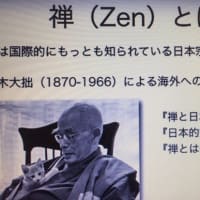
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます