
前に計画していた秩父:三峯神社に紅葉を見に行ってきた。
西武秩父駅で友人と待ち合わせ、土曜日とあって、車内は紅葉見物らしい人で混んでいた。
ほとんどが年配者、とくに、5万分の一の地図を見入ったり、じっと外の景色を眺める一人旅の老人や2,3人連れの高齢女性が目立つ。
秩父駅が近くなると、途中の駅々で、三々五々と降りはじめる。
若い女性:山ガールが10人くらい連れだって改札に向かっていて頼もしい!
秩父駅は、5,6年前に、12月の秩父夜祭りに来たことがある。
そのとき、町の目抜き通りを見て歩いたが、セメント産業などを中心に、以前はもっと栄えていたことが伺える。
駅の仲見世商店街は、今でも華やかな感じで、翌日の中津川紅葉まつりや12月初めの夜祭りを控えて、大きなポスターや飾り付けがしてある。菊の展示がちょうど見ごろで美しい。
駅前ロータリーの大きなイチョウが黄色く色づき華を添えている。


秩父駅の仲見世 菊の展示 駅前のイチョウ
ここから、バスで1時間半近く、秩父三津峯神社に向かう。
半分ほどの距離を、荒川沿いの国道を進むとダム手前で、曲がりくねった山道になった。
渓谷が段々深くなるにつれ、車窓からの眺めは赤く、黄色く染まってくる。
やっぱり、もみじの朱色鮮やかに目に焼きつく!
朝は今年一番の冷え込みとかで、神社の駐車場でバスから降りた時は、さすがに震えが出るほど。
三峰神社の創建は、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)で、ここから雲取山2017(日本百名山)、白岩山、妙法山の3つが並んで見えることから三峰神社と命名したとある。
鳥居の手前に、秩父多摩甲斐国立公園のビジターセンターがあり、クマやキジなどの動物はく製や生態、山を開いた先人の解説がある。



神社からの眺め ビジターセンター 三ツ鳥居 もみじ
鳥居は大1小2と三つが並び、三ツ鳥居といって珍しい。
左には、秩父宮記念博物館があり、神社の歴史や信仰に関する常設展があるようだ。秩父の宮という名は、こことの縁からか?
本殿まで階段の両側には「入谷講」とか「川越講」とかの碑が並ぶ、檜30万本とか書いてあり、寄進額のことだろう。
三峯講と言って、御嶽講や富士講などと同じように、山伏とか修験者とかが、各地に参拝を説いて回った山岳信仰の集まりのようだ。
石段とか、灯篭などほとんどが寄進で作られている。日本武尊の像もある。
日本武尊は、実在したかどうか?
日本書紀、古事記に出てくる神話の中でも、勇猛な武将を組み合わせたもの、という説が分かりやすい。
天皇の系譜で、皇太子ということになる。
─垂仁─景行は┼成務
└日本武尊─仲哀─応神─仁徳 ┬履中
└反正 

日本武尊の像 お茶屋さんのハクセイ
『野火の難』説話は有名:
野火に囲まれたヤマトタケルは、「草薙剣」で周囲の草をなぎ払い、向かい火をつけて難を逃れたのであるが、この説話は、静岡の焼津神社と草薙神社に伝承されているとのこと。熱田神宮の三種の神器の一つ”剣”のことか?
拝殿、本殿は、日光東照宮のように鮮やかな彩色彫刻で飾られ、華やか。
祭神は、イザナギ・イザナミノミコトで、クニ造りのカミ、山犬(オオカミ)がヤマトタケツノミコトを導いたお使いの神と言う。
真偽のほどは分からないが、2000年もの間 山岳信仰の対象として引き継がれてきた事実は、文化遺産として貴重だと思う。
拝殿の石段の両側に樹齢700年という大杉がそびえ、パワースポットになっている。
2人づつ、両手を幹に当て、気を戴いている。但し、お参りで献金をした人のみ御利益あり。



拝殿 拝殿 ご神木 大輪登竜橋
下りは、表参道を林の中を小ハイキング、と思ったら、これがかなりの急坂で、古の参拝者も大変苦労したと思われる。
参道は、倒木や鉄砲水で荒れたところが目立つ。
ほとんどすれ違うハイカーもなく、3hrくらいの間に登り3人、下り5人くらいだった。
中年男性が多く、女性は二人ずれの母子らしい一組、歩きなれている感じだ。
途中、宿坊のような空き家があった。
これだけの神社と参道を維持するだけの資金が集まるのだろうか?と余計な心配もしたくなる。
同行の友人は、膝と腰が痛むと言うので、できるだけ休みながらどうにか大輪バス停に着く。
パンフには、うどん・お食事・まんじゅうなどの店が載っているが、営業している気配なし。
ここから西武秩父まで1hr40m、荒川の支流に沿って、曲がりくねった国道を走る。結構混んでいて、立ったままバスを下りたときは、もうすっかり暗くなっていた。
明日の紅葉まつりは、この秩父駅も大賑わいだろう。
駅前の、そば屋さんの味はいま一つの感じだったが、名産の豚のみそ漬けが付いていた。

清浄の滝 大輪か登竜橋からの荒川渓谷










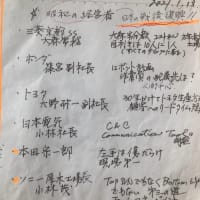
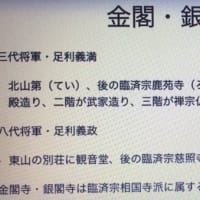
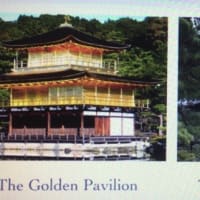
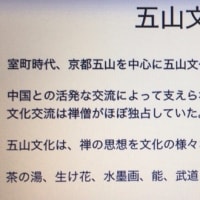
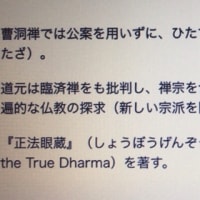
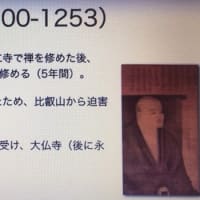
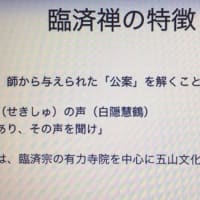
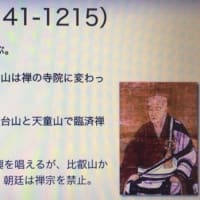
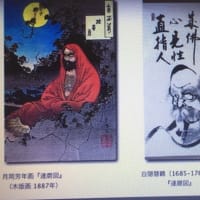
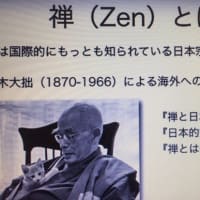
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます