
今日の毎日論説委員の記事で、菅首相が防衛幹部との会談で次の発言を挙げ、為政者の国防・文民統制の認識不足と”平和ボケ”について懸念している。
首相曰く「昨日予習したら、防衛省は自衛官ではないそうだ」 「改めて調べたら、首相は自衛隊の最高の指揮監督権を有すると規定されていた」
さすがに、統合幕僚長は「冗談だと思う」とフォローしたという。
日本国憲法 第66条
「第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」
自衛隊法
(内閣総理大臣の指揮監督権)
「第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」
(戦前の大日本国帝国憲法では、第11条:「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」であった)
「文民」という語は日本国憲法を制定する際に造られた言葉で、第9条に関して自衛(self-defence)を口実とした軍事力(armed forces)保有の可能性があると危惧して、連合軍の極東委員会がcivilian条項を入れるように求めた。しかし当時の日本語にはcivilianに対応する語がなかったため、「現在、軍人ではない者」に相当する語として、「文官」「地方人」「凡人」などの候補が挙げられた。「文官」では官僚主義的であるとされ、「文民」という語が選ばれた。
第二次世界大戦以前には軍人が内閣総理大臣を務めることが多々あり、その反省から現行の日本国憲法第66条第2項で明記されている。
一般的な「文民」は、「一般市民」、「文官(一般公務員、警察官を含む)」、「非戦闘員(銃器を所持しない者)」のニュアンスを持ち、「軍隊(現在の日本においては防衛省・自衛隊)の中に職業上の地位を占めていない者、もしくは席を有しない者」を指すと考えられている。
文民統制・シビリアンコントロール(Civilian Control Over the Military)とは民主主義国における軍事に対する政治優先または軍事力に対する民主主義的統制をいう。つまり、主権者である国民が、選挙により選出された国民の代表を通じ、軍事に対して、最終的判断・決定権を持つ、という国家安全保障政策における民主主義の基本原則である。 軍については、一般的に最高指揮官は首相・大統領とされるが、これは、あくまでも、軍に対する関係であって、シビリアン・コントロールの主体は、立法府(国会・議会)そして究極的には、国民である。このため、欧米では、その本質をより的確に表現するPolitical Control(政治的統制)、あるいは、民主的統制・デモクラティックコントロール(Democratic Control Over the Military)という表現が使われることが、より一般化しつつあるという。
改めて、文民統制のことを調べてみると、民主主義の基本に関する認識として、冒頭の菅首相の発言は極めて大きな問題であることが分かる。(そして何よりも、国会議員それも首相の立場で、こんな無知を公言するという感覚に危惧を覚える)
民主党政権は”政治主導”による改革を旗印にして元気よくスタートしたが、与党としての対応もチグハグなまま、来月の代表選の内部抗争劇でも、国民の失望を絶望に変えつつある。
菅首相のこのような問題だけでなく、前原国交省など自分の専門以外の基本的認識を欠く内閣が、複雑な国政レベルの難題を主導できるのだろうか。
首相曰く「昨日予習したら、防衛省は自衛官ではないそうだ」 「改めて調べたら、首相は自衛隊の最高の指揮監督権を有すると規定されていた」
さすがに、統合幕僚長は「冗談だと思う」とフォローしたという。
日本国憲法 第66条
「第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」
自衛隊法
(内閣総理大臣の指揮監督権)
「第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」
(戦前の大日本国帝国憲法では、第11条:「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」であった)
「文民」という語は日本国憲法を制定する際に造られた言葉で、第9条に関して自衛(self-defence)を口実とした軍事力(armed forces)保有の可能性があると危惧して、連合軍の極東委員会がcivilian条項を入れるように求めた。しかし当時の日本語にはcivilianに対応する語がなかったため、「現在、軍人ではない者」に相当する語として、「文官」「地方人」「凡人」などの候補が挙げられた。「文官」では官僚主義的であるとされ、「文民」という語が選ばれた。
第二次世界大戦以前には軍人が内閣総理大臣を務めることが多々あり、その反省から現行の日本国憲法第66条第2項で明記されている。
一般的な「文民」は、「一般市民」、「文官(一般公務員、警察官を含む)」、「非戦闘員(銃器を所持しない者)」のニュアンスを持ち、「軍隊(現在の日本においては防衛省・自衛隊)の中に職業上の地位を占めていない者、もしくは席を有しない者」を指すと考えられている。
文民統制・シビリアンコントロール(Civilian Control Over the Military)とは民主主義国における軍事に対する政治優先または軍事力に対する民主主義的統制をいう。つまり、主権者である国民が、選挙により選出された国民の代表を通じ、軍事に対して、最終的判断・決定権を持つ、という国家安全保障政策における民主主義の基本原則である。 軍については、一般的に最高指揮官は首相・大統領とされるが、これは、あくまでも、軍に対する関係であって、シビリアン・コントロールの主体は、立法府(国会・議会)そして究極的には、国民である。このため、欧米では、その本質をより的確に表現するPolitical Control(政治的統制)、あるいは、民主的統制・デモクラティックコントロール(Democratic Control Over the Military)という表現が使われることが、より一般化しつつあるという。
改めて、文民統制のことを調べてみると、民主主義の基本に関する認識として、冒頭の菅首相の発言は極めて大きな問題であることが分かる。(そして何よりも、国会議員それも首相の立場で、こんな無知を公言するという感覚に危惧を覚える)
民主党政権は”政治主導”による改革を旗印にして元気よくスタートしたが、与党としての対応もチグハグなまま、来月の代表選の内部抗争劇でも、国民の失望を絶望に変えつつある。
菅首相のこのような問題だけでなく、前原国交省など自分の専門以外の基本的認識を欠く内閣が、複雑な国政レベルの難題を主導できるのだろうか。










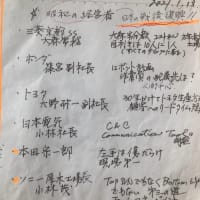
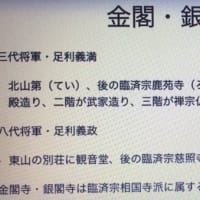
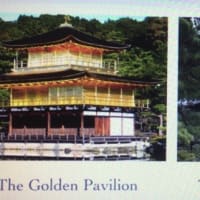
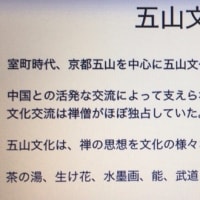
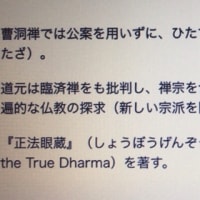
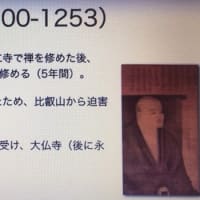
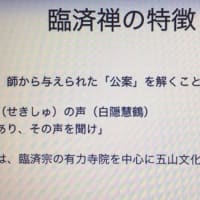
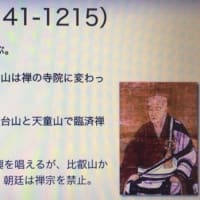
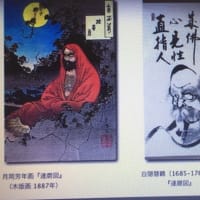
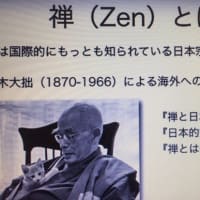
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます