
孫が来月から3歳保育園。いろんなことを覚えて手に負えなくなるだろうと覚悟している。
先日、ふと自分の子供時代を思い出し、ハーモニカで童謡を吹いてみた。
男の児(3.5歳と1.5歳)なので、テレビのヒーローに夢中、三銃士やウルトラマンのような勇ましい歌ばかり関心があるようなので、ちょっと情操を育てたいと思ったから。
「春の小川」「ふるさと」「なかよし」「夕焼け小焼け」などメロディーを思い出しながら、タイムスリップした。
孫は二人とも余り関心なし。
唱歌と童謡、それに昔からのわらべ歌はどう違うのだろうか。
netで調べてみた。
江戸時代は、わらべ歌:遊びの少なかったこともあり、遊び歌が多い。
「かごめかごめ」「通りゃんせ」てまり歌「あんたがたどこさ」や子守唄「竹田の子守唄」など郷愁をそそる。(去年、川越祭りのとき、川越城の裏に三芳野神社というのがあり、ここに「通りゃんせのふるさと」の大きな看板があった)
明治から大正初期には文部省唱歌「ふるさと」「春の小川」など戦時の情操教育の意味もあり、高名な作詞家・作曲家により、尋常小学・高等小学校で体系的に普及。
大正後期、鈴木三重吉の「赤い鳥」発刊(1918(T7))を契機に、「芸術的香気の高い子供向けの歌謡」として、童謡運動が起きる。
ちょうど、第一次世界大戦を経て、自由主義、大正デモクラシーの盛り上がりの中で、次代を担う子供たちへのメッセージとして、次々と童謡が作られた。
先日、ふと自分の子供時代を思い出し、ハーモニカで童謡を吹いてみた。
男の児(3.5歳と1.5歳)なので、テレビのヒーローに夢中、三銃士やウルトラマンのような勇ましい歌ばかり関心があるようなので、ちょっと情操を育てたいと思ったから。
「春の小川」「ふるさと」「なかよし」「夕焼け小焼け」などメロディーを思い出しながら、タイムスリップした。
孫は二人とも余り関心なし。
唱歌と童謡、それに昔からのわらべ歌はどう違うのだろうか。
netで調べてみた。
江戸時代は、わらべ歌:遊びの少なかったこともあり、遊び歌が多い。
「かごめかごめ」「通りゃんせ」てまり歌「あんたがたどこさ」や子守唄「竹田の子守唄」など郷愁をそそる。(去年、川越祭りのとき、川越城の裏に三芳野神社というのがあり、ここに「通りゃんせのふるさと」の大きな看板があった)
明治から大正初期には文部省唱歌「ふるさと」「春の小川」など戦時の情操教育の意味もあり、高名な作詞家・作曲家により、尋常小学・高等小学校で体系的に普及。
大正後期、鈴木三重吉の「赤い鳥」発刊(1918(T7))を契機に、「芸術的香気の高い子供向けの歌謡」として、童謡運動が起きる。
ちょうど、第一次世界大戦を経て、自由主義、大正デモクラシーの盛り上がりの中で、次代を担う子供たちへのメッセージとして、次々と童謡が作られた。

西条八十「かなりや」北原白秋「赤い鳥小鳥」野口雨情「十五夜お月さん」など小さいころ家族で口ずさんだ頃が懐かしい。
大正時代というのは、15年間と短く、世相も退廃的な面はあったが、人々の自由への憧れが強かったと言われる。
大正モダン建築は今でも各地で保存され、夢多き時代だったことが伺われる。
特に神戸を中心に阪神間での洋風建築物は、斬新的な建築家を育て、全国に広まったという。何年か前に、丹波篠山町役場として使用され、今は大正ロマン館となっているハイカラな佇まいを思い出す。
昨年末、愛知県の三河蒲郡で、大正高粋舎(ハイカラヤと読む)なるダイニングに行った。建物はもちろん、アプローチの照明、内部の装飾・調度品をすべて大正レトロで揃え、竹久夢二ワールドの照明壁など、オーナーのこだわりが感じられる。

このチェーン店は、”明治の文明開化を経て、使用文化を貪欲に吸収、日本の伝統文化の豊かさに目覚めた大正の再現”をコンセプトに全国規模で展開していることをnetで知った。
この時代、自由と夢を求めて羽ばたいた人々は、やがて関東大震災、世界大恐慌、そして第二次世界大戦へとそれぞれの運命を弄ばされていったことを、思うと哀しくなる。
自由と夢や希望に飢えていたから、その分だけ思いは強かったのだろうか。
僕たちの大正生まれの親世代はそういう時代を生きてきた。










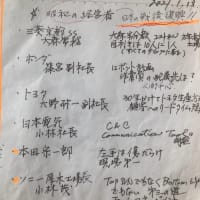
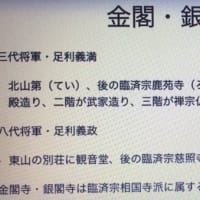
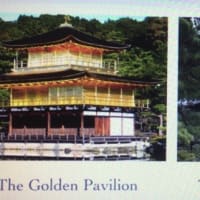
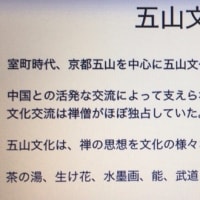
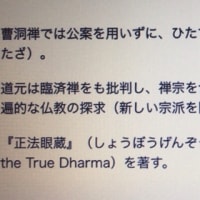
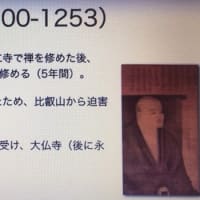
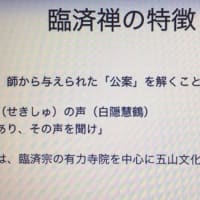
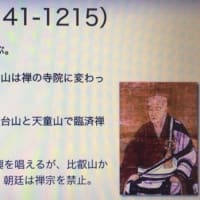
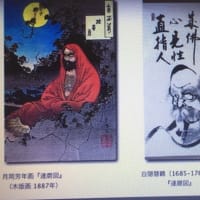
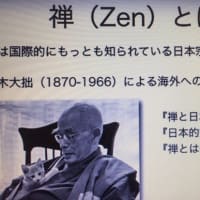
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます