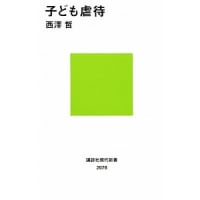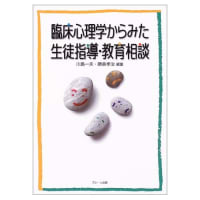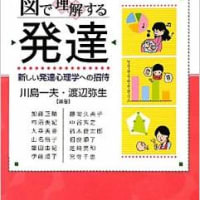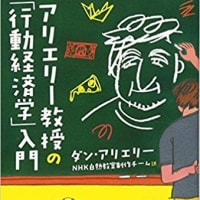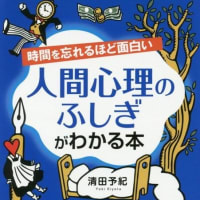1. 子どもに虐待をしないと固く誓っていたのにもかかわらず、思わず虐待をしてしまったという事例がネットで紹介されています。ひょっとしたらそのような癖を持つ親は他にもいるのではないかと思ってしまいますが、もし虐待的な行動をしてしまいそうになったら、その気持ちを落ち着かせるためにどのような方法をとることが適切だと思いますか。
答:それは、皆さんに、話したことのある「認知行動療法」のような方法でゆっくりと時間をかけて訓練が必要となります。いろいろ、簡単にできそうなことを考えてしまいますが、虐待をする親にとっては時間をかけて自分自身を訓練していかなければ、常に冷静でいることは難しいのだと思います。
2. もし友達に子どもができたとして、その友達が子どもに虐待をしている可能性があったとします。それを友達に言って、気づかせてあげることもできなくはないと思いますが、その友達の子育ての方法や親としてのプライドを傷つけてしまわないか心配です。かといって児童相談所などにすぐに相談してしまうのもどうかと思うときに、どのように友達に声をかけれぼよいでしょうか(友達としてやはり教えてあげるべきなのでしょうか。それとも、子どもの命のことを考えてすぐにでも児童相談所へすぐにでも相談した方がよいのでしょうか。)
答:基本的に、虐待が明らかであるならば、すぐにでも児童相談所に相談をするほうがいいでしょう。児相は、匿名でも受け付けてくれます。直接、話をするのは、私は避けたほうがいいと思います。これは、教員になってからもそうです。児童相談所の職員はプロですから、うまく話をつけてくれると思います。
3. アメリカでは親とお風呂に入ると「性的虐待」と言われるのはなぜですか?シャワー文化だから関係ないようにも思えますが…(一度聞いた質問だったらすみません)
答:これは、はっきりしたことは言えませんが、まず、日本と比較してアメリカは、里親が多いことがあげられます。アメリカでは、他の国からでも養子をもらって育てることを、社会貢献だと考えているからだと思いますが、人間関係の持ち方も違うのだと思います。また、養護施設にいるよりも家族でいる方が環境的に良い環境だと考えているのです。ある意味では、日本では、血がつながっていないと家族とはいえないと考えていますが、再婚の件数が多く、ステップファミリーが一般的なアメリカでは、家族は共同生活者のような感覚ではないかと思われます。
ということで、親とお風呂に入ると「性的虐待」になる可能性が強いために、そのような法律があるのでしょう。特に、アメリカの人の方が性的欲求が強いとか自制心が弱いということはないと思いますし・・・
4. グラフから分かるように「児童相談所における児童虐待相談対応の内容」の件数が平成9年から平成30年にかけて急増したのには何かわけがあるのでしょうか。虐待に対する調査の仕方や定義が変わったからでしょうか。
答:日本での虐待の定義は、2000年の「児童虐待の防止等に関する法律」で、4つの虐待が定義されました。しかし、不登校のような定義の改定による数字の変化のような影響を与えたとは思えません。私自身も、1990年代の半ばまで「虐待」という言葉には興味を持ちませんでした。しかし、1990年代の後半から、急激に「虐待」を含め空気を読めないなどの人間関係に関連した社会問題が多く発生してきました。さらに、虐待については、はじめは社会の問題として、核家族が増加したとか社会全体の人間関係が個人主義になったとかいろいろな要因が考えられるようになりました。虐待は、社会全体の問題というよりも、家族内の人間関係が原因であることが多いようの思えます。例えば、再婚した父親の実子でない子どもへの虐待は、いかにも、ライオンが実子でない子どもをかみ殺すような生物学的な要因を含んでいるかもしれません。また、家庭内での父親からのDVをそのまま子どもに返すようなこともあります。その考えると、虐待は社会における対人関係の変化と同時に家庭内の人間関係の変化が同時に生じたことから、急激な増加がみられたのではないかと考えられます。
5. 感想文の最後に「虐待を発見できるような社会環境の確立」と書いたのですが、私には隣人の協力と学校の家庭での子どもの実態把握くらいしか思いつきませんでした。川島先生はどうすれば迅速に虐待を発見できるような社会を作ることができると思いますか。
答:そうですね、やはり、隣人の協力と学校の家庭での子どもの実態把握(学校での子どもの観察)が基本になると思います。また、授業でも話しましたが、社会全体が一人一人の子どもは、親(特に母親)だけの子どもでなく、社会全体の宝物であり将来の社会を担う、大切な一人なのだという意識が出てこないと、どうしようもない気がします。
6. バイオハザードなどの暴力的な表現を含むゲームや映画に年齢制限が設けられているのは暴力を見て育った者が暴力を他者にしてしまうというような考え方があるからなのですか?
答:そうです。1960年代の研究ですが、バンデューラという人の有名なモデリングの研究があります。そこでは、暴力的なビデオを見た子どもは、親和的な子どものビデオを見た子どもよりも、その後の遊びや態度が攻撃的、暴力的になりました。ゲームや映画だけでなく、攻撃的、暴力的な両親に育った子どもは同様のことが起こります。虐待が遺伝するというのも、同様の現象が含まれていると考えられます。
7. 虐待をしてしまった親と接したことはありますか?もしあったらどんな様子でしたか?可能だったら教えてください。
答:いや、普段は普通ですよ。というより礼儀正しかったりします。ただ、自分より目下のものに対しては、思い通りにならないとすぐにカッと来てしまう傾向があるのでしょうね。そして内的(心の中では)には、家庭内などのストレスがあるだろうというのは感じられました。