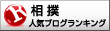ミヤマオビオオキノコ。
ヒメオビオオキノコ、タイショウオビオオキノコという類似種がいます。
3種の識別ポイントは、「複眼の径:複眼間の距離」の比率。
ミヤマオビオオキノコ 1:2.0~2.5
ヒメオビオオキノコ 1:1.5~2.0
タイショウオビオオキノコ 1:3.5
2倍以上離れているので、ミヤマオビオオキノコとしました。
旧名:
ゴーラムオオキノコ
分類:
コウチュウ目ヒラタム . . . 本文を読む
アオグロカミキリモドキ。
ガマズミ?の花に来ていました。
当日は風が強く、肝心の頭がマトモに写っていません。
でも、全体の色や形、上翅の隆条はハッキリ写っているので、合っていると思います。
来年、機会があったら、再チャレンジしたいですね。
分類:
コウチュウ目ゴミムシダマシ上科カミキリモドキ科カミキリモドキ亜科
体長:
6~9mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
成虫の見られる時期:
5~8 . . . 本文を読む
ヒメアシナガコガネ。
背中の模様は変化に富みます。
後脚は長い。
ガマズミ?の花に群れていました。
黒っぽい個体も。
オ♡シ♡リ♡
分類:
コウチュウ目コガネムシ上科コガネムシ科コフキコガネ亜科
体長:
6.5~11mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見られる時期:
5~8月(年1化、東北地方山間部では2年1化も)
幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:
成虫・・・花の蜜 . . . 本文を読む
ダンダラチビタマムシ。
老眼のKONASUKEには、発見時、昆虫なのかどうか、確証が持てませんでした
_| ̄|○
食痕の端っこの穴のようにも見えるし、何かの糞のようにも見えるし。
まぁ、その辺がこの昆虫の護身術なのでしょうけど。
クリの葉を食べている最中です。
※あくまでKONASUKEの観察です。
必ずしも同定ポイントとはならないことをご承知おきください。
①頭部:背中側から見た時、真ん中 . . . 本文を読む
ゴボウゾウムシ。
近似種にオオゴボウゾウムシとシラクモゴボウゾウムシがいますが、いずれも体の最大幅が、吻を除いた体長の1/2を超えません。
また、ゴボウゾウムシは他二種と比べて吻が細く、前脚腿節の先端部より細いとのこと。
オオゴボウゾウムシは前胸背の点刻が強く、互いに融合して強いシワ状。
鞘翅点刻も強く、間室はやや隆起して小じわ状。
大きさも
ゴボウゾウムシ5.6~8.5mm
オオゴボウゾウ . . . 本文を読む
キベリクビボソハムシ。
名前の通りで、前胸背や上翅が、橙色に縁取りされています。
しかし、この種は、背面の斑紋に変化が多いのだそうです。
この個体と同様のタイプでも、普通は、前胸背の模様がさらに上下二つに分かれるものが多いようです。
また、翅の模様も、黒紋が4つのタイプ、後方に二つのタイプ、全く黒紋を欠くタイプなど様々のようです。
(参考:原色日本甲虫図鑑(Ⅳ))
①体背面の斑紋:変化に富む
② . . . 本文を読む
キボシルリハムシ。
黒っぽい体に、前胸背板の両端が橙黄色のハムシ。
ビオトープ天神の里にて撮影。
HP
ブログ
Twitter
別名:
キボシナガツツハムシ
分類:
コウチュウ目ハムシ上科ハムシ科ツツハムシ亜科
体長:
4.5~6.5mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見られる時期:
5~8月
越冬形態?
エサ:
カンバ類、ヤナギ類、ハコヤナギ類、ハギ類、イタドリなどの葉 . . . 本文を読む
コシマゲンゴロウ。
この状態で見つけて、よ~く撮ろうと思ったら・・・
逃げられました。
これが今回の限界。
まぁ、今後の出会いに期待。
ビオトープ天神の里にて撮影。
HP
ブログ
Twitter
RDB:
東京都・絶滅種
松山市・絶滅危惧Ⅱ類
分類:
コウチュウ目肉食亜目ゲンゴロウ科
体長:
9~11mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:
3~11月(年1 . . . 本文を読む
キバネホソコメツキ。
前胸背が黄褐色なので、♀、ですね。
♂は暗褐色で、前胸背板は前翅より暗色。
2014年4月29日付の記事「鳳台院で見かけた生き物~甲虫編~」で、コメツキムシの1種としていたものは、キバネホソコメツキの♂であると思われます。
時期的にも、花にいたところも、状況証拠はバッチリ。
さらに、触角第2節+第3節≦第4節であるところも、ネット上の多くの画像と一致します。
分類:
コウ . . . 本文を読む
ムネアカオオトビハムシ(ムネアカオオホソトビハムシ)?
赤い前胸背、黒っぽい鞘翅、黒い頭、黒い脚、太く発達した後脚腿節。
タマアシノミハムシに似ていますが。
それにしては全体に細長いようです。
翅が青みを帯びていることと、全体に点刻を散らしているようなのが気になりますね。
同定間違いの可能性大です。
各脚脛節の腿節寄りは淡色のようです。
ムネアカオオトビハムシは、春に花で見られるようですが、 . . . 本文を読む
アトボシアオゴミムシ。
これも過去のリベンジ。
オサムシ科は暗い所にいる上に、チョコマカと動き回るので、ピンボケ・ブレブレになりやすいのです。
お気づきかも知れませんが。
ここのところ、未掲載種を掲載できていません。
同定が手強くなっていて、未同定の山が築かれつつあるのです
( ̄▽ ̄;)
再掲載の種で、とりあえず日々の更新を続けつつ。
同定できた種があり次第、載せて行きたいと思います。
①頭 . . . 本文を読む
ヤナギルリハムシ。
ヤナギ類の枝の付け根に居るのを見つけました。
越冬中と思われます。
大胆にヘアカットされた柳は、まだしばらく芽吹く気配はありません。
分類:
コウチュウ目ハムシ科ハムシ亜科
体長:
4mm前後
分布:
北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:
4~11月(年3~4化)
成虫で冬越し
エサ:
成虫・幼虫ともネコヤナギ、カワヤナギ、シダレヤナギ、タチヤナギ、ジャ . . . 本文を読む
ツヤケシハナカミキリ?
ムネアカクロハナカミキリの可能性もある?
分類:
コウチュウ目カミキリムシ科ハナカミキリ亜科
体長:
8~13mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:
5~8月(年1化)
幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:
成虫・・・ウツギ、クリ、イボタノキ、ムラサキシキブ、リョウブ、シシウド、セリ、ガマズミ、ノリウツギ、ミズキ、ノイバラなどの花の蜜
幼虫・・ . . . 本文を読む
ドウガネホソヒラタコメツキ(ドウガネヒラタコメツキ)。
明るいところで見ると、キラキラと細かく光を反射します。
体が細かい点刻に覆われているからでしょうね。
胸が異様に長くて、アンバランスな感じです(笑)
①青紫色の鈍い光沢がある
②前胸背は体の割に長い
③前胸背の正中線上に細長い楕円形の縦溝がある
④脚:黄褐色
⑤後角は長く鋭くトゲ状に張り出す
旧名:
ドウガネヒラタコメツキ
分類:
コウチ . . . 本文を読む
ツブノミハムシ。
キイチゴ類にいたので、キイチゴトビハムシかと思ったんですが。
キイチゴトビハムシはこんなに上翅の肩部が張らないようです。
また、上翅の点刻は点刻列になるようです。
ツブノミハムシは、主にナラ、サクラで見られるそうですが、キイチゴ類の新葉も好きだとのこと。
キアシツブノミハムシと酷似しますが、キアシ~は前・中脚が全体的に黄褐色をしていると。
画像は腿節が黒褐色をしていますので . . . 本文を読む