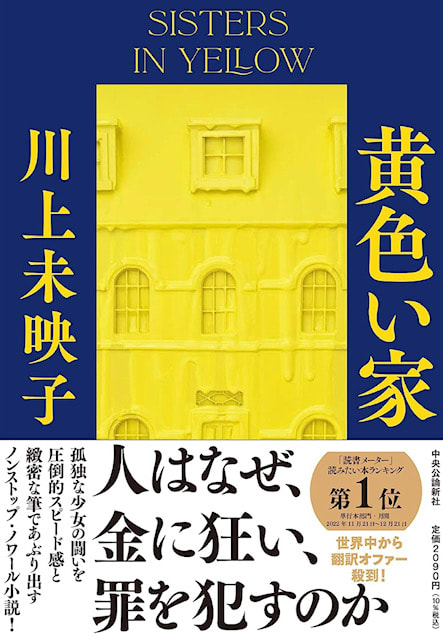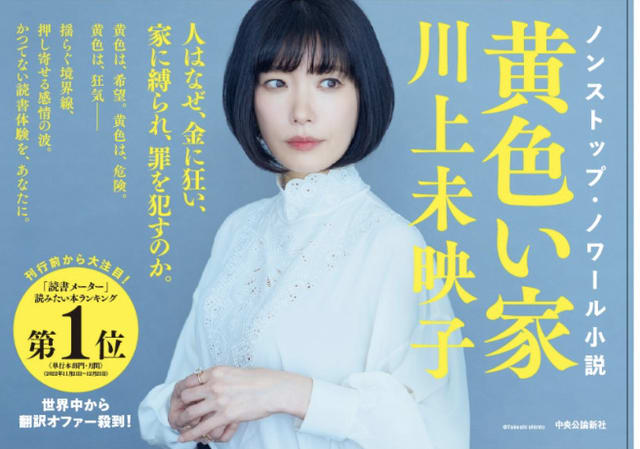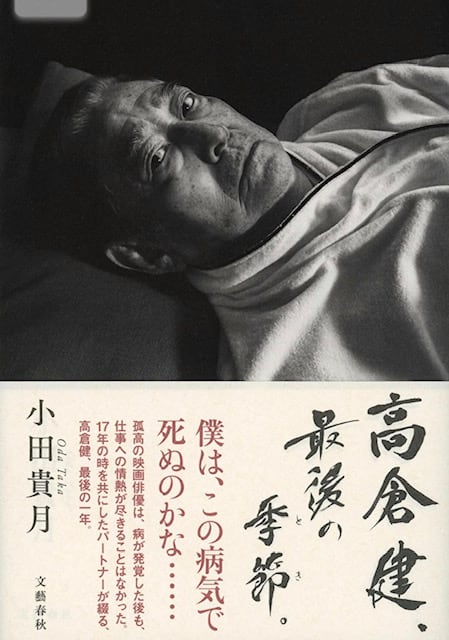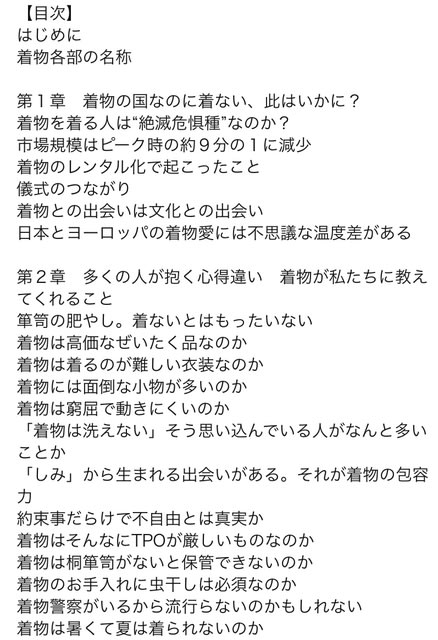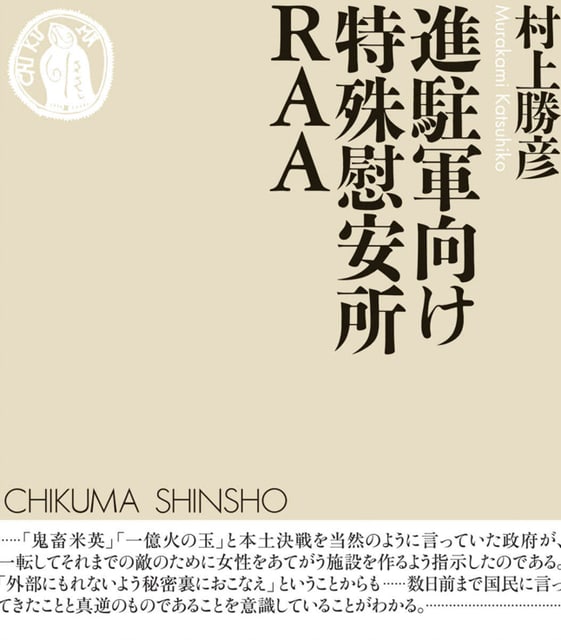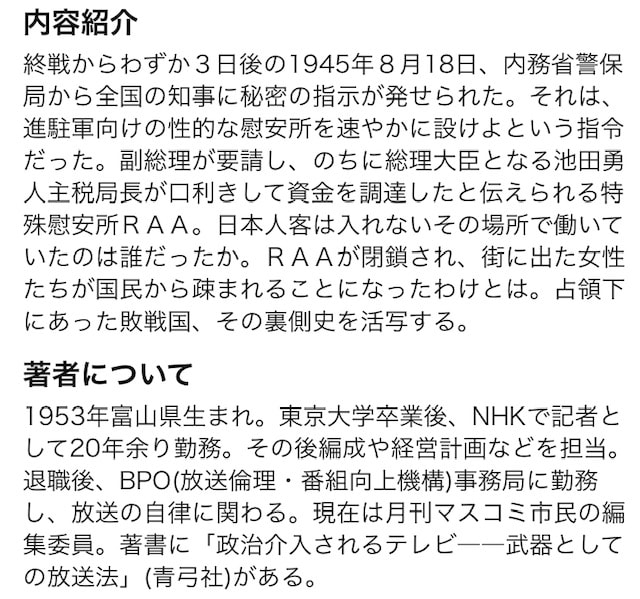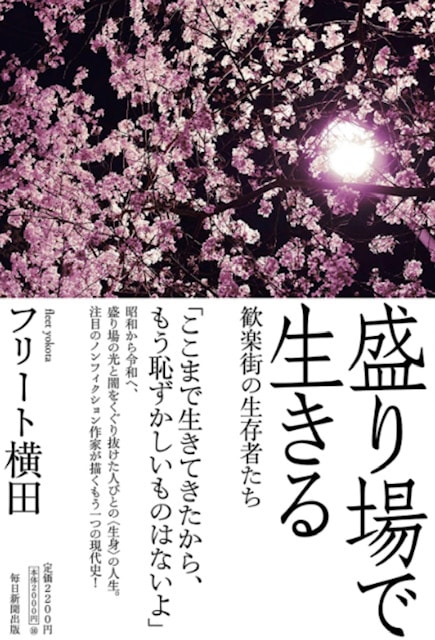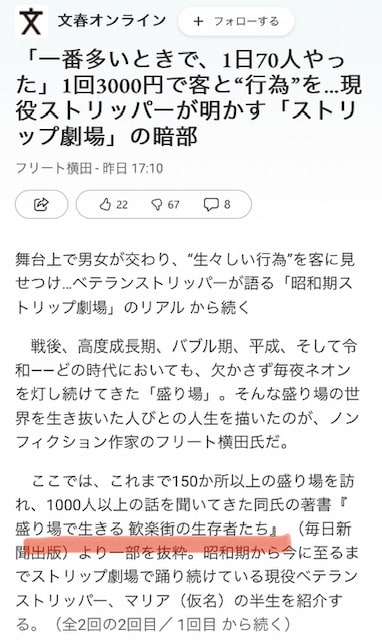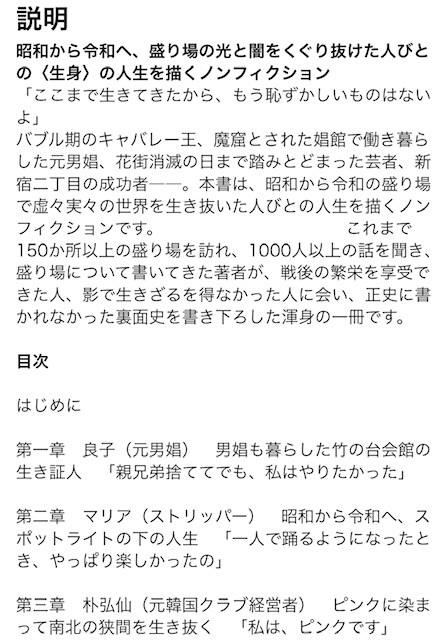◇

◇
この本が出版されたとき
「自分と妻の死後の出版のために書かれた自伝」
と帯にあるのを見て
随分と奇異に感じたものだったが
読み終えて想ったのは
これじゃ確かに
奥さんには読ませられんわなぁ~
というもの。
◇
この本の中で石原慎太郎氏は
自身が生涯で重ねた不倫の数々を
赤裸々に綴っているのだ。
◇
ご興味のある方は
御一読を !
◇
( kindle版あり )
◇
「 弟・裕次郎や家族への愛と感謝、
文学・政治への情熱と悔恨、
通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷……。
太陽のような輝きで、
この国を照らし続けた男が
死して初めて明かす「わが人生の証明」。
死の瞬間にも意識だけは
はっきりしていたいものだ。
出来ればその床の中で、
有無言わされぬ
たった一度の体験として迎える
自分の死なるものを意識を強め、
目を凝らして見つめてみたいものだ。
それがかなったならば、多分、
この俺は
つい昨日生まれたばかりのような気がするのに、
もう死ぬのかと思うに違いない。(本文より) 」
◇
( kindle版あり )
◇
(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)


◇
( kindle版あり )
◇
「 俳人・夏井いつきが、
季語を提示して募集した読者の投句を批評しながら、
俳句づくりのイロハから伝授。
さらに、超初心者2人「くじら」と「水流(つる)」
の成長の軌跡をコラムで紹介。
多くの人に俳句の楽しさを知ってもらう
「俳句の種まき運動」を展開する著者が、
「俳句は筋トレと同じで、
続けていけばいくほど
間違いなく筋力はついていきます。
それを『俳筋力』と呼んでいますが、
身についた筋肉は人を裏切りません。
『継続は力なり』とは、
まさに俳句修業そのものを言い表す言葉です」
とのコンセプトで、
投句者の作品を「学びの材料」に。
読み進むうちに、自然と俳句への理解が進み、
ノウハウが身につく。
教育誌『灯台』好評連載の書籍化。 」(内容)
◇
( kindle版あり )
◇
(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)
◇


◇
( kindle版あり )
◇
「 弟・裕次郎や家族への愛と感謝、
文学・政治への情熱と悔恨、
通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷……。
太陽のような輝きで、
この国を照らし続けた男が
死して初めて明かす「わが人生の証明」。
死の瞬間にも意識だけは
はっきりしていたいものだ。
出来ればその床の中で、
有無言わされぬ
たった一度の体験として迎える
自分の死なるものを意識を強め、
目を凝らして見つめてみたいものだ。
それがかなったならば、多分、
この俺は
つい昨日生まれたばかりのような気がするのに、
もう死ぬのかと思うに違いない。(本文より) 」
◇
( kindle版あり )
◇
(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)


◇
 |
京都うた紀行 歌人夫婦、最後の旅 (文春文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
( kindle版あり )
◇
先日、NHK のBSプレミアムと4K
で放送された
「あの胸が岬のように遠かった
~ 河野裕子と生きた青春」
をご覧になった方も多いと想うが、
◇
冒頭に掲げた「京都うた紀行 」は、
その河野裕子・永田和宏御夫婦の
最後となった旅の記録。
◇
以下は、その内容紹介。
◇
「 死別を前に
歌人夫婦が訪ねた歌枕の地
歌に魅せられ、
その歌に詠まれた京都近郊の地を
ともに歩いて綴った
歌人夫婦の記。
河野氏の死の直前に行われた
最後の対談を収録。 」
◇
 |
京都うた紀行 歌人夫婦、最後の旅 (文春文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
( kindle版あり )
◇




(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)