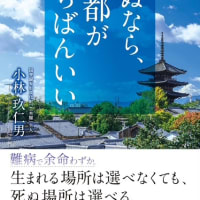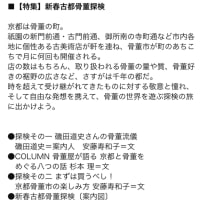◇
冒頭に掲げたのは、2007年からの月足チャート(楽天FX)。
◇
先日も見たように( → コチラ )、
トランプが大統領に就任した2017年以降
ドル円は105円近辺になると必ず反発する、、、、
ということを繰り返してきた。
◇
ドル円相場というのは
トランプ政権のこれまで3年半の間
無風に近い状態だったわけだ。
◇
トランプ大統領の日米間の巨額の貿易不均衡に由来する
対日強行発言にも関らず
これまで少なくともドル円相場に関しては
トランプが無関心だったということだろう。
◇
しかし、トランプ大統領就任以前のドル円相場について見ると
緑色で囲ったブレグジットで荒れに荒れた2016年の100円近辺、
黄色で囲った2011年の東日本大震災以降の円高(75円近辺)
とけっこう深い底を形成しているのが分かる。
◇
狭いレンジ内を上下するここ何年間かの凪のような時期は
むしろ例外で、ドル円相場というのは
歴史的にはかなりダイナミックに動くマーケットだったのだ。
◇
問題は、今回の円高がどこまで進むか ?
だが、その場合の最大のポイントは
これまでの円高局面と決定的に異なり
米国10年債の利回りが
空前の水準まで下げているということ。
◇
日米の金利差に着目し
米国債投資を進めてきた銀行や年金のドル買い需要は
これまでの円高局面では
必ずそれを反対方向に押し戻す機能を果たしてきたが、
ここまで利回りが低下してくるとそれも確実に減少する。
◇
同様に、スワップ狙いのFX投資家(いわゆるミセスワタナベ)のドル投資も
スワップの縮小につれて減少していこう。
スワップというのは金利差がかたちを変えたものにすぎないからだ。
◇
ようするに、何かのキッカケで円高方向に動き始めた場合、
それを押し戻す反対方向の需要が存在しない
(ないしは弱い)というのが今後のドル円相場、、、、
ということになる。
◇
極端な話、FRB が今後も利下げを続けて
米国も日本同様のゼロ金利となった場合、
ドルの需給は、貿易やM&Aなどによる直接投資といった
実需だけに絞られる、、、、
といった事態さえ想定される。
◇
金利差の無い世界では、これまで強いドルを支えてきた
キャリートレードというのがそもそも成立しなくなるのだ。
◇
もちろん、この先、米国債利回りが上昇に転じれば
ドル円の急反発も予想されるが、反対に
米国債利回りがこのまま低位で推移する、
(ないしはさらにその水準を切り下げていく)となると
円高は一層進むと考えるのが自然だろう。
◇
新型コロナの短期的な終息が見通せないなか、
個人的には、当面
ブレグジットの年の100円近辺を目指して
円高が進むのではないか、、、、と考えている。
◇
そして、その場合の円高も、
これまで円高になるたびに
それを押し戻す(阻止する)方向に働いてきた
金利差狙いの反対需要が不在のなか
意外と進ピッチで進むのではないか、、、とも。
◇
下は、平成の各年の為替と出来事を詳説した
「FX データブック 平成の為替31年」。
◇
◇
「 元号が変わった2019 年。 そして、平成の31年間の為替相場。
歴史は繰り返すとよく言いますが、チャートの動きや投資家たちの考えから その時、
どのような要因でドル円が動いていったのでしょうか ?
当時の為替チャートと各種データを元に検証し、解説していきます。
本書は過去の相場を振り返ることで現代の投資に活かすことを目的とした
現代のFXトレーダーに必要な情報をまとめた書籍です。
目次
第1章 平成元年~平成10年 バブル崩壊やアジア通貨危機に翻弄されるドル円相場
第2章 平成11年~平成18年 ITバブルや米国経済の悪化による円高トレンドからFXブームによる円安トレンドへ
第3章 平成19年~平成31年 リーマンショックの超円高時代からアベノミクスによる円安トレンド。
そして、トランプショックによる混迷へ
著者について
柳生大穂
金融や歴史を中心とした書籍・ムックなどを製作する編集プロダクション「バウンド」所属。
FXや株、投資信託などお金系中心のムックや書籍などを執筆・編集を行う。
これまでの過程で100人以上の投資家や識者に取材。
著書は「FXで稼ぐ人のテクニックシリーズ」「FXメタトレータースターティングガイド」
「FXメタトレーダーベストテクニック」
「ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる! 」など多数 」
◇
京都移住について考える・「老後は京都で」~トップページに戻る
( インスタグラム版「老後は京都で」は → コチラ )