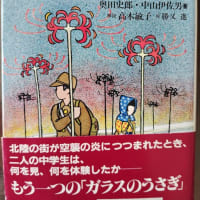続いて訪れたのが、6世紀末から7世紀末にかけて造られた吉見横穴古墳(横穴式石室)
の集合墓です。219基もの整然と並んで造られています。木の伐採中の為。中央の
階段を登って見晴らし台に登れなかったが残念です。

江戸時代の中頃から「不思議な穴」として人々に興味を持たれていたそうです。明治20年に
発掘を行い237基の横穴を発掘し住居でなく墓であるとの結論に至りました。下の方の
横穴に幻想的な緑色を放ち自生している「ヒカリゴケ」を肉眼で見ることが出来ました。

太平洋戦争末期(1944~1945年)に、集合墓の一部を陸軍が壊し、巨大なトンネルが
数多く掘られ地下軍需工場が造られた為、10数基の横穴墓が壊されしまいました。


吉見百穴から坂道を上って「武州松山城跡」を目指して歩きました。三方は市野川に
囲まれた要害の地にあり、北武蔵地域の要所である為、城をめぐる取り合いの攻防が
激しかったところです。左手の百穴から歩いて25分位だったと記憶しています。

ここから登って行きました。道なき道でした。

脇からイノシシが出てきそうな「けものみち」を全員頑張って頂上の城跡まで登りました。

本曲輪に全員到達できました。(城の中枢部であり、本丸御殿のような居住域兼
政務域を持ち、戦時には最終防衛線となるところ。)

ここ比企地方は15~16世紀にかけて扇谷上杉、山内上杉、公方足利氏達の騒乱が
絶えず支配者が頻繁に変わりましたが,やがて後北条の勢力下に加わった上田氏の
支配下に納まりその後、徳川の松平忠頼の時に廃城となったとのことです。

団体でないと怖くて登れません。皆で登れば怖くない。
 随分盛り沢山に見て回りましたが、地元からのバス旅行の為、歩数計では13000歩の記録でした。
随分盛り沢山に見て回りましたが、地元からのバス旅行の為、歩数計では13000歩の記録でした。